
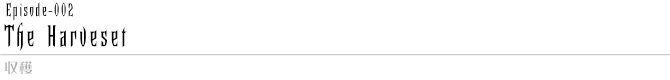
扉の向こうは一段と暗く、二メートル先を見るにも目を凝らさなければならないほどだった。ホグワーツ城にもいくつか暗い通路があったが、ここには微かに揺れる蝋燭も、足元を照らす松明もない。バフィーは踏み外さないよう慎重に階段を下りると、一度はたと足を止めた。東?東ってどっちだろう。
その疑問に答えるように、前方から音がした。何かの鳴き声だ。バフィーは反射的に顔を上げたが、すぐに足元に引き戻された。今、何かが足に触った。暗闇のせいで自由の利かない目をよく凝らしてみると、ネズミだった。逃げてきたのだ。と、いうことは——。
いつ何時でも動けるように、バフィーは頭の上に乗せていたサングラスを外し、ネズミが逃げてきた方向に足を進めた。
どこかから水の滴る音がする。それと自分の靴音だ。硬い石壁に何度も反響して、出所が紛れている。今のところ他には何も聞こえない。バフィーは濡れた壁を前に左折して、さらに奥へ奥へと進んだ。そのうちに、曲がり角に直面した。その向こう側から微かな明かりが漏れている。できるかぎり息を殺し、気配をひそめて、恐る恐る覗き込む——と、裸の電球が天井からぶら下がり、暗闇に頼りない明かりを供給していた。
その時、すぐ真後ろで靴の音がした。心臓が止まるかと思った。しかし、振り返って目の前にいたのは、なんと学校で待っているはずのザンダーだった。
「ここで何してるの?」
安心と焦燥が半分ずつ入り混じった心境で、バフィーは叱りつけた。
「バカなことさ。つけて来た!」
「そんな——」
「だってじっとしてられなかったんだよ……」
バフィーは溜め息をついた。「それは分かるわ。でももう帰って」
しかし、ザンダーはバフィーが思った以上に頑固者だった。
「嫌だ」
「ザンダー!これは命令よ」
「ジェシーは親友だもん。できるだけのことをしてやりたいんだよ」
暗がりに見たザンダーのまなざしは、いつものおちゃらけたザンダーのものではなかった。そう簡単にへし曲げられそうにない。バフィーは緊張をほどき、「ついて来て」と言うかわりに軽く首を傾けて見せた。
「それに、『魔法薬』の授業がサボれるしな」
それは聞かなかったことにした。
ザンダーの登場のお陰で、ずいぶんと気が楽になったのは確かだった。少なくとも、陰気な空気に呑まれることはなくなった。後ろをついてくる場違いに明るい声を軽く聞き流しながら、バフィーはエンジェルに言われた通りの方角に向かって慎重に進み続けた。
「オッケー、十字架、にんにく、心臓に突き刺す杭……」
ザンダーの声は緊張で微かに揺れていた。
「よくできました」
「やりぃ!……でも残念ながら何一つ持ってない」
「はい、これ」と、バフィーは懐にしまっていた木の十字架を背後の手に押し付けた。
「来ようか、どうしようか、迷うのに忙しくて、道具のことまで考える余裕がなかった——でも、これはあるよ」
突然、後ろから眩い明かりが差した。
「消してよ!」
バフィーは慌ててランタンを叩き伏せた。ザンダーには敵地に潜入しているという自覚が足りないらしい。
「ごめんごめん!」ザンダーが急いで謝った。「俺、明かりを出す呪文使えなくて……他には?」
「『他には』って?」
「退治に有効なもの」
「あー……火、首切りの道具、太陽光線、聖水、そんなとこ」
風向きや気配を気にしながら矢継ぎ早に挙げていくと、ザンダーが信じられないという声を上げた。
「首切ったことあるの?」
「ええ……前の学校でクィディッチやってた子に押さえつけられたことがあって……彼、その時はもうバンパイアだったんだけど、とにかく物凄く太い首で、あたしには小型ナイフだけしか——」ザンダーが青白い顔で弱々しく笑ったのを見て、バフィーは口をつぐんだ。「あ……こういう話、苦手だわね」
「いや、なんかすごく勇気づけられてる」
それから二人は特に会話をすることもなく、黙って地下道の奥へ入っていった。
一方、ハリーたちが授業に出ている間、ジャイルズは図書館に引きこもり、蔵書をすべてひっくり返して『収穫の日』についての情報を漁っていた。
「やがて彼らは集合し、『ベセル』から命が注がれる——『命』ねぇ……」
分厚いページをめくると、大袈裟な演出の版画が目についた。コウモリのような翼を生やした悪魔が、地上から地下にいる裸の男にエネルギーを注ぎ込んでいる場面だ。悪魔の足元にはおびただしい数の躯が転がっている。
「冬至を過ぎた最初の三日月の夜それは来る——すると……」ジャイルズはメガネをかけ、卓上のカレンダーに目を向けた。「……今夜か」
「まあ!藤色になるはずなのになんで?……待ってよ」
ウィローたちのテーブルのすぐ近くで、コーディリアがじれったそうにかき混ぜ棒を叩き付けたのが聞こえた。一年のグリフィンドール生とスリザリン生は、大鍋の横に広げた教科書と睨めっこしながら、二人一組になって、難しい『変色薬』の調合に手こずっているところだった。
「それにしても夕べはすごかったわ」
スネイプの目がマルフォイの鍋の中身に向いている隙を見計らって、コーディリアがハーモニーに話しかけた。
「バフィーが来てたんだけど——」三人はハッと顔を上げた。「——あんな変な子いないわよ。あたしを襲ったのよ!信じられる?」
ハーモニーは「またその話か」とばかりに適当な相槌を打った後、自分の鍋を覗き込んで溜め息をついた。
「やっぱり間違えたみたい」
「無理にやらなくてもこういうタルいことが好きな子いるじゃない……あの子何してる?」
コーディリアがウィローを顎で示したので、ハーモニーはウィローの手元をちらっと覗き込んだ。大鍋の中ではとっくに藤色の液体が冷めていて、机の上いっぱいに『地震と超常現象』や『悪の兆候』を広げてレポートを作成している真っ最中だった。
「あー……なんか別のことやってるわ」
ハーモニーが肩をすくめた。
「オッケー。で、次は右に四回でしょ……それとも火から下ろす……これだ!」
コーディリアはついに霧が晴れたような顔をした。ハーモニーは自信なさげに「かもね」と笑った。
「——で、さっきの続きだけど、あたしがトイレから出たらすっ飛んで来たの」コーディリアのおしゃべりが再開した。「杭持って、大声で、『殺してやる!殺してやる!』って、そりゃもうすごかったんだから!」
「誰が?」
大鍋の陰から、セオドール・ノットが顔をのぞかせた。
「バフィーよ」コーディリアが答えた。
「ほら、転校生」とハーモニーが言い足した。
「彼女が何?」
「完璧にイカれてる」
コーディリアの笑い声が気になって、ハリーたちはまた手を止めて顔を上げた。
「前の学校の話聞いた?」と、ハーモニー。「退学よ!」
ノットは「ワオ」と目を丸くしたが、コーディリアはリアクションを見せなかった。ハリーはかき混ぜ棒を握るロンの手がブルブルと震えているのを注意深く凝視した。
「それぐらい聞いても驚かないわ」
「なんで退学に?」ノットが聞いた。
「あー……それは彼女が異常だからよ」
ロンがかき混ぜ棒を背後に投げつけるよりも早く、ウィローが声を上げていた。「そんなことないわ」
スリザリン生がシーンと静まり返った。教室の反対側から、スネイプがマルフォイを誉めたたえる声が間抜けに響いて聞こえてくる。
「諸君、見たまえ。マルフォイ君がまたしてもやってくれた。左に三回半、右にきっかり四回、完璧なかく拌だ」
「え?」
コーディリアがウィローをきつく睨んだ。ハーモニーとノットもおかしなものを見る目でウィローを見た。ハリーとロンは昨晩の出来事のせいでウィローの頭がショートしてしまったに違いないと思った。
「異常じゃないわよ」ウィローが繰り返した。「知りもしないくせに!」
コーディリアの形の整った眉がくいっと吊り上がったのを見て、ハリーとロンは思わず身を寄せ合った。
「お言葉だけど、誰が生きてていいって言った?あたしがあんたの会話に割り込んだことある?いいえ。なぜ?退屈だからよ」
ウィローは何も言い返さなかった。大鍋から一すくいの『変色薬』を試験官に注ぎ込み、スネイプの教卓に提出に向かった。ちょうどそのタイミングで、ハーモニーとコーディリアの『変色薬』も完成した。
「オッケー。これで完成よ」
「とうとう悪夢の終わりが来たわ!オッケー、冷ますのはどうするの?」
コーディリアが杖を取り出して大鍋に向けた。
「『スコージファイ』よ」
ウィローが去り際に言った。
「スコージファイ?それ何?」
呪文を口にした途端、コーディリアの杖先から閃光が走り、大鍋の中身が一瞬にして空っぽになった。茫然とするハリーとロンの前で、コーディリアはショックのあまり言葉を失ってしまったようだった。
緊張はピークに達していた。警戒心が高まり、足取りは自然と遅くなってきた。ザンダーは長身の体を丸めて、しきりにキョロキョロしている。
「もうすぐよ」
バフィーは声を落として警告した。
「なぜ分かる?」
「ネズミがいないもん」
二人は分かれ道の前に出た。左右に道が延びているが、正面は壁だ。そこでザンダーはバフィーより一歩前に飛び出し、ランタンで床を照らした。うつ伏せに誰か倒れている。
「ジェシー!」ザンダーが叫んだ。
「大変!」
二人が駆け寄ると、ジェシーは驚いて飛び起きた。顔色が真っ青だ。ジェシーは見慣れた親友の顔を認識すると、ふらついた足でザンダーの首に抱きついた。
「ザンダー……」
「ジェシー、大丈夫か?」
バフィーはきつく抱擁を交わすザンダーの手からランタンを引き取り、ジェシーの足元にかがみ込んだ。
「大丈夫じゃないよ!全然大丈夫じゃない!早く逃げなきゃ……」
ジェシーの足首には鉄の足枷が嵌めてあった。地面に杭を打って繋げられている。
「俺たちにはバフィーがついてる」
ザンダーがなだめた。バフィーは「ジッとしてて!」と注意してから、杖で足枷を叩き折った。思った以上に金属音が響き渡った。
「……聞かれたかな?」
ジェシーが不安そうに呟いた。顔を上げた三人は、曲がり角の向こうに人影が揺らめくのを見つけた。誰の合図もなく、三人は同時に駆け出した。
「君らをおびき寄せたんだ。俺のこと……囮にして……」
ジェシーが泣きそうな声を上げた。
「今頃そんなこと言うなよ」ザンダーが言った。
次の曲がり角に差し掛かったところで、三人の前にバンパイアが三匹躍り出た。しわくちゃで生気のない顔に爛々とした笑顔を浮かべ、ライオンのような低い唸り声を上げている。
「おおっと……」
バフィーは慌てて止まった。すぐ後ろでジェシーがヒステリーを起こしている。
「なんだよ、もう勘弁してくれよ!」
「他に出口は?」
バフィーが急き込んだ。
「分かんない……こっちかも!」
ジェシーはバンパイアの真逆の方向に向かって走り出した。だが、いくらも行かないうちに、別のバンパイアと鉢合わせしてしまい、またしても立ち往生を食らった。
「ちょっと待って。来る時この通路を来た気がする……多分ね」
バフィーとザンダーはその言葉を信じて、ジェシーに続いて走った。
ところが、三人の行く先に待ち構えていたのは、小さな物置部屋だった。道はここまで一直線で、ドアは一つ、地下だから窓もない。完全に行き止まりだ。
「こ、これじゃあ出られないわ」
バフィーはうめいた。
「でも後戻りもできないぜ。なぁどうする?」
ザンダーに答えたのは、意外なことに、ジェシーだった。
「いい考えがある」
さっきまでのパニックが嘘のように、落ち着き払った声をしていた。不吉な予感に背筋を凍らせ、恐る恐る振り返ったザンダーが見たのは、希望を粉々に打ち砕いてしまうほど残酷な現実だった。
「——死ぬのさ」
ジェシーの顔はろうのように青白く、深いしわに覆われ、そして、鋭い牙をギラつかせていた。
その疑問に答えるように、前方から音がした。何かの鳴き声だ。バフィーは反射的に顔を上げたが、すぐに足元に引き戻された。今、何かが足に触った。暗闇のせいで自由の利かない目をよく凝らしてみると、ネズミだった。逃げてきたのだ。と、いうことは——。
いつ何時でも動けるように、バフィーは頭の上に乗せていたサングラスを外し、ネズミが逃げてきた方向に足を進めた。
どこかから水の滴る音がする。それと自分の靴音だ。硬い石壁に何度も反響して、出所が紛れている。今のところ他には何も聞こえない。バフィーは濡れた壁を前に左折して、さらに奥へ奥へと進んだ。そのうちに、曲がり角に直面した。その向こう側から微かな明かりが漏れている。できるかぎり息を殺し、気配をひそめて、恐る恐る覗き込む——と、裸の電球が天井からぶら下がり、暗闇に頼りない明かりを供給していた。
その時、すぐ真後ろで靴の音がした。心臓が止まるかと思った。しかし、振り返って目の前にいたのは、なんと学校で待っているはずのザンダーだった。
「ここで何してるの?」
安心と焦燥が半分ずつ入り混じった心境で、バフィーは叱りつけた。
「バカなことさ。つけて来た!」
「そんな——」
「だってじっとしてられなかったんだよ……」
バフィーは溜め息をついた。「それは分かるわ。でももう帰って」
しかし、ザンダーはバフィーが思った以上に頑固者だった。
「嫌だ」
「ザンダー!これは命令よ」
「ジェシーは親友だもん。できるだけのことをしてやりたいんだよ」
暗がりに見たザンダーのまなざしは、いつものおちゃらけたザンダーのものではなかった。そう簡単にへし曲げられそうにない。バフィーは緊張をほどき、「ついて来て」と言うかわりに軽く首を傾けて見せた。
「それに、『魔法薬』の授業がサボれるしな」
それは聞かなかったことにした。
ザンダーの登場のお陰で、ずいぶんと気が楽になったのは確かだった。少なくとも、陰気な空気に呑まれることはなくなった。後ろをついてくる場違いに明るい声を軽く聞き流しながら、バフィーはエンジェルに言われた通りの方角に向かって慎重に進み続けた。
「オッケー、十字架、にんにく、心臓に突き刺す杭……」
ザンダーの声は緊張で微かに揺れていた。
「よくできました」
「やりぃ!……でも残念ながら何一つ持ってない」
「はい、これ」と、バフィーは懐にしまっていた木の十字架を背後の手に押し付けた。
「来ようか、どうしようか、迷うのに忙しくて、道具のことまで考える余裕がなかった——でも、これはあるよ」
突然、後ろから眩い明かりが差した。
「消してよ!」
バフィーは慌ててランタンを叩き伏せた。ザンダーには敵地に潜入しているという自覚が足りないらしい。
「ごめんごめん!」ザンダーが急いで謝った。「俺、明かりを出す呪文使えなくて……他には?」
「『他には』って?」
「退治に有効なもの」
「あー……火、首切りの道具、太陽光線、聖水、そんなとこ」
風向きや気配を気にしながら矢継ぎ早に挙げていくと、ザンダーが信じられないという声を上げた。
「首切ったことあるの?」
「ええ……前の学校でクィディッチやってた子に押さえつけられたことがあって……彼、その時はもうバンパイアだったんだけど、とにかく物凄く太い首で、あたしには小型ナイフだけしか——」ザンダーが青白い顔で弱々しく笑ったのを見て、バフィーは口をつぐんだ。「あ……こういう話、苦手だわね」
「いや、なんかすごく勇気づけられてる」
それから二人は特に会話をすることもなく、黙って地下道の奥へ入っていった。
†††
一方、ハリーたちが授業に出ている間、ジャイルズは図書館に引きこもり、蔵書をすべてひっくり返して『収穫の日』についての情報を漁っていた。
「やがて彼らは集合し、『ベセル』から命が注がれる——『命』ねぇ……」
分厚いページをめくると、大袈裟な演出の版画が目についた。コウモリのような翼を生やした悪魔が、地上から地下にいる裸の男にエネルギーを注ぎ込んでいる場面だ。悪魔の足元にはおびただしい数の躯が転がっている。
「冬至を過ぎた最初の三日月の夜それは来る——すると……」ジャイルズはメガネをかけ、卓上のカレンダーに目を向けた。「……今夜か」
†††
「まあ!藤色になるはずなのになんで?……待ってよ」
ウィローたちのテーブルのすぐ近くで、コーディリアがじれったそうにかき混ぜ棒を叩き付けたのが聞こえた。一年のグリフィンドール生とスリザリン生は、大鍋の横に広げた教科書と睨めっこしながら、二人一組になって、難しい『変色薬』の調合に手こずっているところだった。
「それにしても夕べはすごかったわ」
スネイプの目がマルフォイの鍋の中身に向いている隙を見計らって、コーディリアがハーモニーに話しかけた。
「バフィーが来てたんだけど——」三人はハッと顔を上げた。「——あんな変な子いないわよ。あたしを襲ったのよ!信じられる?」
ハーモニーは「またその話か」とばかりに適当な相槌を打った後、自分の鍋を覗き込んで溜め息をついた。
「やっぱり間違えたみたい」
「無理にやらなくてもこういうタルいことが好きな子いるじゃない……あの子何してる?」
コーディリアがウィローを顎で示したので、ハーモニーはウィローの手元をちらっと覗き込んだ。大鍋の中ではとっくに藤色の液体が冷めていて、机の上いっぱいに『地震と超常現象』や『悪の兆候』を広げてレポートを作成している真っ最中だった。
「あー……なんか別のことやってるわ」
ハーモニーが肩をすくめた。
「オッケー。で、次は右に四回でしょ……それとも火から下ろす……これだ!」
コーディリアはついに霧が晴れたような顔をした。ハーモニーは自信なさげに「かもね」と笑った。
「——で、さっきの続きだけど、あたしがトイレから出たらすっ飛んで来たの」コーディリアのおしゃべりが再開した。「杭持って、大声で、『殺してやる!殺してやる!』って、そりゃもうすごかったんだから!」
「誰が?」
大鍋の陰から、セオドール・ノットが顔をのぞかせた。
「バフィーよ」コーディリアが答えた。
「ほら、転校生」とハーモニーが言い足した。
「彼女が何?」
「完璧にイカれてる」
コーディリアの笑い声が気になって、ハリーたちはまた手を止めて顔を上げた。
「前の学校の話聞いた?」と、ハーモニー。「退学よ!」
ノットは「ワオ」と目を丸くしたが、コーディリアはリアクションを見せなかった。ハリーはかき混ぜ棒を握るロンの手がブルブルと震えているのを注意深く凝視した。
「それぐらい聞いても驚かないわ」
「なんで退学に?」ノットが聞いた。
「あー……それは彼女が異常だからよ」
ロンがかき混ぜ棒を背後に投げつけるよりも早く、ウィローが声を上げていた。「そんなことないわ」
スリザリン生がシーンと静まり返った。教室の反対側から、スネイプがマルフォイを誉めたたえる声が間抜けに響いて聞こえてくる。
「諸君、見たまえ。マルフォイ君がまたしてもやってくれた。左に三回半、右にきっかり四回、完璧なかく拌だ」
「え?」
コーディリアがウィローをきつく睨んだ。ハーモニーとノットもおかしなものを見る目でウィローを見た。ハリーとロンは昨晩の出来事のせいでウィローの頭がショートしてしまったに違いないと思った。
「異常じゃないわよ」ウィローが繰り返した。「知りもしないくせに!」
コーディリアの形の整った眉がくいっと吊り上がったのを見て、ハリーとロンは思わず身を寄せ合った。
「お言葉だけど、誰が生きてていいって言った?あたしがあんたの会話に割り込んだことある?いいえ。なぜ?退屈だからよ」
ウィローは何も言い返さなかった。大鍋から一すくいの『変色薬』を試験官に注ぎ込み、スネイプの教卓に提出に向かった。ちょうどそのタイミングで、ハーモニーとコーディリアの『変色薬』も完成した。
「オッケー。これで完成よ」
「とうとう悪夢の終わりが来たわ!オッケー、冷ますのはどうするの?」
コーディリアが杖を取り出して大鍋に向けた。
「『スコージファイ』よ」
ウィローが去り際に言った。
「スコージファイ?それ何?」
呪文を口にした途端、コーディリアの杖先から閃光が走り、大鍋の中身が一瞬にして空っぽになった。茫然とするハリーとロンの前で、コーディリアはショックのあまり言葉を失ってしまったようだった。
†††
緊張はピークに達していた。警戒心が高まり、足取りは自然と遅くなってきた。ザンダーは長身の体を丸めて、しきりにキョロキョロしている。
「もうすぐよ」
バフィーは声を落として警告した。
「なぜ分かる?」
「ネズミがいないもん」
二人は分かれ道の前に出た。左右に道が延びているが、正面は壁だ。そこでザンダーはバフィーより一歩前に飛び出し、ランタンで床を照らした。うつ伏せに誰か倒れている。
「ジェシー!」ザンダーが叫んだ。
「大変!」
二人が駆け寄ると、ジェシーは驚いて飛び起きた。顔色が真っ青だ。ジェシーは見慣れた親友の顔を認識すると、ふらついた足でザンダーの首に抱きついた。
「ザンダー……」
「ジェシー、大丈夫か?」
バフィーはきつく抱擁を交わすザンダーの手からランタンを引き取り、ジェシーの足元にかがみ込んだ。
「大丈夫じゃないよ!全然大丈夫じゃない!早く逃げなきゃ……」
ジェシーの足首には鉄の足枷が嵌めてあった。地面に杭を打って繋げられている。
「俺たちにはバフィーがついてる」
ザンダーがなだめた。バフィーは「ジッとしてて!」と注意してから、杖で足枷を叩き折った。思った以上に金属音が響き渡った。
「……聞かれたかな?」
ジェシーが不安そうに呟いた。顔を上げた三人は、曲がり角の向こうに人影が揺らめくのを見つけた。誰の合図もなく、三人は同時に駆け出した。
「君らをおびき寄せたんだ。俺のこと……囮にして……」
ジェシーが泣きそうな声を上げた。
「今頃そんなこと言うなよ」ザンダーが言った。
次の曲がり角に差し掛かったところで、三人の前にバンパイアが三匹躍り出た。しわくちゃで生気のない顔に爛々とした笑顔を浮かべ、ライオンのような低い唸り声を上げている。
「おおっと……」
バフィーは慌てて止まった。すぐ後ろでジェシーがヒステリーを起こしている。
「なんだよ、もう勘弁してくれよ!」
「他に出口は?」
バフィーが急き込んだ。
「分かんない……こっちかも!」
ジェシーはバンパイアの真逆の方向に向かって走り出した。だが、いくらも行かないうちに、別のバンパイアと鉢合わせしてしまい、またしても立ち往生を食らった。
「ちょっと待って。来る時この通路を来た気がする……多分ね」
バフィーとザンダーはその言葉を信じて、ジェシーに続いて走った。
ところが、三人の行く先に待ち構えていたのは、小さな物置部屋だった。道はここまで一直線で、ドアは一つ、地下だから窓もない。完全に行き止まりだ。
「こ、これじゃあ出られないわ」
バフィーはうめいた。
「でも後戻りもできないぜ。なぁどうする?」
ザンダーに答えたのは、意外なことに、ジェシーだった。
「いい考えがある」
さっきまでのパニックが嘘のように、落ち着き払った声をしていた。不吉な予感に背筋を凍らせ、恐る恐る振り返ったザンダーが見たのは、希望を粉々に打ち砕いてしまうほど残酷な現実だった。
「——死ぬのさ」
ジェシーの顔はろうのように青白く、深いしわに覆われ、そして、鋭い牙をギラつかせていた。