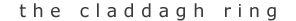「神田!!起きてるか!?」
突然、やかましいノックの音が部屋の中の静寂を破った。共に響いてくる男の声――科学班班長のリーバー・ウェンハムだ。
まだ朝の五時を回ったばかり。いつもならばまだ寝ているはずの神田が珍しく早くに目を覚ましており、 しかも『エクソシスト』の証である団服にキッチリと着替えていたので、リーバーは驚いた表情を見せた。
「神田、コムイ室長が呼んでる――すぐに司令室に向かってくれ」
「コムイが?・・・任務か?」
「ああ、急ぎらしい」
こんなに早くに呼び出すとは、余程急いでいるようだ。 神田はすぐに部屋を出て、言われたとおりに司令室へ向かった。
帰らずの森
神田ユウ・・・任務遂行のためなら仲間をも見捨てるという冷血人間―――。
教団内で自分がそう呼ばれていることは知っていた。たった今すれ違ったファインダーも、 科学班の人間でさえも、神田の姿を見るなり顔色が変わる。ただでさえエクソシストは畏怖の目で見られているというのに、 神田に対する態度がさらに白々しいのは明らかだった。
神田が司令室に着くと、まず目に入ったのは膨大な量の資料だった。 床一面にだらしなく散らばり、しかも片付けようと試みるものはいない。うっかりすれば、きっとドジな人間が滑って尻餅をつくだろう。 ―――そう思っていた矢先、部屋の奥でドスッと音がして、次いで女の短い悲鳴が上がった。
「きゃっ!」
一瞬、同じエクソシストのリナリー・リーだと思ったが、それにしては弱々しい声だと思った。しかし、他に女なんていただろうか? 神田が視線を動かすと、見慣れない小柄な女が尻餅をついて呻いている姿が目に付いた。
「あはは、ちゃんってば転ばないようにって言ったのに」
「か、片付けてくださいよ室長・・・何なんですかこの部屋!」
愉快そうに笑い声を上げたのは、コムイ・リー室長――それに口を尖らせて反論したのは、 赤茶色のクセのある髪の毛が印象的な、可愛らしい少女だった。黒い団服、背中には神田と同じように、刃物を収めた鞘がかかっている。
華奢な体に似合わず、エクソシストだろうか。
「ああ、神田君やっと来たね。朝早くゴメン」
「誰だ?」
神田は、コムイの挨拶に答えずに女を指差してたずねた。女はビクッと大袈裟に肩を跳ねさせ、怯えた目つきでこちらを見る。
「あれ、神田君はまだだったね・・・三週間前入団した、・ちゃん――君の仲間だ」
神田の眉が、訝しげにピクリと動いた。今、『』と言っただろうか。といえば、数年前まで『教団』にいた、マリア・を思い浮かべてしまう。 直接会ったことはないが、教団では少々有名だった。
選ばれたイノセンスがハズレで、『咎落ち』になったとか。
「あの『恍輝』の適合者さ――ちゃん、こっちは神田。言ったとおり、君の仲間だ」
「よ。えっと、その・・・よろしく―――」
「―――『恍輝』の・・・?」
タイミングが悪かった。
が差し出してきた手に反応が遅れて、うっかり無視してしまった。 とはいえ、無視しなかったとしても振り払うつもりではあったが、今回はそうは行かなかった。
「・・・・・・・・・・・・握手、」
突然、手が自分の意思とは別に動き出した。
とかいう女が、『握手』と言った。たったその一言だけで、神田の手は操り人形のように動き出し、 のほうへ差し出された。なんだか右腕全体にヒヤヒヤした奇妙な感覚が走り、気味が悪い。
はそれを握ると、満足げな表情をした。
「・・・・今度の任務はどこだ」
神田は、の手を振り払って、自分の手をさすった。気味が悪い女――それが、神田のに対する第一印象だった。
「ドイツだよ。ドイツ北部にある、森林地帯のダンケルンという村だ」
「最近、そこへ行った人間が帰ってこなくなったらしいの。『帰らずの森』なんて噂も立っているわ」
妙におどおどした口調で、コムイの言葉をが継ぎ、壁にかけられた地図を見るよう促した。
「イノセンスによる奇怪現象の可能性があるので、ファインダーを三人、調査に向かわせた――二日前のことだ」
任務内容の説明が、またコムイに戻った。
「ダンケルン村は森の奥にあるんだが、ファインダーはその手前にある ミッテルバルトという町から、目的地に向かうという連絡が入ったのを最後に消息不明だ・・・これが細部の地図になる」
コムイが高く積み上げられた本の山のてっぺんに、黄ばんだ地図を載せた。 神田は黙ってそれを覗き込んだのだが、なぜかまで地図を見つめているのが気になって仕方がなかった。
「ドイツに着いたらまずミッテルバルトに向かってくれ。森には一本道があり、谷に着くと古い石の橋がかかっている。 その橋を越えれば、ダンケルン村だ」
「この森がちょっと気になるわね――昔から森には不気味な伝説が『つきもの』だし・・・」
「うん、まあそれはさておき、森を通る時は気をつけて。何が出るか分からないから」
神田は頷いた――そして、おかしなことにまで深く頷いた。背中の剣型のイノセンスが、キラキラと光っている。
剣は意外なことに黄金だった。持ち手と鍔の交わる十字に、真っ黒い玉が埋め込まれている。 恐らく、それがこのイノセンスの本体だろう。――そういえば、『恍輝』は自体の温度がとても高く、 なかなか武器に改造できないと聞いたことがある。
「では、二人とも―――。 今すぐドイツへ向かい、ファインダーの救出に当たってもらいたい」
「わかっ・・・・・・あ?」
「了解しました、コムイ室長」
コムイに対する、二人の応答は対照的なものだった。神田は思い切り顔をしかめ、一方は相変わらずおどおどと怯えた表情に、無理矢理な笑顔を貼り付けて頷いた。
――今、コムイは何と言っただろうか。『二人とも』、だと・・・!?この怖がりの頼りなさそうなニンジン女と組めという事か?
「森って、神聖な場所であると同時に恐ろしい魔物が棲んでいるのよね――なんか出てきたら助けてね、神田くん」
何が、『助けて』か。
「・・・・・・・・・俺一人で行くのはダメか?」
「その提案は審議前に却下だね。子守はよろしく頼んだよ」
コムイは、雲のように軽い笑顔を浮かべて言った。