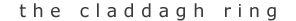「すいません――ダンケルン村への行き方ってわかりますか?」
意外にも、頭の回転は早いようだ。 神田が思いつくよりも先に、は通りかかった老婆に道を尋ねかけた。
「あんたら、あの村へ行くのかい?」
「たぶん、そのつもりです」
「あそこは昔から嫌な噂のある村なんだよ――」
「イヤな噂?」
神田は二人の会話に割って入り、老婆の言葉を鸚鵡返しに聞き返した。
「ああ。 『魔女』が棲んでいて、道に迷った子供を捕まえ、喰っちまうのさ」
「まあ失礼ね!魔女は人間だもの、子供なんて食べないわよ!」
老婆は明らかにを脅かす口調で言った。はまるで自分をけなされたかのように言い返しながらも、 震え上がって神田の袖にしがみついてきた。こちらからすれば、鬱陶しくてたまらない。
「胆だめしかなんだか知らんが、ダンケルン村に興味本位で近づくのはやめな」
「そんなんじゃないわ!それに、わたし子供じゃないもの!」
「ダンケルン村に行くには一本道があると聞いてるんだが」
は今頃やっと子ども扱いされたことに気付いたようで、噛み付くように反論した。 一方の神田も、を腕にぶら下げたまま帰るそぶりを全く見せない。
数秒間の沈黙ののち、老婆が折れて、特大の溜め息を吐いた。
「しょうがないねぇ・・・あそこに『ダンケルン村』って立て札があるだろう?あの道を真っ直ぐ行って森を抜ければ、村に着くよ」
「わかった。手間を取らせたな」
老婆の指差した方向を見つめながら、神田は静かに言った。 がボケッとしている間にも、神田は先を歩き出す。
「でも、あんたら・・・本当に行くのかい?」
老婆がまた、神田の背中に向かって声を投げかけたので、神田はふと立ち止まって老婆の方へ顔を向けた。
「ああ。そのつもりだ」
「あの村は、人が帰ってこないって言われてるんだよ。つい二日前にも三人組の男が森に入っていったが、 戻ってきていない」
「わたしたち、その人たちを探しにきたのよ・・・多分、だけど――」
が突然声を上げた。 老婆の顔には諦めの色が浮かび、溜め息と共に「戻ってこられるといいね」という呟きが聞こえたような気がした。 しかし、その頃には神田はまた歩き出していたので、それが本当かどうかは分からなかった。
森へ
まさか本当に、ここまでどんくさいとは思わなかった。どんな雰囲気をかもし出しているにしろ、エクソシストであるからには 並の人間よりは運動神経がいいと思っていた。しかし、は先程から何十回も木の根に躓いて転んでいる。
「神田くん・・・待っ・・・・てっ・・・、きゃあっ!」
ドサ、という、もう聞きなれた音に、 神田は何度目か知れない溜め息をついた。
「お前、今来た道引き返して、ミッテルバルトで待機してろ」
「えっ、どうして?」
「どうしてもなにもない。お前がいるとこっちの進みが遅くなんだよ――俺一人で行った方が速いだろ」
神田の言葉に、は思い切り顔をしかめた。『足手まとい』と言われたことに、相当腹が立っているんだろう。 だが、本当のことだ。コムイも、何だってこんな女をペアに組ませたんだ?
「だって、暗いんだもの。足元がぼやけててよく見えないのよ」
「どんな言い訳があるにしろ、俺にとっては足手まといだ」
「あなた、どうしてそんな冷たいことしか言えないの!?まさかわたしが殺られそうになっても、見捨てるとか言わないわよね!?」
―――何を喚いているんだこいつは。
神田はイライラして、を睨みつけた。 鋭い視線に怯えて、ヒッと息を呑んで肩をビクつかせている。頼りになるようには見えない。どうせ、すぐ死ぬようなタイプの女だろう。
「残念だが、任務遂行のためなら俺はお前を見捨てるぜ。それがイヤなら森の外で待っていればいい」
「何て・・・!?だけどっ、その・・・・・・・いいえ!付いてくわ」
は怯えたように視線を泳がし、やがて首を振って強く言った。一瞬、神田にはが今来た道を引き返そうかと迷ったように見えた。なら、首を振らずに引き返せばよかったものを。
弱虫のクセに何をそんなに出しゃばるのか、俺には全く理解できない。
「お言葉ですけど! わたし、こう見えてもジャニス・クレイマー元帥の弟子なんですからね!そう簡単に死にやしません!」
置いていこうとついに動き出した神田の足が、突如ピタリと止まった。
今、こいつは何と言った・・・?―――あのクレイマー元帥の弟子だと・・・・!?
神田が振り向いた時、ちょうど二人の間を湿った風が通り過ぎていった。 の赤毛がサラサラと横になびき、神田の黒髪も同じように揺れる。深緑のの目が、真っ直ぐとこちらを見つめていた。
「もういい。勝手にしろ」
「・・・あら、それじゃあいいの?付いていっても―――」
「そうしたいならそうすればいい。ただし、後から帰りたいなんて泣き言言い出しても、俺は聞かねェからな」
「・・・ちょっと自信ないわ」
はまた弱々しく微笑み、か細い声で言った。 今まで、こいつの顔をまともに見たことはなかった。しかし、突如見せられた微笑みに、何故だか心臓が跳ね上がったような気がした。
***
二人は引き続き、森の中を歩き出した。奥へ進めば進むほど、陽の光は木々に遮られ、 薄暗くなっていく。ファインダーどころか、人の気配は全くしなかった。やはり、何かに巻き込まれてしまったのだろうか。 それとも、村についてから襲われたのだろうか?
がまたしても木の根につまづき、神田のほうへ倒れこんできた。
「きゃっ・・・・・!!」
短い悲鳴の後、神田の左腕辺りにトスッ、と軽い衝撃がくわえられた。 左肩から少し前へ倒れかけたが、そこまで強い力ではなかったので、バランスは簡単に取り直せた。 ただ、左腕に何か温かい小さいものがしがみついている。
「あっ、ごめんなさい・・・、」
は慌てて、神田からパッと手を放したが、その拍子に今度は後ろに転びそうになってしまった。 神田は片手を伸ばしての手を引っつかむと、その小さな手を握ったままズカズカとまた歩き始めた。
「え、えっと・・・・・・・??」
「あまり後ろで何度も躓かれても気になるからな。こうしてればもう転ばねェだろ」
「そ、それはわたしがうざったいとか、そういう意味?」
神田はあえて無言だったが、内心はそれ以外に何がある、 と言いたくてたまらなかった。
「あれ、ねぇ神田くん――」 突然が声を上げた。
「何だ」
「何か、足音がしない?向こうから、ヒタヒタって・・・・・」
神田は歩みを止めて、耳を澄ましてみた。 そういえば、の言うとおり、確かに人の足音が聞こえる。ヒタヒタと僅かな小さい音だが、 そいつは明らかにこちらへ近づいてきている。
―――ヒュッ!
空気を切る音と、鋭い殺気を感じた。
神田は咄嗟にを片手で抱きかかえ、襲ってきた何かをサッと避けた。 すると、視界に斧を握り締めた、きこり風の若い男がチラリと映った。神田はを乱暴に突き放すと、 背中の鞘から六幻を引き抜いて、男の腹を峰打ちしてやった。
「ぐうっ・・・!!」
男が呻きながら、地面に倒れこんだ。同時に枯れ葉が数枚舞い上がり、神田の視界を少しばかり遮った。 それでも、男の顔にビキビキと音を立てて太い血管が浮かび上がったのは、しっかりと見えた。
「・・・っ、アクマだわ!」
突き飛ばされて倒れこんでいたが、金切り声を上げた。 直後、男の皮を脱ぎ捨て、巨大な鉄の塊が空中へ飛び出した。その体からはいくつもの円筒形のキャノンが四方八方に突き出している。
「銃器攻撃のアクマか・・・まだ進化していない、初期段階だな」
神田は背中から六幻を勢いよく引き抜き、黒い刃を二本の指で撫で上げた。 すると、電気を帯びたかのように、刃はビリッと音を立てて発光する。
―――イノセンス発動!
神田は一気に地を蹴って飛び出し、アクマに向かって刃を振り下ろした。 弾丸をも跳ね返す硬質な本体も、イノセンスによって容易に切り裂かれる。切り裂かれたアクマは火を吹いて爆破し、跡形なく消え去った。
「フン・・・」
神田は、たった今までアクマがいた場所を見下ろしながら、六幻を鞘に収めた。 は尻餅をついたような格好のままで、ぽかんと神田を見上げている。
「すごい・・・強いのね、神田くん」
「あれくらい余裕で壊せなきゃ困る」
「でも、速かったわ」
―――何だか質素な会話だな。
その原因は主に自分にあるだろうと分かっていたが、神田はそう思った。