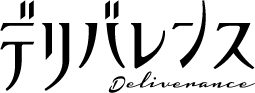
その日突然、玲乃はそれに気が付いた。『幽霊屋敷』を出て、寂れた住宅街を少し進んだところに、妙な男がいた。
まるで人目を避けるように、電柱の陰にひっそりと突っ立っている。住宅のブロック塀に体を向けるかたちでピッタリ張りつき、今に体の前半分がめり込むのではないかと思われた。質素なスーツを着ているので、きっとマグルのサラリーマンだ。最初はそう思ったが、さらに歩き進めて男の風体がよく見えるようになってくると、玲乃にはそう断言できる自信がなくなった。男は、赤黒い染みのついた大きな麻袋を、すっぽりと頭に被っていた。
男の周辺は異様な空気が充満していた。それは目にも見えず、臭いもしない感覚的なものだったが、玲乃はそれに激しく不快感を抱いた。
──あそこ、通りたくないな⋯。
しかし、この道を通らなければ学校には行けない。この道以外に選択肢などないのだ。玲乃は清浄な場所に立ち止まったまま、男の様子を窺った。依然と頭に袋を被ったまま、何もないコンクリートの塀に向かって、不気味な沈黙を吐き出している。玲乃はのるかそるかの博打に出るべきか悩んだ。あの様子なら、後ろをそっと通りかかったって気づかないかもしれない──いや、だけど、突然振り返るかも──もしかしたら、「ワッ」と襲いかかってきたりして⋯⋯。
いやいや、怖気づいちゃいけない──玲乃は強く自身に言い聞かせた。私は魔女。偉大なる魔法使いダンブルドアが校長を務める『ホグワーツ』の、グリフィンドール寮の生徒。『勇猛果敢』で通っているグリフィンドール生なんだから⋯⋯。
とうとう意を決して、玲乃は一歩を踏み出した。まっすぐ、脇目を振らないようにまっすぐと、前だけを見て歩いた。『何か』に自分の存在を意識されないように、平静を装った。電柱まであと少し⋯⋯人影が動く様子はない⋯⋯大丈夫、大丈夫⋯⋯。
電柱の側を通り過ぎる瞬間、体の右側に嫌な気配がした。何かがまとわりつくような感じだった。逃れようのない気持ちの悪さが背筋を舐め上げ、ぞくっと鳥肌が立った。一刻も早くここから離れたい。だけど、脚が思うように進んでくれない。なんだか体が重いような気がする。視界に映っているものを上手く認識できない。甲高い耳鳴りがして、頭が痛くなりそうだ⋯⋯。
、
あ 、
──雖後□雖後□縺�縺九i雖後□縺」縺ヲ險縺」縺溘s縺�遒後↑縺薙→縺ェ縺��繝ゥ縺薙s縺ェ縺ョ辟。諢丞袖縺�繧�▲縺ヲ縺ッ縺�¢縺ェ縺九▲縺溷�驛ィ蜈ィ驛ィ髢馴&縺」縺ヲ縺溘s縺�驕弱■繧堤官縺励◆蜿悶j霑斐@縺ョ縺、縺九↑縺�%縺ィ繧偵@縺溘♀縺励∪縺�□繧ゅ≧縺翫@縺セ縺�□菴輔b縺九b謇矩≦繧後↓縺ェ縺」縺溘%縺ョ縺セ縺セ關ス縺。縺ヲ縺�¥繧薙□蠎輔↑縺励↓關ス縺。繧倶ク譁ケ縺�隱ー繧ょ勧縺代i繧後↑縺�勧縺代&縺帙↑縺�ク邱偵↓關ス縺。繧九s縺�蝨ー縺ョ譫懊※縺ョ繧ゅ▲縺ィ蜈医∪縺ァ驕馴」繧後↓縺励※繧�k
縺�・
、
────────────────⋯⋯
「──?──さん?──宝生さん?」
玲乃はハッとした。ルキアが怪訝そうに玲乃の顔を覗き込んでいた。
いつの間にか、玲乃は空座一高の校門前に突っ立っていた。耳鳴りの音しか聞こえていなかった意識の中に、賑やかな喧騒が戻ってきた。思わず辺りをきょろきょろ見回したが、どこにも麻袋はない。
「どうしたのだ?先程から何度も声をかけていたというのに。目が据わっていたぞ」
「え──あ、ごめん。ぼーっとしてた」
「いや⋯、何事もなければ良い」
そうは言いながら、ルキアの目が一瞬、玲乃の右肩あたりを捉えたような気がした。
「おールキア。そこで何して──」
二人がパッと顔を上げると、ちょうど黒崎が登校してきたところだった。鮮やかなオレンジの髪が、朝日を受けてキラキラしている。黒崎はルキアの陰に隠れていた玲乃に気づくと、ちょっとだけ驚いたような顔をした。
「珍しい組み合わせだな⋯⋯」
「そうか?」
ルキアがあっけらかんと言った。
「お・おはよう、黒崎くん」
玲乃はちょっぴりどぎまぎして、挨拶を紡ぐ声がひっくり返りやしないかとヒヤヒヤした。黒崎は玲乃の緊張など何のその、当然のように「おう」と答えた。
「立ち話もいいけど、HR遅れんなよ」
「何を偉そうに」
「く・朽木さん⋯⋯」
過ぎ去る黒崎に向かって平然と憎まれ口を叩くルキアに玲乃は縮み上がり、どうか本人に聞こえていませんようにと祈った。
「ところで宝生、」
ルキアが声を落として呼びかけてきた。
「お前⋯⋯どこかおかしなところはないか?」
「え?」
「その、⋯体調とか⋯⋯」
玲乃は首を傾げた。
「何ともないよ。どうして?」
「い・いや!元気なら良いのだ!──じゃ!」
ルキアは取り繕ったような笑顔でブンブン手を振ると、玲乃をその場に置いてけぼりにして行ってしまった。その背中が、先に昇降口へ向かった黒崎と合流し、何やら深刻そうにヒソヒソやり出したのを、玲乃はきょとんとしたまま見送った。
「宝生さん⋯⋯大丈夫?」
席に着くなり、石田が開口一番そう言った。玲乃はつい眉を寄せた。「また?」
「『また』とは?」
「あ・ごめん⋯⋯さっき朽木さんにも同じこと言われたから」
玲乃はそんなに顔色が悪く見えるのかと不安になって、頰をさすった。石田はよほどルキアのことが気に入らないのか、名前を聞いただけで鼻にしわを寄せていた。
「⋯⋯何か困ったことがあったらすぐに言うんだ」
メガネを押し上げながら、石田はぶっきらぼうに言った。
「携帯に連絡をくれても⋯⋯そういえば、君の連絡先知らないな」
それを聞いて、玲乃もはたと気づいた。
「ほんとだ。私も石田くん
「緊急時に文通する気か君は!?──携帯電話の番号だ!」
「あっ、そっか。ごめんね、電話持ってない⋯⋯」
すると、石田は意外そうに「へえ」と呟いた。
「まあ、そういう教育方針の親御さんもいるしね。けど、弱ったな。それじゃあ何かあった時、どうやって人に連絡するんだ?」
「えっと⋯⋯何かって、どんな?」
「いや、ホラ──僕の数学の問題集を間違えて持って帰ったのに気づいた時とか」
「え──あ!」
玲乃は自分の机に積み上げていた教科書の山の中に、『石田雨竜』の名前を見つけて慌てた。
「ご・ごめん⋯⋯」
「いいよ。気づいてたから」
石田は玲乃から問題集を受け取ると、ズレてもないのに、またメガネをくっと押し上げた。
「何かあったら、赤い花火上げるよ」玲乃は投げやりに言った。
「何だいそれ」
「うん⋯⋯だから、空を見ててね」
石田は訳が分からないという顔をしていたが、しばらくして冗談だと理解したのか、「はいはい」と面倒臭そうに返事をした。
軽い調子ではぐらかしたはいいが、帰り道、またあの場所に差し掛かると、玲乃は誰にも相談しなかったことを激しく悔やんだ。
「⋯⋯うわ⋯」
人影はまだいた。相変わらず頭に麻袋を被ったまま、コンクリート塀に向かって佇んでいる。一日中あんな格好で突っ立っていて、誰にも通報されなかったのが玲乃にはとても信じがたかった。そういえば──玲乃はふと小さな違和感に気づいた──場所を移動している。今朝は電柱の陰に隠れていたのに、次の電柱との間の、ちょうど真ん中くらいにいる。『幽霊屋敷』に少し近づく形だ。
玲乃は悪寒がした。『家バレ』という言葉が脳裏に浮かぶ。やっぱり、どうしてもこの道を通りたくないと思った。しかし、ずっとこのまま対峙しているわけにはいかない。
一歩ずつ、あまり足音を立てないようにして進んだ。どうか私の存在に気づきませんようにと強く念じながら、きつく目を瞑っていた。今朝だって何事もなかったから、大丈夫だ──そう言い聞かせつつも、男の横を抜ける瞬間に駆け上がる不気味な感覚には、きっと慣れそうもなかった。
文字化けはわざとです!