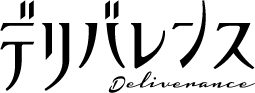
「あれ、朽木さん。また来てるの」
いつもの帰り道、『浦原商店』の前でシャッターを蹴飛ばしているルキアを見つけた玲乃は、声をかけてしまった後から、声をかけないであげるべきだったと悔やんだ。ルキアは玲乃と目が合うと、途端にサーッと青ざめて、十発目を喰らわせようと振り上げていた脚のやり場に困り出した。
「ごめんなさい…」玲乃は思わず謝った。「私のことは気にせずに、ガツンとどうぞ」
「お・おう、そうだな……」
言われるがままに、ルキアは小さな革靴を履いた足をシャッターに叩き込んだ。ついでに言うと、玲乃はルキアが猫を被り忘れていることに気づいていたが、これ以上はかわいそうな気がして、敢えて追及を自粛しておいた。
「今日は皆さん揃って朝からお出かけみたい」
玲乃は今朝、この道で大荷物を持った浦原たちと挨拶を交わしたのを思い出して言った。
「何かご用だったの?」
「まあ、急を要するほどでもない。苦情を入れにきただけだ」
「ふ〜ん……」
駄菓子に入れる苦情とは何だろうと率直な疑問がよぎったが、これも追及しない方がいいことのような気がした。
「まったく……夜逃げでもしたんではないだろうな」
ルキアはため息まじりに店の外壁に背を預けてしゃがんだ。どうやら浦原の帰宅をここで待つつもりらしかった。そんなに重大な欠陥が駄菓子にあったんだろうかと訝りながらも、ここに彼女一人置き去りにするのには気が引けて、玲乃はルキアの隣に並んで座った。
「……?」
不思議そうな視線を横目に感じながら、玲乃はポケットから引っ張り出したヨーグレットをルキアに差し出した。空座町に越してきてから、玲乃のおやつはもっぱら『浦原商店』の駄菓子だった。
「これ、食べる?」
戸惑ったような、躊躇ったような、一瞬の静寂が二人の間にあった。やがてルキアはものすごく小さな声で、「……いる」とだけ答えた。
ルキアの白くて小さな手のひらに、銀のプラスチックシートをまるまる一枚乗せてやり、彼女がタブレットを一つ押し出して口に運んだのを見計らって、自分の分も口に放り込んだ。安っぽい甘さと仄かな酸味を味わいながら、奇妙な沈黙にボリボリ音が響くのを聞いていた。
「マグルのお菓子ってつまんないのが多いけど、ここのお菓子はちょっと好き」
自己紹介になるかなと思って呟いた一言に失言があって、頷きかけていたルキアがちょっと引っかかった。
「——マグルって?」
「……よく分かんない」
「何だそりゃ」
玲乃が雑にごまかすと、ルキアは小さく笑って、二つ目のヨーグレットを口に投げ入れた。
「しがない駄菓子だぞ」
真新しいヨーグレットを舌の圧だけで溶かすチャレンジをしていた玲乃は、それについて深刻そうに頷いてから、ちょっと引っかかって聞き返した。「——しがないって?」
「よく分からん」
「なあにそれ」
それからしばらく沈黙があって、玲乃はヨーグレットをボリボリ言わせながら、ルキアについてぼんやり考える時間があった。
学校では、黒崎や浅野、小島といった騒がしいグループと比較的一緒にいることが多い。反面、少し離れたところから一人ぼっちでみんなを眺めていることもある。そういえば、女子と仲良くしている印象はあまりない。編入からちょっと経って、大分勝手が分かってきた様子ではあるが、まだうまく溶け込めていないみたいだった。
とはいえ、玲乃はあまり人のことを言えないとも思った。自分もたまたま知り合った石田と時折話をするくらいで、肝心な同性の友達は一人もできていない。玲乃にとってそれは、とても難しいことだったのだ。マグルのクラスメイトたちとは、生き方も文化もまるで違った。好きなお菓子の味を共有することもないし、悪戯グッズをけしかけて笑いを取ることも、クィディッチのチームについて語り合うこともない。自分の思い出すら人に話して聞かせられないのだ。薄い膜で隔てられた違う世界の人々を見ているようで、その中に自分が馴染んでいるところなんて想像できない。
こんな風に考えたらおこがましいが——案外、ルキアは玲乃と似たところがある気がした。同級生に対して玲乃が抱いている疎外感を、彼女は知っているのかもしれない。実はルキアもどこか別の世界から来た魔女で、訳あってマグルの世界に潜んでいるんだったりして……。
おかしな考えは、ルキアの思い出したような「あ」という声によって遮られた。
「……?どうしたの?」
「いや……、その…忘れていた」
ルキアはいつの間にか最後の一錠となったヨーグレットをかじりながら、低い声で続けた。
「猫をかぶるのを」
これまでそれに気づいていなかったのは、きっと世界中でルキアたった一人だったはずだと玲乃は思った。
「あらァ、青春ですね。羨ましいなあ」
おやじ臭い声に顔を上げると、ルキアの待ち人が、いつものあの笑みを湛えて立っていた。いつの間に…?——身構える玲乃をよそに、浦原はカランコロンと下駄を鳴らしながら二人の前を通り過ぎ、連れがシャッターを開けるのを正面で待った。
「何が青春だ。お前に文句を言うために待っておったのだぞ」
「おやまあ、そうだったんスか?いやァ、制服の乙女が二人並んで駄菓子屋の前で駄菓子かじりながら夕日を眺めてるモンですから、つい。なんか今にもスポドリのロゴが見えてきそうじゃありません?」
——お、乙女……。
照れ臭くなって咳払いをする玲乃に、ルキアがなぜか呆れ果てた目を向けた。
「——で」浦原がバサッと扇子を広げた。「ウチの商品に何か不具合でも?」
「不具合なんてモンじゃ——」
息巻いて浦原へ詰め寄りかけたルキアが、ハッとして言葉を切った。どうしたものかという視線が、しゃがんだままの玲乃に降り注ぐ。玲乃には彼女のこの目に覚えがあった。玲乃に聞かれたらまずい話がしたくて、その上、そうと勘づかれるのもまずいという時の目だ。
「あー」玲乃はわざとらしく膝を打って立ち上がった。
「ペットに餌をやらなくちゃいけないんだった」
「ペット?」
見え透いた嘘の口実に、浦原が反応した。
「意外だなあ。何飼ってるんスか?」
パタパタと閃く扇子を見つめながら、玲乃は咳とごちゃまぜにして「ふくろうとパフスケイン」と答えた。
「そ・それじゃ、お先に失礼します」
「ハイハイ気をつけてねー。すぐそこっスけど」
浦原の大きな手がヒラヒラと揺れる。玲乃はそれに手を振り返してから、ルキアに微笑みかけた。
「はい。朽木さんも、またね」
「う・うむ…」
踵を返して『幽霊屋敷』へ向かう玲乃の背中に、「宝生!」と呼び止める声がかかった。振り返ると、ルキアが目元を赤く染めながら唇を尖らせていて、振り絞るように言った。
「馳走になったな……その、『まぐる』の駄菓子」
舌足らずなイントネーションに、玲乃は思わず笑みをこぼした。
「お粗末様でした」
「『マグル』?何スかそれ」
「野暮な奴め。乙女の青春に口を挟むな」
あながち間違ってもない