時代にただ一人 選ばれし少女
闇の世界と戦う力を備えた少女
それが
バンパイア・スレイヤー

鋭い牙の先が皮膚に触れた。バフィーは叫び、もがいた。自分に覆いかぶさる巨体を押しのけようと、無我夢中で身をよじった。ルークはバフィーの首筋を噛み切ろうといっそう身を乗り出し——鋭い悲鳴を上げて、弾かれたように飛びのいた。バフィーは驚いて見上げた。ルークの真っ赤に手は焼けただれ、ジュージューと煙を上げている。バフィーはそこで自分の胸元に光っている銀色のペンダントのことを思い出した——バンパイアは十字架に触れられない。
バフィーは両足を振り上げ、ルークの土手っ腹を思い切り蹴り上げた。ルークは痛烈な悲鳴を上げ、棺桶の外に吹っ飛ばされた。バフィーは急いで棺桶から飛び出し、ルークが目を覚まさないうちに、霊廟を後にした。
全速力で墓地を疾走していると、何個か先の墓石の向こうからかん高い悲鳴が聞こえた。バフィーは大急ぎで回り込み、ウィロー・ローゼンバーグの上に覆いかぶさっているバンパイアを見つけた。
「ちょっと!」
バンパイアがパッと振り返った。バフィーはその顔を容赦なく蹴り飛ばした。バンパイアはもんどりうって芝生の上に投げ出されたが、すぐに起き上がって森の向こうへ逃げ出した。バフィーが後を追いかけようと踏み出した時、今度は後ろの方から、ロン・ウィーズリーの泣き叫ぶような声が聞こえてきた。
「ザンダー!!」
バンパイアが二匹、ザンダー・ハリスの体を引きずってどこかへずらかろうとしていた。バフィーは素早く敵の正面に躍り出て、強烈なキックを一発ずつお見舞いしてやった。バンパイアが景気よく吹っ飛ばされたのを見届けてから、ウィローとロンが大慌てでザンダーの傍に駆け寄った。バフィーはエルトンの墓の傍らにそびえ立っていた木の枝をへし折り、ちょうど立ち上がったところのバンパイアの心臓を迎え討った。
「ザンダー!ねえ、大丈夫?」
ウィローに抱え起こされたザンダーは、うつろな顔で小さくうめいた。「頭がクラクラする……」
ハリー・ポッターは数メートル離れた先で気を失って倒れていた。うつ伏せになった体のすぐ近くに、壊れた丸メガネが無造作に投げ出されている。バフィーはそれを上着のポケットにしまいこみ、ロンと一緒にハリーを抱き起こした。
「ジェシーは!?」
「分からない、突然囲まれて…」ウィローがオロオロと答えた。
「あの女が…つれてったよ…」とザンダー。
「どっちへ!?」
ザンダーは弱り切った様子で「分からない」と首を振った。
「……ジェシー…」
あたりを注意深く見回しながら、バフィーは呟いた。
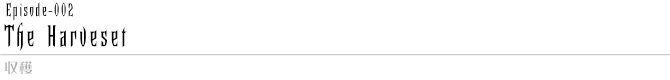
五人は命からがら何とかホグワーツ城への生還を果たしたが、寮に辿り着いた頃には消灯時間を二十分も過ぎていた。みんなボロボロのくたくたで、ハーマイオニー・グレンジャーが怖い顔をして迫ってきたのを押しのけて、まっすぐ寝室に向かった。しかし、化け物との乱闘で興奮しきっていた五人は、ベッドに潜り込んでもずいぶん長い間目が冴えてしまい、日が昇る時間になっても寝つくことができなかった。おかげで、翌朝は大幅に寝坊してしまったばかりか、揃いも揃って目の下にに隈を作り、頬はげっそりと痩せこけていた。
大広間で朝食をとったあと、五人は授業が始まるまでの間、図書室にこもりきった。といっても、勉強しにいったわけではない。司書のルパート・ジャイルズが昨日の件について話がしたいとスレイヤーを呼びつけたので、バフィーが昨日の被害者全員を連れて行ったのだ。ジャイルズは四人を見ると驚いた顔をしたが、わけを話すとすんなり入れてくれた。
「僕、図書室って来たの初めてだよ」
ジャイルズが本を取りに二階へ姿をくらますと、ハリーが極力小さな声でバフィーにささやいた。
「こんな辛気くさいところに来るのは、ハーマイオニーかウィローくらいのもんだからな」
ロンは二階に置いてあった地球儀を高速回転させながら軽口を叩いた。
「バフィー、傷が痛むの?」
濡らしたタオルで右腕を押さえつけているバフィーを見て、ハリーが心配そうに声をかけてきた。
「ちょっとひねっただけよ。ありがとう、やさしいのね。でも大丈夫だから心配しないで」
バフィーがほほ笑みかけると、ハリーは照れくさそうに鼻の頭を掻いた。その顔つきがどうも昨日と違う気がして、バフィーは「あら?」と首をひねった。よく見ると、丸メガネのブリッジがどうしようもなくねじ曲がってしまっている。
「ハリー、メガネをどうしちゃったの?」
バフィーは自分の鼻のあたりを指差してたずねた。ハリーはメガネを外し、目を少ししばしばさせた。
「わかんない。壊れちゃったみたいだ。たぶん、バンパイアに殴られた時だと思う」
「頑張れば直るだろ」
ロンは気軽に杖を取り出したが、なかなかうまくいかなかった。呪文は分かっているのに、ハリーやロンがいくら「レパロ、直れ!」を唱えても、メガネはうんともすんとも言わないのである。みんなが杖を振って悪戦苦闘していると、やがてジャイルズが二階の奥の部屋から現れた。腕に本を山のように抱えている。
「世界は思いのほか古く、創世記にあるような『楽園』では始まらなかった——」
ジャイルズは険しい顔をして杖を振り、ロンがふざけて回しっぱなしにしていた地球儀を止めた。
「遥かその昔、地上には悪魔がいた。地上に住み着き、そこを——『地獄』に変えた。だがある時、悪魔の時代は終わり、命に限りある人間がそれに取って代わった。今に残るある種の魔術や生き物は、古き悪魔の名残りだ」
「バンパイアもね」
バフィーが付け足した。ジャイルズはみんなが集まったテーブルに腰かけ、とびきり古くて分厚い本を広げた。
「だけど信じられないよ!」ザンダーが興奮気味に言った。「今バンパイアの話をしてるんだろ?俺たち、マジでバンパイアを語ってるんだぜ?」
「それって、夕べ見たあいつら?」
バフィーのすぐそばに座っていたウィローが弱々しい声を上げた。
「いいえ、あれは違うわ」バフィーが首を振った。
「あの人達は……お肌の手入れが必要なだけよ。でなきゃ狂犬病かも。ええ、きっとそうだわ!男が消えて見えたのも光のせいよ!——初めてバンパイアを見たときはそう思おうとした。もちろん、悲鳴を上げた後だったけど」
「あぁー…座らないと倒れそう…」
ウィローがうめいたのを見て、バフィーは苦笑した。
「大丈夫!もう座ってる」
「そう……よかった…」
「じゃ、あいつらは『悪魔』?」ハリーがへなへなした。「僕、魔法界って、もっと楽しい世界だと思ってた…」
「僕だってそうさ。バンパイアがいるってことくらいは知ってたけどさ、まさかこんなに近くにいるなんて…」
ロンの言葉にみんな黙りこくった。気まずい沈黙の中、バフィーが不安になってみんなの顔色をチラチラ窺っていると、ジャイルズがようやく本から顔を上げた。
「文献によると、最後の悪魔は消える前に人間を食らい……血が混ざった。それは、姿こそ人間だが、悪魔の魂に犯されていた。そして地上を歩き回り、次々と人を襲い、腹を満たした。殺し、時には血を吸い合って仲間を増やし……いつの日か人間が全滅し…悪魔が戻るのを待ってる」
ジャイルズはまっすぐにバフィーを見つめていた。バフィーは何も言わず、埃っぽい灰色の目を見つめ返した。底冷えするような沈黙に耐えかねて、ロンがぶるっと身震いした。
薄暗い、嫌な臭いのする地下通路に、三つの人影がどこからともなく現れた。欠けたレンガで補強された壁は、湿った空気で結露しており、余計に肌寒さを感じる。ジェシー・マクナリーは貧血でフラフラと今にも倒れてしまいそうだったが、ルークがそれを許さなかった。ジェシーは抵抗できない力で後ろ手を掴まれ、暗い通路を延々と歩かされた。
最後の角を曲がった時、ジェシーは思わず立ち止まってしまった。長々と続く通路は、急な階段を最後に終わった。その先は洞窟のように開けており、あちこちでろうそくや松明が赤い炎を燃え上がらせている。奥には真っ赤な血の池がぐつぐつと沸き立ち、そこら中にひどい臭いが充満している。
「歩け」
ジェシーは後ろから強く突き飛ばされ、もう少しで真っ逆さまに落ちるところだった。ふらふらしながら階段を下りていくと、池の向こうから、影のような黒い人物がするりと姿を現した。もしジェシーに声を出す元気が残されていたら、間違いなく悲鳴を上げていただろう。その人物は見るからに弱り果てていたが、後ろにいる二人のバンパイアとは比べ物にならないほど恐ろしい風貌をしていた。もっと古く、もっと残忍で、もっと凶悪だ。
「 」
」
痩せこけたジェシーを品定めするようになめ回し、マスターが弱々しく言った。
「召し上がって下さい」
「割とおいしいです。血が澄んでて」
ダーラがしゃしゃり出た。主君のために極上の獲物を用意したことを褒めてもらいたい様子だった。
「……手をつけたのか…?」
マスターの真っ赤な瞳が、ぎらりと意地悪く光った。ダーラはとたんに小さくなった。
「わたしはお前の犬か…!残り物を食わせる気か…?」
「そ、そんなつもりじゃ…」ダーラは痙攣するように首を横に振った。
「わたしは待った…!この六十年間ずっとわたしは待ち続けた…!!お前たちが往来している間も、わたしは……この礼拝堂に…足止めだ…!わたしの復活の日はそこまできている……」
マスターがゆっくりと近づいてきた。ジェシーは怯え、ダーラは今にも卒倒してしまいそうな顔をした。
「祈れ…!その日わたしの機嫌がいいように…!!」
蝋のような白く細い手がダーラの顎を掴んだ。
「マスター、お許しを!他にも獲物がいたのに、邪魔が入って——女です!」
「その女は、腕が立ち、我々の正体も知っていました。あれはひょっとしたら、例の——」
ルークが声を落として言った。それを聞いたマスターはハッと大袈裟に息を呑んだ。「……スレイヤーか…!」
「——それが誰だって?」
ハリーが声を張り上げた。壊れたメガネ越しに見えるその顔には、「まさか」「信じられない」という疑いの表情がありありと刻まれていた。ウィローとロンは言葉も出せない様子だ。
「スレイヤーだよ」ジャイルズが面倒臭そうに繰り返した。「バンパイアがいる限り存在する、選ばれし少女だ」
「そのくだりほんっと好きね!」
バフィーがニヤッとした。ジャイルズは当たり前のように無視した。
「スレイヤーはバンパイアを退治する。バフィーがそうであることは内密に。今のところ、必要な情報は以上だ」
「一つ忘れてるよ」ザンダーが口を挟んだ。「どうやって殺すの?」
「それは私の仕事よ!」
バフィーが急いで言った。ザンダーは奴らと戦う気でいるのだ。
「でもジェシーは俺の——」
「——ジェシーを救えなかったのは、あたしのせいなんだから」
ザンダーはイライラした声で「そうじゃない」とつっこんできた。それにはウィローも同意した。
「あなたが来なきゃ、私たちも捕まってたわ……」青白い顔で言った。「……悪いけど気を失っちゃだめ?」
「呼吸して!」
バフィーが慌てて肩を叩くと、ウィローは朦朧としたまま大きく息を吸い込んだ。「……呼吸…」
「そう!——ルークって男が、『マスターに捧げる』って言ってたの。ジェシーが単なる『食糧』じゃなく、その『捧げ物』だったら、まだ生きてるかもしれない。彼を探すわ」
「あー、バカな質問かもしれないけど、『魔法省』に通報しないの?」
ウィローはとにかく事件に関わらないようにするのに必死だったが、ジャイルズはそれを聞いてバカバカしいとばかりに笑い飛ばした。
「通報して何と言うんだ?」
「だから…『バンパイア』とは言わずに、た、ただ『悪いやつがいる』って……言ったらどう…?」
「『魔法省』を呼んでも解決しないの。魔法は通用しないもん」
バフィーはウィローに向かって言い聞かせるように首を振ってみせた。ウィローももちろん落胆した様子だったが、それ以上にハリーとロンがひどくがっかりして溜め息をついた。
「連中の行き先に心当たりは?」
ジャイルズがずれかけたメガネを押し上げながらバフィーに聞いた。
「追いかけようとしたけど、墓地をでたとたん消えたわ。ヒューッ!って」
「飛べるの!?」
ザンダーが目を見開いた。バフィーはさあと肩をすくめた。
「車かもね」
ザンダーは「あぁ…」と納得したように頷いたが、その顔はどこからどう見てもちょっぴり残念がっていた。
「車の音はしなかったけど……」
ハリーが不思議そうに眉をひそめると、ロンが急にニヤニヤ笑いを浮かべてからかった。
「そりゃあそうさ。君は自分より背の低い女の人にノックアウトされてたからな」
プライドをずたずたにされたハリーがひどく衝撃的な顔をすると、ロンはますますニヤニヤした。ジャイルズは二人のやり取りをまるで無視して話を続けた。
「地下に戻ったと考えるのが一番妥当な線だろうなあ…」
「バンパイアは下水道が好きなのよ。光を浴びずに町中どこへでも行けるから」バフィーが口添えした。「でも、あのあたりに出入り口はなかったわ」
「マグルの電気用の地下道なら、町中を走ってる!」
ザンダーが思いついた。みんな「なるほど」と感心したが、ジャイルズはひどく億劫そうに溜め息をついた。
「地下道の見取り図があれば連中の集合場所が分かるかもしれない。マグルの建築管理官に問い合わせてみるか」
バフィーはいよいよじれったくなってきた。
「そんなことしてる時間ないって!」
マグルに問い合わせなんかしている間にジェシーが『捧げ』られてしまったら、助けられるものも助け出せなくなる。みんなが行き詰まって顔を見合わせていると、いちばん予想だにしていなかった人物が、自信に満ち溢れて名乗りを上げた。
「みんな!——他にも方法があるかも」
黙りこくった五人を順番に見回して、ウィローが明るく提案した。
「……スレイヤーだという…証拠はあるのか…?」
マスターがゆっくり手下を振り返って聞いた。ダーラとジェシーは相変わらず困惑した表情を浮かべていたが、ルークは確信に満ちた声色ではっきりと答えた。
「わたしと戦い、なおも生き延びています」
「それだけ聞けば充分だ…」
マスターは考え込むような口ぶりで言った。人間の生き血を塗りたくったような真っ赤な瞳がギラギラとよからぬ光を放っている。
「最後にこのようなことが起きたのはいつだったか…」
「一八四三年、マドリードで——」ルークは少しきまり悪そうに言い淀んだ。「——寝込みを襲われて…」
マスターは忌々しい過去を思い出し、喉の奥から奇妙な音を発した。それは息を呑んだ音にも聞こえたし、うめき声のようにも聞こえたが、どちらにせよひどく嗄れいて、背筋のゾッとするような音だった。
「『収穫の日』の邪魔をする者は阻止せねばならん…」
「そんな真似はさせません!」ルークが声を荒げた。
「心配するな…むこうから出向いてくるさ……」マスターがのんびりと言った。「我々には『切り札』がある……本物のスレイヤーなら…小僧が生きている限り、助けにくるはずだ……」
「『食糧』としか考えていなかったが——おめでとう。お前はたった今昇格した」
ルークはジェシーの背中に腕を回し、ごつごつした短い指で、細い首をぞろぞろとなで上げた。恐ろしくて縮み上がったジェシーにずいっと顔を寄せると、ただでさえおぞましいしわくちゃの顔の上に、ニヤリと邪悪な表情を浮かべた。
「——『オトリ』にな」
バフィーは両足を振り上げ、ルークの土手っ腹を思い切り蹴り上げた。ルークは痛烈な悲鳴を上げ、棺桶の外に吹っ飛ばされた。バフィーは急いで棺桶から飛び出し、ルークが目を覚まさないうちに、霊廟を後にした。
全速力で墓地を疾走していると、何個か先の墓石の向こうからかん高い悲鳴が聞こえた。バフィーは大急ぎで回り込み、ウィロー・ローゼンバーグの上に覆いかぶさっているバンパイアを見つけた。
「ちょっと!」
バンパイアがパッと振り返った。バフィーはその顔を容赦なく蹴り飛ばした。バンパイアはもんどりうって芝生の上に投げ出されたが、すぐに起き上がって森の向こうへ逃げ出した。バフィーが後を追いかけようと踏み出した時、今度は後ろの方から、ロン・ウィーズリーの泣き叫ぶような声が聞こえてきた。
「ザンダー!!」
バンパイアが二匹、ザンダー・ハリスの体を引きずってどこかへずらかろうとしていた。バフィーは素早く敵の正面に躍り出て、強烈なキックを一発ずつお見舞いしてやった。バンパイアが景気よく吹っ飛ばされたのを見届けてから、ウィローとロンが大慌てでザンダーの傍に駆け寄った。バフィーはエルトンの墓の傍らにそびえ立っていた木の枝をへし折り、ちょうど立ち上がったところのバンパイアの心臓を迎え討った。
「ザンダー!ねえ、大丈夫?」
ウィローに抱え起こされたザンダーは、うつろな顔で小さくうめいた。「頭がクラクラする……」
ハリー・ポッターは数メートル離れた先で気を失って倒れていた。うつ伏せになった体のすぐ近くに、壊れた丸メガネが無造作に投げ出されている。バフィーはそれを上着のポケットにしまいこみ、ロンと一緒にハリーを抱き起こした。
「ジェシーは!?」
「分からない、突然囲まれて…」ウィローがオロオロと答えた。
「あの女が…つれてったよ…」とザンダー。
「どっちへ!?」
ザンダーは弱り切った様子で「分からない」と首を振った。
「……ジェシー…」
あたりを注意深く見回しながら、バフィーは呟いた。
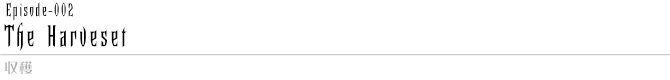
五人は命からがら何とかホグワーツ城への生還を果たしたが、寮に辿り着いた頃には消灯時間を二十分も過ぎていた。みんなボロボロのくたくたで、ハーマイオニー・グレンジャーが怖い顔をして迫ってきたのを押しのけて、まっすぐ寝室に向かった。しかし、化け物との乱闘で興奮しきっていた五人は、ベッドに潜り込んでもずいぶん長い間目が冴えてしまい、日が昇る時間になっても寝つくことができなかった。おかげで、翌朝は大幅に寝坊してしまったばかりか、揃いも揃って目の下にに隈を作り、頬はげっそりと痩せこけていた。
大広間で朝食をとったあと、五人は授業が始まるまでの間、図書室にこもりきった。といっても、勉強しにいったわけではない。司書のルパート・ジャイルズが昨日の件について話がしたいとスレイヤーを呼びつけたので、バフィーが昨日の被害者全員を連れて行ったのだ。ジャイルズは四人を見ると驚いた顔をしたが、わけを話すとすんなり入れてくれた。
「僕、図書室って来たの初めてだよ」
ジャイルズが本を取りに二階へ姿をくらますと、ハリーが極力小さな声でバフィーにささやいた。
「こんな辛気くさいところに来るのは、ハーマイオニーかウィローくらいのもんだからな」
ロンは二階に置いてあった地球儀を高速回転させながら軽口を叩いた。
「バフィー、傷が痛むの?」
濡らしたタオルで右腕を押さえつけているバフィーを見て、ハリーが心配そうに声をかけてきた。
「ちょっとひねっただけよ。ありがとう、やさしいのね。でも大丈夫だから心配しないで」
バフィーがほほ笑みかけると、ハリーは照れくさそうに鼻の頭を掻いた。その顔つきがどうも昨日と違う気がして、バフィーは「あら?」と首をひねった。よく見ると、丸メガネのブリッジがどうしようもなくねじ曲がってしまっている。
「ハリー、メガネをどうしちゃったの?」
バフィーは自分の鼻のあたりを指差してたずねた。ハリーはメガネを外し、目を少ししばしばさせた。
「わかんない。壊れちゃったみたいだ。たぶん、バンパイアに殴られた時だと思う」
「頑張れば直るだろ」
ロンは気軽に杖を取り出したが、なかなかうまくいかなかった。呪文は分かっているのに、ハリーやロンがいくら「レパロ、直れ!」を唱えても、メガネはうんともすんとも言わないのである。みんなが杖を振って悪戦苦闘していると、やがてジャイルズが二階の奥の部屋から現れた。腕に本を山のように抱えている。
「世界は思いのほか古く、創世記にあるような『楽園』では始まらなかった——」
ジャイルズは険しい顔をして杖を振り、ロンがふざけて回しっぱなしにしていた地球儀を止めた。
「遥かその昔、地上には悪魔がいた。地上に住み着き、そこを——『地獄』に変えた。だがある時、悪魔の時代は終わり、命に限りある人間がそれに取って代わった。今に残るある種の魔術や生き物は、古き悪魔の名残りだ」
「バンパイアもね」
バフィーが付け足した。ジャイルズはみんなが集まったテーブルに腰かけ、とびきり古くて分厚い本を広げた。
「だけど信じられないよ!」ザンダーが興奮気味に言った。「今バンパイアの話をしてるんだろ?俺たち、マジでバンパイアを語ってるんだぜ?」
「それって、夕べ見たあいつら?」
バフィーのすぐそばに座っていたウィローが弱々しい声を上げた。
「いいえ、あれは違うわ」バフィーが首を振った。
「あの人達は……お肌の手入れが必要なだけよ。でなきゃ狂犬病かも。ええ、きっとそうだわ!男が消えて見えたのも光のせいよ!——初めてバンパイアを見たときはそう思おうとした。もちろん、悲鳴を上げた後だったけど」
「あぁー…座らないと倒れそう…」
ウィローがうめいたのを見て、バフィーは苦笑した。
「大丈夫!もう座ってる」
「そう……よかった…」
「じゃ、あいつらは『悪魔』?」ハリーがへなへなした。「僕、魔法界って、もっと楽しい世界だと思ってた…」
「僕だってそうさ。バンパイアがいるってことくらいは知ってたけどさ、まさかこんなに近くにいるなんて…」
ロンの言葉にみんな黙りこくった。気まずい沈黙の中、バフィーが不安になってみんなの顔色をチラチラ窺っていると、ジャイルズがようやく本から顔を上げた。
「文献によると、最後の悪魔は消える前に人間を食らい……血が混ざった。それは、姿こそ人間だが、悪魔の魂に犯されていた。そして地上を歩き回り、次々と人を襲い、腹を満たした。殺し、時には血を吸い合って仲間を増やし……いつの日か人間が全滅し…悪魔が戻るのを待ってる」
ジャイルズはまっすぐにバフィーを見つめていた。バフィーは何も言わず、埃っぽい灰色の目を見つめ返した。底冷えするような沈黙に耐えかねて、ロンがぶるっと身震いした。
†††
薄暗い、嫌な臭いのする地下通路に、三つの人影がどこからともなく現れた。欠けたレンガで補強された壁は、湿った空気で結露しており、余計に肌寒さを感じる。ジェシー・マクナリーは貧血でフラフラと今にも倒れてしまいそうだったが、ルークがそれを許さなかった。ジェシーは抵抗できない力で後ろ手を掴まれ、暗い通路を延々と歩かされた。
最後の角を曲がった時、ジェシーは思わず立ち止まってしまった。長々と続く通路は、急な階段を最後に終わった。その先は洞窟のように開けており、あちこちでろうそくや松明が赤い炎を燃え上がらせている。奥には真っ赤な血の池がぐつぐつと沸き立ち、そこら中にひどい臭いが充満している。
「歩け」
ジェシーは後ろから強く突き飛ばされ、もう少しで真っ逆さまに落ちるところだった。ふらふらしながら階段を下りていくと、池の向こうから、影のような黒い人物がするりと姿を現した。もしジェシーに声を出す元気が残されていたら、間違いなく悲鳴を上げていただろう。その人物は見るからに弱り果てていたが、後ろにいる二人のバンパイアとは比べ物にならないほど恐ろしい風貌をしていた。もっと古く、もっと残忍で、もっと凶悪だ。
「
 」
」痩せこけたジェシーを品定めするようになめ回し、マスターが弱々しく言った。
「召し上がって下さい」
「割とおいしいです。血が澄んでて」
ダーラがしゃしゃり出た。主君のために極上の獲物を用意したことを褒めてもらいたい様子だった。
「……手をつけたのか…?」
マスターの真っ赤な瞳が、ぎらりと意地悪く光った。ダーラはとたんに小さくなった。
「わたしはお前の犬か…!残り物を食わせる気か…?」
「そ、そんなつもりじゃ…」ダーラは痙攣するように首を横に振った。
「わたしは待った…!この六十年間ずっとわたしは待ち続けた…!!お前たちが往来している間も、わたしは……この礼拝堂に…足止めだ…!わたしの復活の日はそこまできている……」
マスターがゆっくりと近づいてきた。ジェシーは怯え、ダーラは今にも卒倒してしまいそうな顔をした。
「祈れ…!その日わたしの機嫌がいいように…!!」
蝋のような白く細い手がダーラの顎を掴んだ。
「マスター、お許しを!他にも獲物がいたのに、邪魔が入って——女です!」
「その女は、腕が立ち、我々の正体も知っていました。あれはひょっとしたら、例の——」
ルークが声を落として言った。それを聞いたマスターはハッと大袈裟に息を呑んだ。「……スレイヤーか…!」
†††
「——それが誰だって?」
ハリーが声を張り上げた。壊れたメガネ越しに見えるその顔には、「まさか」「信じられない」という疑いの表情がありありと刻まれていた。ウィローとロンは言葉も出せない様子だ。
「スレイヤーだよ」ジャイルズが面倒臭そうに繰り返した。「バンパイアがいる限り存在する、選ばれし少女だ」
「そのくだりほんっと好きね!」
バフィーがニヤッとした。ジャイルズは当たり前のように無視した。
「スレイヤーはバンパイアを退治する。バフィーがそうであることは内密に。今のところ、必要な情報は以上だ」
「一つ忘れてるよ」ザンダーが口を挟んだ。「どうやって殺すの?」
「それは私の仕事よ!」
バフィーが急いで言った。ザンダーは奴らと戦う気でいるのだ。
「でもジェシーは俺の——」
「——ジェシーを救えなかったのは、あたしのせいなんだから」
ザンダーはイライラした声で「そうじゃない」とつっこんできた。それにはウィローも同意した。
「あなたが来なきゃ、私たちも捕まってたわ……」青白い顔で言った。「……悪いけど気を失っちゃだめ?」
「呼吸して!」
バフィーが慌てて肩を叩くと、ウィローは朦朧としたまま大きく息を吸い込んだ。「……呼吸…」
「そう!——ルークって男が、『マスターに捧げる』って言ってたの。ジェシーが単なる『食糧』じゃなく、その『捧げ物』だったら、まだ生きてるかもしれない。彼を探すわ」
「あー、バカな質問かもしれないけど、『魔法省』に通報しないの?」
ウィローはとにかく事件に関わらないようにするのに必死だったが、ジャイルズはそれを聞いてバカバカしいとばかりに笑い飛ばした。
「通報して何と言うんだ?」
「だから…『バンパイア』とは言わずに、た、ただ『悪いやつがいる』って……言ったらどう…?」
「『魔法省』を呼んでも解決しないの。魔法は通用しないもん」
バフィーはウィローに向かって言い聞かせるように首を振ってみせた。ウィローももちろん落胆した様子だったが、それ以上にハリーとロンがひどくがっかりして溜め息をついた。
「連中の行き先に心当たりは?」
ジャイルズがずれかけたメガネを押し上げながらバフィーに聞いた。
「追いかけようとしたけど、墓地をでたとたん消えたわ。ヒューッ!って」
「飛べるの!?」
ザンダーが目を見開いた。バフィーはさあと肩をすくめた。
「車かもね」
ザンダーは「あぁ…」と納得したように頷いたが、その顔はどこからどう見てもちょっぴり残念がっていた。
「車の音はしなかったけど……」
ハリーが不思議そうに眉をひそめると、ロンが急にニヤニヤ笑いを浮かべてからかった。
「そりゃあそうさ。君は自分より背の低い女の人にノックアウトされてたからな」
プライドをずたずたにされたハリーがひどく衝撃的な顔をすると、ロンはますますニヤニヤした。ジャイルズは二人のやり取りをまるで無視して話を続けた。
「地下に戻ったと考えるのが一番妥当な線だろうなあ…」
「バンパイアは下水道が好きなのよ。光を浴びずに町中どこへでも行けるから」バフィーが口添えした。「でも、あのあたりに出入り口はなかったわ」
「マグルの電気用の地下道なら、町中を走ってる!」
ザンダーが思いついた。みんな「なるほど」と感心したが、ジャイルズはひどく億劫そうに溜め息をついた。
「地下道の見取り図があれば連中の集合場所が分かるかもしれない。マグルの建築管理官に問い合わせてみるか」
バフィーはいよいよじれったくなってきた。
「そんなことしてる時間ないって!」
マグルに問い合わせなんかしている間にジェシーが『捧げ』られてしまったら、助けられるものも助け出せなくなる。みんなが行き詰まって顔を見合わせていると、いちばん予想だにしていなかった人物が、自信に満ち溢れて名乗りを上げた。
「みんな!——他にも方法があるかも」
黙りこくった五人を順番に見回して、ウィローが明るく提案した。
†††
「……スレイヤーだという…証拠はあるのか…?」
マスターがゆっくり手下を振り返って聞いた。ダーラとジェシーは相変わらず困惑した表情を浮かべていたが、ルークは確信に満ちた声色ではっきりと答えた。
「わたしと戦い、なおも生き延びています」
「それだけ聞けば充分だ…」
マスターは考え込むような口ぶりで言った。人間の生き血を塗りたくったような真っ赤な瞳がギラギラとよからぬ光を放っている。
「最後にこのようなことが起きたのはいつだったか…」
「一八四三年、マドリードで——」ルークは少しきまり悪そうに言い淀んだ。「——寝込みを襲われて…」
マスターは忌々しい過去を思い出し、喉の奥から奇妙な音を発した。それは息を呑んだ音にも聞こえたし、うめき声のようにも聞こえたが、どちらにせよひどく嗄れいて、背筋のゾッとするような音だった。
「『収穫の日』の邪魔をする者は阻止せねばならん…」
「そんな真似はさせません!」ルークが声を荒げた。
「心配するな…むこうから出向いてくるさ……」マスターがのんびりと言った。「我々には『切り札』がある……本物のスレイヤーなら…小僧が生きている限り、助けにくるはずだ……」
「『食糧』としか考えていなかったが——おめでとう。お前はたった今昇格した」
ルークはジェシーの背中に腕を回し、ごつごつした短い指で、細い首をぞろぞろとなで上げた。恐ろしくて縮み上がったジェシーにずいっと顔を寄せると、ただでさえおぞましいしわくちゃの顔の上に、ニヤリと邪悪な表情を浮かべた。
「——『オトリ』にな」