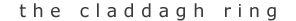「あいつ、追いかけてくると思う?」
「さぁな」
が不安げに話を持ちかけると、 神田はのほうを見向きもせずに言った。
「モヤシの体力がどれだけ持つか・・・。 アイツがあのアクマを倒せるはずがねェからな。ヤツもじき、追いかけてくるだろう」
「・・・?どうして?」
はきょとんと首をかしげた。神田は、アレンがアクマに負けることを前提に物事を考えている。いくら新米だからといって、 まさかこんなに早く殺されてしまうなんてことはないと思うが。
「見てわかっただろ。アクマの方が一枚上手なんだよ。 進化した相手の能力も、モヤシはまだわかってねェ」
「・・・・・・根性で勝てると思うけど・・・その、頑張ればね」
「あぁ、お前ならできるかもな。ただし今アクマと闘ってんのはそれ程経験つんでねェへろへろのモヤシなガキなんだよ」
―――すごい言い方・・・・・・。
神田の容赦ない、噛み付かんばかりの迫力に、怒りを通り越して呆れてしまった。 こういうのを、『犬猿の仲』と言うのかな。いや、犬猿の仲よりもっと仲が悪いかもしれない。
「あの・・・」
二人の会話に、おずおずと少女が割り込んできた。二人が同時に少女を見やると、彼女は少し驚いてびくりと肩を跳ねさせた。
「その…この街には、強い日差しから逃れるための地下通路があるんだけど…」
「地下通路?」
神田がオウム返しに聞き返した。
「うん。迷路みたいに入り組んでて、知らずに入ると迷うけれど、出口のひとつに谷を抜けて 海岸線に出られるのがある・・・・・・・・。あのアクマとかいう化け物は空を飛ぶ・・・地下に隠れた方がいいよ」
は神田の顔を見た。神田ものほうに目を向けた。二人とも、考えていることは同じのようだ―――少しでも 遠くに逃げられれば、それだけの時間が稼げる。
神田とは、屋根から下りて同時に着地した。 背負っていた者を降ろし、肩を上下させて息を整える。不思議と、体がさっきよりも少し軽く感じられた。
―――ジリリリリン!―――
黒電話のようなベル。ティナシャロンだろうか、それとも神田のゴーレムか。
は慌てて服の袖からティナシャロンを引っ張り出したが、残念ながら音源は神田のゴーレムだった。 ティナシャロンは相変わらず、の周りを好き勝手に動き回っている。
「トマか、そっちはどうなった?」
どうやら、通話の相手は途中で別れたファインダーのトマのようだ。
『別の廃屋から伺っておりましたが、 先程激しい衝撃があってウォーカー殿の安否は不明です』
刹那、頭に物凄い衝撃が走った。
まるで、頭を金槌で殴られたかのように、グワングワンと。体の中を、物凄いスピードで氷のように冷たいものが駆け巡っていく。
息がつまるようだった。
「アレンくん・・・が・・・・・・?安・・・否不・・・・明・・・・・・?」
途切れ途切れの、 それだけの言葉で精一杯だった。泣きたくなるような、そして体が恐怖でブルブルと震えている。今まで行動を共にしていた人間が 突然消えてしまうということは、にとってこの上なく恐ろしいことだった。
『あ、今アクマだけ屋内から出てきました。 ゴーレムを襲っています』
トマのくぐもった声が、奇妙なほどよく頭に響いてきた。辺りは、先程よりも一層と静かになったよう に感じられる。
「わかった。今、俺のゴーレムを案内役に向かわせるから、ティムだけつれてこっちへ来い。長居は危険だ」
神田はあくまでも冷静だった。その上、いつもと変わりないその表情からは、仲間が行方不明だという事に対してなんの焦りも 感じていないようだった。
「今はティムキャンピーの特殊能力が必要だからな。何かあったら、のティナに連絡を入れろ」
トマが肯定の返事を返してきた直後、通信がブツリと切れた。
「さて」
神田は、ゴーレムが羽ばたいていく のを見送りながら、老人と少女の方に顔を向けた。
「それじゃ地下に入るが、道は知ってるんだろうな?」
「知って・・・・・・いる・・・」
神田の問いに答えたのは、今度は背の高い老人の方だった。しゃがれた声を、 一生懸命に喉から絞り出して。
「グゾル・・・―――」
少女は、心配そうに彼の名を呼ぶ。
「私は・・・ここに500年いる。知らぬ道はない」
そう言って、グゾルは大きな三角帽子を脱いだ。その下から、 しわくちゃの肌が露になる。あちこちが腫れ上がり、肌の色は大袈裟に変色、そして片目は潰れていた。
も神田も言葉を失い、思わず目を見開いてしまった。
「くく・・・醜いだろう」
「お前が人形か? 話せるとは驚きだな」
神田は冷たく言い放ったが、にはそれを咎めるほどの元気なんてなかった。 ただ、淡々と二人の会話が続いていくのを眺めるだけ。それで精一杯だった。
「そうだ・・・。お前達は私の心臓を奪いに来たの だろう?」
「できれば今すぐ頂きたい。デカい人形のまま運ぶのは手間がかかるからな」
少女の顔色が変わったのを、 は見逃さなかった。少女はボロ布のような服を翻しながら、血相を変えてグゾルの前に立ちはだかる。
「ち、地下の道はグゾルしか知らない!グゾルが居ないと迷うだけだよ!!」
「お前は何なんだ?」
神田は、少女の言葉を無視して訊ねた。その言い方に、少しばかりトゲがあるような気がした。少女の目が泳ぐ。 神田の言葉に困惑しているのが、誰の目にも明らかだった。
「私は・・・グゾルの―――」
「人間に捨てられていた・・・子供だ!」
少女がモゴモゴと口ごもると、グゾルがしゃがれた声を張り上げた。 その声はとても必死な様子だった。
「ゲホ・・・ッ、私が・・・拾ったから、側に・・・・・・置いでいだ・・・!!! ゲホッ、ゲホッ・・・!!!!」
「グ・・・グゾル・・・っ!」
血を吐くんじゃないかと思うほど、大きく咳き込んだグゾル。 少女は顔色を真っ青にして金切り声を上げる。その様子を見ながら、と神田は顔を見合わせた。弱々しい視線と、 鋭い視線がかち合う。
―――怪しい。
そうは思ったものの、二人を眺めているだけでは何も見破ることはできない。
「神田殿」
トマが建物の陰から現れた。神田はそれに気付くと、ゆっくりと 立ち上がりながら二人に言った。
「悪いが、こちらも引き下がれん。敵にお前の心臓を奪われるわけにはいかないんだ。 今はいいが、最後には必ず心臓をもらう」
そこまで言い切ってから、ふと、神田の目つきがやわらかくなったように思えた。
「巻き込んですまない」
「「・・・・・・・・・・・・・・・・・」」
少女もグゾルも、ただきょとんと神田を見上げる だけで何も言わなかった。
別行動
「ティムキャンピーです」
そう言ってトマが差し出した手の上には、無残としか言いようのない金色の残骸が乗せられていた。 粉々になったカケラ。まるで、ただの石のような。
カケラがひとつ、ふわりと中に浮かび上がった。 それを合図としていたかのように、無数のカケラが後に続き、金色のゴーレムが蘇生していく。正面の正十字がキレイに繋がった頃、 神田はゆっくりと口を開いた。
「お前が見たアクマの情報を見せてくれ、ティム」
羽根が、尾が、手が、 欠けた所も見えないくらいに蘇生した。ティムはゆっくりと口を開く。とがった牙が露になった。
そこから浮かび上がる、 アクマの映像。そいつは、やがてアレンとそっくりの姿に変わる。神田と、ゴーレム達までもが、食い入るようにそれを見つめた。
「鏡のようだ・・・・・・」
「・・・それ、どういう意味?」
神田がポツリと吐いた言葉。 は意味がよく理解できず、小声で聞き返した。神田はまだ、ティムの映像から目を離さない。
「逆さまなんだよ、このアクマ・・・見てみろ」
神田は顔を少し動かしてに促した。
「奴がモヤシに化けた時の姿・・・服とか武器とか。左右逆になってる―――ほら、切られた偽者も、よく見ると逆・・・」
彼の言うとおりだった。アレンの対アクマ武器は、アクマの左手ではなく右に付いている。傷と額のペンタクルも、ローズクロスも、 全部が左右逆だった。
「しかもコレは、中身は空で360度外見だけのもの―――・・・ただ単に『化ける』能力じゃない」
「何かで対象物を写し取ってる・・・・・・というべきね」
神田の言葉を引き継いだ。神田はコクリと深く頷く。 ティムキャンピーの映像は続いた。
「しかも、写し取ったそれを装備すると、その能力を自分のものにできるようだ・・・ モヤシの左腕を変形させて攻撃している所を見るとな。厄介なモン取られやがってアイツ・・・」
神田は顔をしかめて舌打ちした。もう今日になって何回舌打ちしているんだろう。数えたら相当な数になるんじゃないかな。
「でも、取られちゃった者は仕方ないと思うけどね・・・わたし、それよりアレンくんが無事かどうか―――」
は両腕をさすりながらポソリと言った。神田の背中に向かって。神田は、こちらを振り向く気配を見せない。
「神田くん、聞いてる?」
ひょっこりと神田の方へ回り込み、恐る恐る顔を見上げてみた。同時に、神田が物凄い怒声を上げた。
「 ふ た り が い な い ! ! 」
―――間。
「・・・・・・えっ?」
素っ頓狂な声を上げてしまった。神田の視線の先を追ってみれば、確かに、いるはずのグゾル達の姿が見当たらない。
「 に゛ っ 、 逃 げ や が っ た ! ! ! 」
「えええええっ、どうしよう神田くん!?」
保護すべきイノセンスに逃げられるだなんて、夢にも思っていなかった。ましてや、相手は足が二本はえた人型だ。 は焦り、オロオロしながら神田の袖にすがりついた。
「俺が知るか!くそっ、あいつらどこに―――」
二人が慌てふためいていると、トマが何かに気付いて背後を振り返った。背後から忍び寄る足音と気配・・・は、自分の顔が どんどん蒼白になっていくのがわかった。
―――後ろに、誰かがいる・・・。
「神田殿、殿―――後ろ・・・!!」
震えるトマの声を合図に、二人はゆっくりと後ろを振り返った。 刹那、体の中を恐ろしいものが駆け抜けて行ったような気がした。息がつまるような感覚・・・凍りつく内臓。
「アレンくん・・・?左右・・・逆・・・・・・」