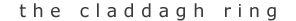「どこか手当てできる場所を探さないと・・・」
は神田を背負いながら呻いた。神田は細身なので意外に軽い。
「くそ・・・ここが一体どこなのかサッパリわからない―――」
「そうね。どこに行きたいのかハッキリしてないと ティナシャロンも使えないから・・・ごめん、その、役立たずで・・・・・・」
アレンの悪態に怯えて謝ると、 彼の厳しい視線が飛んできた。
「嘘、えっと、だからその・・・」
が慌てふためいて訂正しようとしたが、 なんと言えばいいのか思い浮かばない。情けなく口ごもっていると、アレンが何かに気付いて顔を上げた。
「・・・・・・歌・・・?」
「え?歌って何―――」
は首をかしげて訊ねかけて、口を閉ざした。 僅かに聞こえてくる、美しい歌声。酷く美しい旋律の、造花の子守唄だった。
人形劇
たちは、声のするほうに向かって 歩き出した。疲労と痛みで頭がガンガンする。足が鉛のように重く、歩くのも難しいくらいだ。それでも、自分達が進む方から聴こえる声 は、どんどん大きくなってくる。
その声はとても美しく、羨ましいくらいだった。歌は有名な子守唄なのに、 声が綺麗だからかもっと上質なものに思える。声に自分達の足音が重なってしまうのが勿体無い。
歩き続けているうちに、 プツリと歌声が途切れた。
それは、ちょうど達が広場へ出たところで、倒れかけた柱の向こうには二人の人影が 見受けられる。一人はグゾルで、もう一人は小柄な女の子だった。髪の色から予測するに、ララだろうか?
「泣いているのか・・・ララ?」
グゾルの問いに驚いて、ララは目を見開いた。
「ヘンなこと訊くんだね、グゾル」
「何か・・・悲しんでいるように聴こえた・・・」
グゾルがかすれた声で言う。ララは悲しげに微笑み、 グゾルの方に身を乗り出して言った。
「 私 は 人 形 だ よ ・ ・ ・ ? 」
ララの衝撃的な言葉。 アレンとは互いの顔を見合わせた。人形は、グゾルではなくララの方だったのか。『醜い亡霊』という噂は嘘だったのだろうか? でも、なぜグゾルはそんな事を偽ったのだろう。
「グゾル。どうして自分が人形だなんて嘘ついたの?」
ララの問いかけで、グゾルが押し黙った。ここからでは光の関係でグゾルの顔に影がかかってしまうので、その表情は読み取れない。 それでも、ララが彼の顔を見て驚いたのだけは見て取れた。
「私はとても・・・醜い人間だよ―――ララを他人に壊されたく なかった・・・」
グゾルが言った。その声は、悲しみに押しつぶされたようにかすれていて。今にも死んでしまいそうに弱々しく、 聞いているだけでも泣きたくなるくらいの、切ない言葉。
「ララ・・・ずっとそばにいてくれ―――そして私が死ぬとき、 私の手でお前を壊させてくれ・・・」
短い沈黙が流れた。そんな中、ララはそっと白い手をグゾルの方へ伸ばす。 そしてララは、長い髪の毛をふわりとなびかせながら、グゾルにギュッと抱きついた。その顔は幸せそうに微笑んでいて。
「はい、グゾル―――」
ララの澄んだ綺麗な声が、乾燥の地に鈴の音のように響き渡った。
「―――ララはグゾルだけの お人形だもの・・・次は何のお歌がいい?」
グゾルの頬を、きらりと何か光るものが伝った。
「私は醜い・・・醜い・・・人間・・・だ」
途切れ途切れのグゾルの言葉。それが何だか悲しくて、見ているだけでも、辛くなる。 だって、もしも彼女が人形ならば―――わたしたちはララを壊さなきゃならない。それが任務なのだ。
「 ! ! ! 」
突然、向こうがこちらの存在に気付いた。ララはグゾルから離れると、勢いよくこちらを振り返る。
「あ、ごめんなさい。立ち聞きするつもりは無かったんですけど・・・」
慌てて言い訳するアレン。しかし、ララの視線が鋭い。 まるで、視線だけで二人とも射殺せそうな勢いだ。
「・・・キミが人形だったんですね」
もはや、ララは容赦しなかった。倒れていた石柱に指を食い込ませ、高々と持ち上げる。こびり付いていた砂が、音を立てて滑り落ち、 立ち上がったララの姿をカーテンのように隠す。
それでも、アレンとが顔を引きつらせるには充分だった。
「う・・・あのか細い腕のどこにあんな怪力を・・・!?」
「あぁ・・・嘘でしょう!?やだ、も〜・・・・・・」
ララの目がぎらりと光った。文句をたれる二人に構わず、巨大な石柱を力の限り投げつけてくる。物凄い迫力で突っ込んでくる石柱。 二人はそれぞれ怪我人を担いだまま、逆の方向に飛んで避けた。
「 ど わ た っ ! ? 」
「 や ー っ ! ! 」
響き渡る奇声と、空気を震わせる爆音。着地しながら振り向くと、また石柱を持ち上げる ララの姿が見えた。
「ままま待って待って!!落ち着いて話しま・・・ わ っ ! ! ! 」
アレンは焦りながらも口を開くが、ララの攻撃は止まらない。アレンの言葉も、途中から悲鳴に変わってしまう。そして、 ララが再度石柱に手をかけた。どうやら聞いてくれそうに無い。
「!」
アレンが声を上げながら駆け寄ってきた。
「、トマを頼みます!」
「えっ!?ちょっ―――」
ぐったりとしているトマを半ば押し付けるように手渡し、 アレンはララのほうへ飛び出した。口に挟んで左手の手袋を外し、イノセンスを発動させる。黒い十字架が光った。
アレンは、自分に向かって飛んできた柱をかがんで避け、左手の指を食い込ませるようにして柱をキャッチした。ララが驚いて目を見張る と、アレンは得意そうにニッと口の端を吊り上げる。
「それっ!!」
アレンの掛け声と共に、ギュンギュンと音を立てて 石柱が飛んだ。今度はアレンからララに向かって。ララは、次に襲い掛かってくるであろう衝撃に、頭を抱えてギュッと目をつぶった。
ガ ガ ガ ガ ガ ガ ! !
けたたましい破壊音・・・それに耐え切れず、も顔を伏せた。 まさか、アレンはララを破壊してしまったのだろうか?脳内をよぎった、嫌な予感。恐る恐る顔を上げると、そこには予想外の光景が 広がっていた。
「あ・・・石柱が―――」
アレンの投げた石柱が、ララの背後の石柱を一本残らずへし折り、 彼のところへ戻っていく。空気を切り、スピンしながら、勢いよく。アレンは左手でそれをキャッチすると、抱きかかえたままララの ほうへ一歩踏み出した。
「もう投げるものは無いですよ」
へにゃり、と和らぐアレンの表情。
「お願いです。 何か事情があるなら教えてください―――可愛いコ相手に闘えませんよ」
ララは唖然とアレンの顔を見上げていた。 アレンは優しく微笑んでいて、ララから心臓を取ったりしない、と顔に表している。それでも、ララはまだ困惑した様子で、戸惑った視線 をのほうに滑らせてきた。
「わ、わたしもっ、そのっ・・・あなたには手を出さないから・・・っ!だから・・・ 大丈夫・・・」
慌てておどおどしながら首を振ると、ララはやっと安心したようで。足の力を抜き、ガクリとそこに膝をつく。
「・・・グゾルは、もうじき死んでしまうの」
ポソリと、弱々しい声でララは言った。少し離れた所で、石柱にもたれ グゾルは肩で息をしている。
「それまで私を彼から離さないで!この心臓はあなたたちにあげていいから・・・!」
ララの声は、空っぽなその空間にむなしい響きで轟いた。
***
同時刻、イタリアから遠く離れた、 英国の土地。
一人の少女が、何かから逃げまわっていた。息も切れ切れだが、それでも彼女は走るのをやめない。肌は擦り切れ、 血がにじんでいる。服もボロボロで、顔は涙でぐちゃぐちゃだった。
少女は道の角を曲がり、そして壁にぶち当たった。 行き止まり―――もう逃げられない。突きつけられたその現実に、彼女は悲鳴にならない声を上げる。奇妙な足音が近づいてくる。 少女は、壁に背中を向けて振り返った。
角から現れたのは、一体のアクマだった。
奇妙奇天烈なその姿に、 少女は怯えきって腰を抜かしてしまう。狂ったような血走った目が少女を見据えた時、また別の影が空に差した。
黒いコートをなびかせた、茶色い髪の男。
手には長い死神鎌が、月の光を受けて銀にきらめいている。刃の根元にぶら下がる、 頭蓋骨のアクセサリ。
アクマはその存在に気付かず、少女に向かって腕を振り上げている。しかし、少女だけは、 アクマの頭上に振り下ろされる鎌に釘付けになっていた。鋭い刃の先が、物凄いスピードで肉を切り裂き―――。
「 き ゃ あ あ あ あ あ ぁ ぁ ぁ あ あ ぁ あ ぁ ! ! 」
アクマの破壊による爆発音。 少女の恐怖心による悲鳴。自分の横をすり抜けて駆けて行く少女を横目に、少年は顔にこびり付いた血をぬぐった。
「すんげー悲鳴・・・」
溜め息と共にこぼれた言葉。それは、再び静まり返った夜空の下に良く響き渡った。