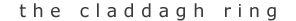はチラチラとセシリーを盗み見ながら、フォアグラを口につっこんだ。だけじゃない、神田もフランスパンをちぎりながら、 セシリーを鋭い視線で観察している。
―――む・・・。
何だかわからないけど、セシリーと神田に対して無性に腹が立った。
「じゃあカンダさんは、任務のためにこの町へ?」
セシリーは輝かしいくらいの微笑みを浮かべて神田に尋ねた。 ところが、神田はもうさっきから何の応答もしていない。それでもセシリーは、神田の無言を都合のいいように解釈してお喋りを続けた。
「きっと、私と貴方が出会えたのも運命ですわね!私、貴方みたいに素敵な方と出会えて、今とても幸せ!」
夢見心地の乙女気取り。 はブチブチと自分の額に浮かび上がる青筋に気付かないふりをしながら、銀に輝くフォークを力の限り握り締めた。
ラビが顔を 引きつらせているのは、きっとの見間違いだ。
「セシリー様、はしたないですよ」
執事がきびきびとセシリーをたし なめた。すると彼女は「はいはい」と面倒くさそうに返事しながらスープを金のスプーンで小さな口に流し込んだ。
「お嬢様気取りやがって――このメスブタ」
が虫の声ほどの小さい、それでも物凄い声色で悪態を呟くと、 両隣に座っていた神田とラビが同時にぶっと吹き出した。
黒髪の女
「全く!なんなのあの女の子!!かわいこぶりっ子して、お嬢様気取り!?色気振りまいて、そのくせファッションセンス最低! 髪型もペシャンコだわ!ありえない!!」
部屋に案内され、は甲高い声で愚痴をぶちまけた。ちなみに、神田は客室の一番 広い豪華な部屋へ案内され、ラビとは客室の小部屋、しかも同室だ。こんな酷い扱い、許せない――こればかりはラビも同感だった。
「ちゃん、ベッドで寝るさ?俺は床でもいーけど――」
ラビが恐る恐るの愚痴に口を挟むと、は ぷいっと顔を背けてしまった。
「寝ない!ずっと起きてる!」
「はぁ!?」
「寝ないって言ったのよ!こんなムカムカしてたら 寝られないし、そりゃ、夜暗いのは怖いけど、朝まで町をパトロールしてるわ!」
カンカンに怒鳴りながら、は恍輝を背負って、 黒い革コートを団服の上に羽織った。ジャラジャラと鎖がこすれる音がして、コートの内側に縫い付けられた、大量の魔除けが揺れた。
「寝不足で足手まといになってユウに捨てられても知らないさー」
「知らないわよ、あんなすけべ男!時代遅れの侍!長髪!女男!」
二人の言い合いを見ていて、ラビはいつも思う。
―――ガキのケンカさー・・・
「行ってきます!壊してきます!むしろ殺して きます!!」
「うん、おやすみー・・・って待てェ!何殺す気さ、ちゃん!!」
怖がり少女が発した突然の爆弾発言に脳が 追いつかず、ラビは思わずノリツッコミを入れてしまった。
「―――何も殺さないわよ、幻聴じゃないの?」
フッと嘲笑うよう な笑いを残し、は荒々しく部屋を出て行った。ラビはポツリと部屋の中に残され、安堵やら恐怖やら呆れやら色々混じった溜め息を はぁーと吐き出した。
「ちゃん――マジで怒ってるさ・・・?」
赤いフカフカのじゅうたんをズカズカ 踏みしめ、黄金のシャンデリアの下を早歩きし、巨大な銅像の前を素通りし、歴代の姫の肖像画に悪態を吐き捨て、は城の中を不機嫌 モードで徘徊し続けた。
本当は外へ行こうとしたのだが、あまりにも暗いのが怖くてためらったのだ。
エクソシストなのに、 情けないな、とは心の中で自分にまで悪態をついた。バカみたいだ、そう思ったりもした。なんで、今日はこんなに腹が立つのだろう? 人前で我を忘れるほどカンカンになったのが今更ながらとても恥ずかしくなってきた。
―――神田くんに嫌われたかな…。
ふと不安になって、の足がピタリと止まった。そして、顔を真っ青に染めて、両手で頬をベチンと押さえた。
あんな、 お嬢様気取りやがってこのメスブタなんて――絶対聞こえてたに違いない。絶対嫌われた・・・どうしよう!?あんなの女の子が使う言葉なんか じゃないのに――そうだ、セシリーの方が綺麗だし、女の子らしいし、神田も絶対彼女の方が好
っ と 。
「何を神田くんなんかのことでモジモジしてんのよ、気色悪い!わたしが!!」
また自分にブツブツ 悪態をつきはじめる。そうだ、何でこんなに神田を意識する必要があるんだろう?別にヤキモチやく必要なんかないのに・・・だって、 神田みたいな冷血人間は大ッ嫌いなんだから。
「―――ぁ゛ぁ゛ぁ゛ぁ゛ぁ゛ぁ゛ぁ゛ぁ゛ぁ゛ぁ゛ぁ゛・・・・・・・・・・・・・」
キーン、と鋭い悪寒が背中を貫いたような気がして、はビクッと顔を上げた。背後から聞こえてくる、不気味な呻き 声――体がぶるっと震え、は恐怖に目を見開いた。
「・・・・・・・・・・・・・ぁ゛ぁ゛ぁ゛ぁ゛ぁ゛ぁ゛ぁ゛ぁ゛ぁ゛―――」
―――また、聞こえた・・・!!!
は目を見開いて、体をブルブル震わせたまま、ゆっくりと背後を振り返った。 首筋が凍り付いていて、顔を後ろに向けるには足ごとその場で半回転しなければならなかった。
しかし、振り向いた先にはなにも いなかった。
そこには延々と赤いじゅうたんを敷いた廊下が闇へと続いているだけで、呻き声を発するようなものはいない。
いつの間にか、辺りはシーンと静まり返っていて、の荒くなった息が微かに響き渡ってしまうほどだった。見開いたままの目は、 月の光を受けてチラチラと光っている。
そのとき、シャンデリアの明かりが、ブツッと音を立てて消えた。
「!!?」
は大きく息を呑んで、一歩後ずさった。恐怖が体をみるみるうちに虫食んでいくのがわかる。悲鳴を上げようとしても、 声を聞きつけて何かが襲ってくるのが怖くて、ヒィヒィ掠れた息を喉から出すことしかできなかった。
ド ン ド ン ド ン ド ン ! ! !
何かが、一番近くの部屋のドアを叩いた。内側からだ。頭の中が真っ白に なった――恍輝を鞘から抜くことすら、今のには考え付かなかった。ただ恐ろしくて、怖くて―――。
そっと、金のドアノブ に手を触れた。
そっと捻って押し開けると、ギギギ、と酷く軋む音が異様なほど響いた。の息は荒い――ホラー映画の一シーンのように、彼女の息の音が大きく響いている。
ドアを完全に開けるなり、は怯えて3歩も後ずさりした。幽霊が出てきたら、 どうしよう?アクマのことなんか、すっかり頭の中から消えていた。遠目からそっとドアの向こうを見やる。
何もいない。
もう諦めればいいのに、と思いながらも、は恐る恐るドアの敷居をまたいだ。そこは暗い部屋で、ピアノが一つだけ置いてあるだけの、 何の変哲もない空間だった。気のせいだったのかな、はそう思い、ほっと溜め息を一つついた。
――――その時。
大太鼓がドンと音を響かせたような衝撃が、の心臓に走った。恐怖に見開いていた目は、今や限界と言えるほど大きく 開いている。悲鳴の代わりに呑んだ息でむせ返りそうになったが、あいにく今の彼女にそんな余裕はなかった。
上から垂れ下がる長い黒髪、ギラギラと光る大きな目、肌はほぼ青で唇は紫、黒髪からはべっとりと赤い液体が滴り落ちている。
そんな女が、の目の前の天井から、頭を下にしてぶら下がっていたのだ。
「 き ゃ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ ! ! ! 」
は頭を抱え、鋭い悲鳴を力の限り上げ続けた――それでも、恐ろしい光景から目が釘付けになったように 離れなくて、は泣きながら来た道を我武者羅に駆け出した。