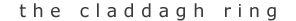恐ろしくて、気持ち悪くて。
は逃げ、そしてその後ろを、女がギトギトの髪の毛を引きずりながら四つん這いになって追いかけてきた。
「…………は、くそっ―――」
足がもつれて倒れてしまいそうだ。でも、スピードを緩めたら追いつかれてしまう…!
は恐怖に怯えながら、恐る恐る背後を振り返った――血まみれの黒髪の女は、青白い腕を突き出して猛スピードで追いかけてくる。 黒髪のわずかな隙間から、ギョロついた巨大な目がを見上げていた。
「うっ……!?」
気持ち悪い。 精神的にもうヤバいかも――さっき食べたばかりのフォアグラやクロワッサンが、口をついて飛び出してきそうだ。
それくらい、 背後の光景はグロテスクで恐ろしいものだった。
はとにかく城の中を駆け回り、適当に階段を駆け上って、 一つの部屋の中になだれ込んだ。急いでドアを閉め、鍵を内側からロックする。そして背中の鞘から恍輝を抜くと、 ドアにピッタリ背中をつけて剣をしっかりと構えた。
恐る恐る、耳をドアの表面に近づける――何の音もしなかった。
が閉じこもっている部屋は、不自然なほど暗い。
「神様…!!」
ここまで来たら、もう神頼みだ。 今まで元帥と共に何度も事件に向き合ってきたが、こんなに恐ろしい心霊現象は初めてだ。
息は切れ切れで、 そしてしゃくり上げる音も呼吸に混じって響いていた。
もう何時間も経ったような気がした。
左手だけをそっと恍輝から離し、 ポケットからお気に入りの懐中時計を引っ張り出す――まだ部屋を出て十分も経っていなかった。
―――でもさすがに、消えたかしら…?
少なくとも一分くらいは音沙汰なしだ。きっと撒いたか、それか諦めて巣に戻ったかのどっちかだ。は一気に脱力し、 大袈裟な溜め息を吐くと共にそっと胸を撫で下ろした。
「………怖かったぁ」
正直な話、まだ怖い。もう泣きたいくらいだ。 心臓はドキドキうるさいし、体中が恐怖で痺れてしまっている。早くラビのところへ戻ろう――は恍輝を鞘に戻し、立ち上がろうとして 地面にそっと手をついた。
床に、不自然な感触があった。
―――髪…の、毛……………?
「ッ!!??」
は大きく息を呑んで跳びあがった。手に、生温かいヌメヌメとした液体がビットリこびり付いている。 まるで泣いた子供のようにしゃくり上げ、息を何度も呑み、はその現実を否定するように首を振りながら後ずさりした。
ドアと床の隙間から、部屋の中へ向かって。
血まみれの髪の毛が、グチャグチャ音を立てて入り込んでくる。
血の気が引いた。背筋が凍りついた。ゾーッと悪寒が体中を駆け巡った。脳がフリーズした。どす黒い血を取り巻いた黒髪から 逃げるように、は後ずさり続けた。
ところが、数秒後。背中が壁にぶち当たるのを感じた。
―――行き止まり…!!
は恐る恐る壁を振り返り、行き止まりになったのを確認すると、またドアのほうに視線を戻した。
「え……!?」
間抜けな声が響いた――視線を戻した先に、女はいなかったのだ。
どこに行ったんだろう。の心臓が一層騒がしくなった――相 手が見えなくなると、いつどこから襲ってくるか予想できなくなって余計怖くなる。恐怖に恐怖が重なって、もう泣いたってどうにもならなかった。
―――バンバンバン!
けたたましい音が、のすぐ後ろで聞こえた。
窓だ。
の体を 悪寒が駆け巡り、血がサーッと凍り始めた。冷や汗が米神を伝う。
振り返りたくなかった――それでも、後ろから攻撃されるのも嫌だ。 は唾を飲み込むと、恐る恐る背後を振り返った。
信じられなかった。
我武者羅でも、は確かに 城を駆け上ってきたはずだ。それなのに、今、窓の外から、黒髪の女がこちらをじっと見上げていたのだ。
髪にこびり付いていた血が 窓に付着し、髪の毛もモジャモジャになってガラスにくっついている。ギョロついた巨大な目はの顔を見つめて逸らさない。
紫色に変色した唇は、に向かってゆっくりと開き――。
「 助 け て 」
その途端、 は膝から崩れるように倒れて、意識を手放した。
セシリー
突如、何かにバチッと頬を叩かれて、は驚いて跳ね起きた。すると、ふわりと暖かい掛け布団が胸から滑り 落ちて、次いで視界に神田のしかめっ面とラビの心配そうな顔が飛び込んできた。
「あれ……?ここって―――」
ポカンと したまま呟くと、ラビと神田がホッと安堵の溜め息を吐き出し、辺りの緊張の糸が大幅に緩んだようだった。
「よかったー!ちゃん、 丸一日も目ェ覚まさなかったんさー!」
「ま、丸一日!?」
ラビの言葉に驚いて、はひっくり返った声を上げた。 パッと視線を窓にやってみると、外は夕日で真っ赤に染まっている――貴重な時間を無駄にしてしまった。
「だから言ったじゃねェか。 引っ叩きゃ起きるだろって」
「引っ叩――な、何なのその起こし方!?やさしく揺さぶったっていいと思わない!?」
顔を見るなり いがみ合う二人。神田とが早速言い合い始めると、二人の間に挟まれたラビは完全に困り果て、とりあえず鎮火しようと両手を挙げて 二人の口をベチッと覆った。
「まーまーいいじゃん生きてたんだしさ!ちゃんも牙むかなーい。ユウ、マジでちゃんの事 心配してたんだぜ?」
「嘘おっしゃい!」
そんな事、天と地がひっくり返ったってありえない。が即座にラビに言い返すと、 神田がピクリと反応して、最大限の殺気をブワッと放った。
「う、『嘘おっしゃい』だぁ!?」
「―――な、なによ」
少し怯みつつ、それでもは退こうとしない。
「お前なあ!誰がここまでお前を運んできてやったと思ってんだ!誰が看病して やったと思ってんだ!礼ってモンはねェのかよ!」
「え、」
この言い方――ひょっとして、をここまで運んでくれたのは 神田だったのだろうか?はすっかり当たり前のようにラビだと思い込んでいたし、その上神田の顔を見るなりガミガミガミガミ……。
「ご、ごめ――――」
あまりにも申し訳なくて、それに神田の形相が怖くて、は謝ろうと口を開いた。
―――― と こ ろ が 。
「 カ ン ダ さ ん ! ? 」
乱暴にはね開けられたドアが壁にぶつかって 跳ね返り、物凄い音を響かせた。甲高い声が騒がしく部屋の中に飛び込んできて、は色んな意味で僅かな頭痛を覚えた。
セシリー・クロフォードのご登場だ。
はもはや神田に対する謝罪の言葉を言いかけていたのも忘れ、ただ信じられないと言う 表情でセシリーをじっと見つめた――病人がいるというのに、この騒ぎは一体なんなんだろう?
「………チッ」
神田があからさま に面倒くさそうな表情で舌打ちした。しかし、セシリーにとって神田の心情など今はどうでもいいいらしい。
セシリーは図々しく神田に とびつき、さらに細い腕を彼の首に回してギュッと抱きついた。
「なっ………!!」
「あららー」
が青筋を浮かべ ている傍らで、ラビが呆れたように間抜けな声を上げる。しかし、セシリーは神田から離れようとはしない。
「カンダさん、お姿が 見当たらないから心配したのよ?昨日の夜もお部屋に行ったらいらっしゃらなかったでしょう?」
「………………………………」
振り払えばいいものの、神田はそれすら実行に移そうとしない。ひょっとして、まんざらでもないのだろうか?時間が経てば経つほどグラグラ とはらわたが煮えくり返ってしまい、はギリギリ奥歯を食いしばりながら羽毛布団を握り締めた。
「この町は夜になると、 恐ろしい幽霊が出ると聞くわ――私、それが恐ろしくって……お願い、今晩は一緒にいてくださらない?」
「………………………………」
何も言わない神田。嫌なら嫌と断ればいいものを!やっぱりコイツ、嫌がっていないんだ!はついにぶち切れて、羽毛布団を ビリビリッと豪快に破き捨てた。
「 ど ー ぞ ! 」
布団を蹴り飛ばし、はベッドから立ち上がりながら 荒い怒声をさらに荒げた。ベッド脇に立てかけてあった恍輝を背負い、革コートを羽織り、ラビの襟首を掴んで引きずるようにして出口へ向かう。
誰もが唖然としていて、ラビもどうすればいいかわからずに、黙ってのなすがままにされていた。が、神田はいち早く正気に 戻り、そしてすぐさまの鞘を引っつかんで引きとめた。
「おい!お前、どこに行―――」
「 帰 り ま す ! 」
はまた怒鳴った。まるで夫婦喧嘩中の嫁の「実家に帰ります」状態だ。
「わたしとラビはもう本部に帰還しますので! 事件解決までお二人ともゆーっくりお幸せに暮らしたらどう!?」
「「はぁ!?」」
今度はラビも正気に戻り、神田と声をそろえた。
「神田くんなら任務もカンッタンにこなせるわよねぇ!?何しろペアに向かって『足手まといになるようだったら見捨てるぜ』なんて 口たたくんですものね!自分が足手まといになるほど弱くはないと自信があるから言える言葉でしょうに!」
耳まで真っ赤に染めて、 カンカンになりながら喚き散らすと、神田がの鞘からパッと手を放して、思わず数歩後ずさった。
怒りは一向に治まる気配を見せず、 は鞘を背中から外すと、ドスンと乱暴に床へつきたてた。
「わたしは急いで帰って他の任務のヘルプにでも行きますからね! だってわたし、エクソシスト班のリーダーだもの!科学班のお手伝いもあるし、あー忙しい忙しい!こんな任務に付き合ってられないわねっ!」
かつて、こんなに怒り狂ったことが、そしてこんなに怒鳴り散らしたことがあっただろうか?いや、それどころか、自分には人に向かって 怒鳴った記憶さえも持っていない。神田とセシリーがどうしてあんなに仲良さ気にいるんだろう。それが無性にムカついて…。
は部屋に駆け込むと、豪華なドアをバーンと鳴らして閉めた。