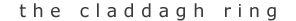が乱暴に荷造りしているのを遠めに眺めながら、ラビがポツリと言った。
「当たり前でしょう!どうせわたしは神田くんにとって足手まといなのよ!だったら――別に帰ったってかまわないはずだもの」
「うーん、ちゃんが足手まといって思われてたとしてもねー、俺は違うかもしれないさ」
ラビがモゴモゴと口を開くと、 は荷造りする手を休めてラビのほうに顔を向けた。
「それ……どういう意味?」
静かにはなった声は怒りと悔しさで 震えていて、ほとんど聞き取りづらかった。
「わたしが――足手まといで、あなたは違うって……そう言いたいの?」
「………」
ラビは「そうだよ」と答える代わりに、気まずそうに視線を逸らした。は手に握っていた懐中電灯を鞄の中に投げ入れると、 涙を含んだ目をグイッと乱暴に拭った。
「ええ、ええ!その通りでしょうよ!どうせわたしは新米の弱っちいエクソシストです! そんなこと言われなくたってわかってるし――ましてや、これ以上成長することもないって…一番知ってるのはわたしなのよ!」
ラビに向かってそこまで怒鳴り切ると、はまた荷造りを再会した。魔法道具を乱暴に詰め込み、包帯を投げ入れ。会って間もない人間に まで足手まといと言われ、はもう本当に泣きたくなってきた。
でも、ここで泣き出したら、もっと弱虫に見られてしまう。 目の奥に浮かんだ涙を零さないようにしながら、は最後の手鏡を乱暴に突っ込んだ。
ガシッ―――。
鞄の中から、何かに手をつかまれた。ティナシャロンだろうか?は面倒くさそうに溜め息を吐き、それから鞄の中から手を抜こうと 力を入れた。しかし、まさにその瞬間、奇妙なことに気付いた。
ティナが、いるのだ。
の、頭の上に。
一体何が起こっているのかすぐに理解できず、はしばらく鞄の中に手を入れたまま固まっていた――よく神経を張り巡らせて見れば、 手首の辺りに、何かひんやりと冷たい細長いものが、5本………。
手…?
「………ッ!!」
は慌てて手を引っ張り、弾かれるように立ち上がって鞄から後ずさりした。いつの間にか息も荒く、米神には冷や汗がじんわり浮かんで いる。何かに掴まれていた手首が赤くはれ上がり、じんじんと僅かな痛みを残していた。
「ちゃん?どうかしたんさ?」
ラビがびっくりしてに尋ねてきたが、生憎今のにはそれに答えている余裕はなかった。まただ――また何か来る。
息を切らしながら辺りを注意深く見回していると、フッとシャンデリアの灯りが掻き消えた。
「「!?」」
今度はラビが跳ね 上がる番だった。部屋の中は真っ暗になり、しかも窓からは月の光すら差し込んでこない。まるで、闇の中に放り込まれたようだった。
「一体――何事さ……?」
「分からない」
は自分の手がブルブルと小刻みに震えているのを感じた。情けない。 そう思っていても、怖いものはどうしようもない。
ふと、足首に誰かの手が触れた気がした。びっくりしながら足をブンブン振り、 はすぐさまラビの方を睨みつけた。
「脅かさないでよ!」
「?何が?」
とぼけた返事が返ってきたので、 は怒って軽く床を踏み鳴らした。どうやらその拍子にラビの足を踏んづけてしまったらしく、隣で大きな何かが呻きながら飛び跳ねるの がわかった。
「ごめん……踏んだのはわざとじゃ――それより、えーっと、灯りをつけなきゃ…」
は背中の恍輝に 手を回し、そっと引き抜いて高く掲げた。目を閉じて、全神経を神剣に流し込む――。
イ ノ セ ン ス 発 動 ! !
神剣に埋め込まれたイノセンスの原石から、パッとまばゆい灯りが広がった。ラビがうっと呻いて目を抑えたが、はもう 突然の光に慣れっこだった。
「よかった――一応明るくはなったわね」
ホッと胸を撫で下ろし、は未だ光を放ち続ける 恍輝の切っ先をそっと床につけた。
しかし、安心していられるのもそこまでだった。
「――見ないことも時には幸せ」
恐怖に金切り声を上げる前に、はまず落ち着き払った声で言った――目の前に広がっていたのは、床一面から人間の生腕が 突き出している光景だったのだ。
「「 ギ ャ ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ! 」」
ラビの悲鳴との悲鳴が見事に重なった。二人とも慌てて振り返り、ドアノブを滅茶苦茶に捻りまくってとにかく外へ出よう と必死になった。ガチャリ、ドアが開いた音がする。
「お邪魔しましたァッ!!」
ラビは自分の部屋であることも忘れてそう 挨拶し、急いで廊下の方へなだれ込んだ。は後ろ手にドアをバタンと閉め鳴らし、そして二人とも抱き合うようにして、あちこち躓き ながらも必死で後ずさり。
「ななな、なんだったの…?」
「知らんさー…ヤッベ、マジでビビッた――」
うぷ、と嫌な音を 立てて、ラビは口元をそっと押さえた。も吐きたい気分だ。しかし、ラビが口から溶けかけたクロワッサンでも吐き出す前に、 ドアの方からけたたましい音が飛び出してきた。
バキバキッ!!――湿った木材を突き破って、生腕が飛び出してくる。 それだけならまだいい、しかし今はドアを突き破るのと同時に、ドアと床の隙間からドロドロの血がベチャベチャと音を立てて染み出してくる のだ。
「何かいい案ある?」 ラビが聞いた。
「逃げるわよ!!」 は叫んだ。
二人はズッコケながらもやっとの ことで立ち上がり、一目散に廊下を駆け出した。背後でバキッと一層大きな音が上がる――奴がドアを完全に突き破ったに違いない。顔を見る 前に逃げ出せてよかった、と二人は内心少しだけホッとした。
死怨
階段を駆け下り、廊下を走り、絶対に後ろを振り返らないようにしながら、二人は我武者羅に走り続けた。 何分走ったか分からない――行きも絶え絶えになってきた頃、とラビは正面の扉にぶち当たった。
行き止まりだ。
「あーーーーーーーーーーーー!!ラビどうしよう!?怖いよぉ!」
「えーい、泣くなぁ!!」
涙を滝のように流してすがりつく に向かって、ラビは困ったように叫んだ。任務で怖くてなくなんて久しぶりだ――魔女の時も、マテールの時もほとんど泣いていない。
―――あれ?
はふと奇妙なことに気付いた――そういえば、神田くんと一緒の時はここまで怖くなかったような…。
しかし、のその思考もすぐに止まった。二人がなんとかして扉を開こうと取っ手をガチャガチャやっているうちに、背後から 影が差したのだ――しかも、二人の足元は血の池になっているではないか。
「来たさ…!!」
ラビがボソリと呟いて、そして 二人はゆっくりと後ろを振り返った。そして絶句した。
長い血まみれの黒髪、青いアザだらけの白すぎる肌がむき出しになった腕、 ギョロギョロと中々向きを定めずに動き回る目玉、腕や足や首の骨はバキバキで、ありえない方向に曲がったり、肌を破って突き出したり。
そいつが、四つん這いになってこちらに向かってくるのだ。一段ずつ階段を踏みしめるように這って。
「開け…開けよ…!!」
ラビは目を大きく見開いたまま、すぐ扉の方に顔を戻した。扉をどんなに叩こうとしても、分厚い鉄の扉は動かない。
は まだ化け物に恐怖で釘付けになっていたが、それでもまだ正気を失っていなかった。
震える両手をラビと自分に向け、風もないのに赤毛が ブワッとなびかせ、白目まで黒く染まらせて。
「 シ ア フ ァ ネ イ ア 」
はそう唱えるや否や、ラビを力強く抱きしめて鉄の扉に向かって体当たりをかました。ぶつかる――ラビがそう叫ぼうとした 途端、二人の体はスーッと扉を通り抜けて、その向こうに躍り出た。
「え…?」
ラビの間抜けな声を響かせて、それから 二人は勢い余って地面に倒れこんだ。とりあえず、奴から逃れられたらしい。
「今、何が…?」
「…透明化呪文を使ったの…はぁ、 良かった助かった――」
弱々しい、けれどホッとしたような声ではラビに答えた。ラビはまだ現状を理解できていないようだが、 それでもホッとしたのかからパッと離れ、そして冷たい床に仰向けに寝転んだ。
「でも、ここは何処かしら…」
は手を突いて立ち上がると、薄暗いその部屋をキョロキョロと見渡してみた。恍輝をもう一度引き抜き、その刃から発せられる光で 辺りを照らす。金の装飾が施されたそこは、どの部屋よりも豪華で、そして暗い雰囲気をかもし出していた。
金で作られた巨大な 十字架が奥の壁に吊るされていて、そしてその前には一つの棺桶。そっと中を覗きこんでみると、そこには黒髪のミイラが寝かせられていた。 間違いない。は確信した。ここは――。
「霊廟…」
見つけた。町の中心にある霊廟とは、城の中に あったのだ。