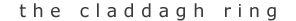の呟きを聞いたラビが、弾かれるように飛び上がった。
「でもおかしいわ。だって資料には『セシリー・クロフォードの霊廟 が』って書いてあったけど、わたしたちセシリーに会ってるもの」
「そのセシリーがアクマだったら?」
が首をかしげると、 ラビがすかさず言った。
「待って――まず状況を整理してみましょう」
まるで脳みそが捻じれたような感覚だ。は片手 を上げてラビの発言を制し、それから腕を組んで廟内を行き来し始めた。
「まず、資料によると。セシリー・クロフォードは父親によっ て殺された――彼女の遺体は町の中心に寝かされ、その後彼女は霊となり、彼に復讐をした、と。それでも気が収まらなかったのか、彼女は 夜な夜な町を徘徊し、無差別殺人を続けた」
「しかーし。俺らエクソシストが現れて、城の執事が口にしたのは、『セシリー姫は生きて いる』!そんでもって町の中心地に霊廟なんか置いてない、と!」
ラビが妙ちきりんな口調で、の言葉の後に続いた。
「そして、確かにセシリー・クロフォードは生きていたわ。執事はさておき、他の使用人におかしい点は見当たらない」
「でも、幽霊が出る と言う点に関しては資料の方が合ってるさ。長い黒髪で、肌は腐敗、服は血まみれ、で超不気味!」
「それと、町の中心地に霊廟がある、 っていうのもね――そりゃ、ちょっと遠回しだったけど…」
二人は、そっと棺おけの方に視線を向けた。そこに寝ているのは、わずかに 黒髪の残ったミイラ。
「オッケー。アレが化け物の正体だと思う人?」
「そんなバカなことないわ!だってミイラは死体が干から びてるだけで、腐敗はしてないもの…多分、だけど……」
が首を振って見せると、ラビは「だよなぁ…」と困り果てて髪の毛を 引っ掻き回した。
「ところでちゃん、昨日なんで気絶したんさ?」 と、ラビが聞く。
「昨日…?あぁ、アレ――さっき と同じよ。黒髪のオバケが追いかけてきたの」
は思い出すのも怖くなり、あまり考えないようにしながらなるべく簡潔に答えた。 ところが、はすぐに正直に言ったことを猛烈に後悔することになった――ラビの頬が、笑いたそうにピクピク震えているのだ。
「ひょっとして……それで怖くて気絶したんか?」
「うるさいわねっ、ホントに怖かったのよ!だって最上階にいたはずなのに、 窓の外からあの女が顔出したり、ドアを開けたら上からぶら下がってたり――」
言い訳がましく反論し始めると、昨日の記憶が鮮明に 甦ってくる。喋っているだけなのに、自分の顔がどんどん青くなっていくのが分かった。
「――――顔?」
突然、ラビの顔色が変わった。
「な、なに…?」
びっくりしてが聞き返すと、ラビは突然の肩を乱暴に掴み、 ブンブン揺すり始めた。ただでさえ気持ち悪いのに、胃液でも吐き出しそうだ。
「お前、顔見たんか!?見たんだよな!?覚えてるか!?」
「だ、だから一体なんなの…!?」
戸惑いながらももう一度聞き返す。
「覚えてんだろ!?ユウが読み上げた資料の内容! 目撃された不気味な女の特徴――」
ラビがあまりにも大きな声を出すので、締め切られた霊廟の中に迫力ある怒声が木霊した。しかし、 は耳を塞ごうとも、物凄い形相のラビから逃げ出そうともしなかった。
記憶を辿るのに、必死で。
―――そ うだわ、あの時神田くんはなんて言ってた…?
それから、毎晩のように怪奇事件が続いた。夜、街を 出歩いている人が次々と変死体で見つかったのである。そして一番奇妙なのが、事件前後には、遺体発見現場の傍で必ず、不審者の影が目撃 されているという事
不審者というのは、長い黒髪の不気味な女性…肌は腐敗し、服も血だらけ、そしてその顔は――
―――そうだ、思い出した。
そ し て そ の 顔 は 、 死 ん だ セ シ リ ー そ っ く り だ と 言 う
痩せこけた顔、腐って爛れた頬。もう少し太らせて、頬を引き締めて みたら?あの金髪女のセシリーそっくりじゃないか。
「…………どういう事…?」
闇の中に溶かして
はドスドスと床を踏み鳴らしながら、 ラビの前を早足で進んだ。階段を幾段も上り、廊下をくねくね曲がり続け、そしてやっと現れた玄関扉。
「オッケー、道は覚えた――そ の、ティナシャロンがね」
道順に関しては人任せだ。ティナシャロンが道順を記録したのを見届けてから、は言った。
「いい?これから町の図書館に行って、あるものを調べてきて欲しいの」
「承知!本なら大好きさー」
ラビはピーンと右手を上げて 了解のポーズをとる。
「事件について詳しく書いてある過去の新聞を全部読み漁って。その中で一番詳しいのを選んで書き写してくるこ と。バカじゃないんだから、どんなのが詳しい記事なのか見分けられるわよね?」
「適度な挿絵、犯人像や目撃者証言、事件現場の詳しい描 写、警察の調べがどこまで進んでるかとか?」
ラビがペラペラと早口でまくし立てた――見かけによらず頭はいいらしい。良かった!
「で、ちゃんはどうするんさ?」
ラビが尋ねてきた。は赤茶色の髪をザッと一つにまとめて結い、コートの ポケットからメガネを取り出して装着する。
「城の中を調べて、その後聞き込み調査に向かうわ。あなたは出来るだけ早く調査を済ませ て」
***
とりあえず、は延々と続く廊下を宛てもないままさまよい始めた。行き当たりバッタリで いい手がかりが得られるかどうかは不安だが、手元には何も情報がないのでは仕方がない。初めはみんな棚から牡丹餅、行き当たりバッタリから だ。
―――でもちょっと広すぎるかなぁ…
ちょっとどころではない。外から見ただけでも壮大なのに、中に入るとさらに巨大な のだから。
「あ、部屋みっけ」
ずっと肖像画のかかった廊下しかなかったのに、突然暗闇から金に輝くドアノブが。は 前後左右を確認してから、そっとドアの表面に手を当てた。
「 シ ア フ ァ ネ イ ア 」
スーッと手がすける。はそれを確認すると、一気にドアに体を押し付けた――ドアを体が通り抜けて、飛び出し た先はこじんまりとした部屋だ。
赤いじゅうたん、黄金のカーテン、しかしそれだけで、ベッドに天蓋はついていないし、壁に模様も刻まれ ていない。
「暗いわね…それになんか、寒い――」
鳥肌が立ちかけて、は急いでコートの上から腕をさすった。しかし、 寒気は収まらない。それどころか、何だか眠気まで襲ってきて、挙句には頭痛まで。
――風邪でもひいちゃったかしら…?
全くこんなときに、とは自分が情けなくてまた溜め息。とりあえずは、倒れる前にこの部屋を探らなきゃ。
ベッドの上には、 あちこち穴の開いたボロシーツが敷かれていて、その上の枕は埃をかぶっていた。使われていない部屋なのだろうか?ふと足元に視線を落とすと、 ブーツのヒールが綿埃を踏ん付けていた――やはり、使われていないのか。
不意に、ティナシャロンに髪の毛を引っ張られた。が 振り向くと、そこにあったのは妙に古びた木製のドア。不審に思って近寄ってみるが、今にも壊れそうなドアノブには、埃が積もっていなかった。
このドアだけ、つい最近使われたという事だろうか?
意を決し、ドアノブを捻ってみる。体をピッタリくっつけるようにしなが ら押し開けると、銀色にキラリと光る何かが顔を覗かせた。
薬棚だ。
「何これ……」
ズラリと綺麗に並べられ た大量の薬瓶。なんだか見ているだけでも気味が悪い。全部毒薬だったりしてとブルブル震えながらも、一番近くに置かれた円柱の瓶を手にとっ てみた。
ラベルに走り書きされた文字――毒物の一種の名称だ。
「え、ホントに毒…!?」
ビックリして、は 慌てて瓶を元通りにしまった。それから恐る恐る隣の瓶に視線を滑らせる…こちらも毒薬だ。
その下も、上も、後ろも、斜め隣りも、全部。 簡単な毒薬から、入手が困難とされる毒薬までズラリ。
突如、キチンと並べられた瓶の中で、あるものが目に留まった。
それはすぐ傍の棚にしまいこまれた、少し指紋で汚れたガラス瓶――無色透明の液体が半分以下にまで減っていて、その上銀に輝くキャップが 少し開きかけているのだ。
「これは…?」
そっと瓶に手を伸ばしかけ――。
ガ チ ャ ッ …
ドアが開く音。途端に、の心臓が跳ね上がった――まずい、誰か来る…!!は急いで息が聞こえないように 鼻と口を両手で多い、目立つ赤毛をコートをかぶってごまかして、棚の奥にもぐりこんだ。
間一髪、何者かの長い足がコツコツと足音 を立てながら二つ隣りの棚へ現れた。バレたらどうしよう――そんな不安のせいか、心臓がドキドキと早鐘を打っている。
そいつは棚の扉を 開け、瓶をカチャカチャ揺らし、それからポケットか何かにしまったのか、ゴソゴソと衣服をこする音がした。
コツコツ、足音が遠ざか って行く――この毒物満載の部屋に、一体誰が何の用だろう?は息を潜めたまま、慎重に棚の奥から顔を覗かせてみた。
長身の男――生憎頭は影に隠れてしまっているので、顔は分からない。せめて髪の色さえ分かれば…とは必死になって顔を動かし、 目を凝らした――と、その時。
男が振り返った。
ヤバ…!!慌てて身を隠す。見られたか?ドキドキと煩い心臓を手で押さえ、 は息を止めた。冷や汗が頬を伝う――数秒の間…そして。
ガチャッ――バタン。
ドアが、閉まった。 同時にドッと安心感があふれ出してきて、は脱力するように安堵の溜め息を吐いた。本当に心臓に悪い任務だと思った。
「あっ…そうだ、あいつ一体何を持っていったのかしら――」
ふと気付き、は駆け足で男が開いた棚を覗き込んだ――先ほどの 指紋だらけのガラス瓶がない。
「きっとあれを持って行ったんだわ――」
は小さく呟き、そして眉をひそめた。 あの長身の男、どうも見覚えがあるような気がしてならない。振りまくオーラ、歩き方。全てが、誰かに重なっているような気がする。
「神田くん…?まさか、ね――」
自分で呟いておきながら、すぐにそんなバカな、と笑って否定。それでも あの男、やはり神田そっくりの雰囲気をかもし出しているようでならない。まさか、神田が毒を持ち出したりするはずはないだろうが。
「えーっと、とにかく…怪しいのは長身の男、あんなに堂々と入ってきたんだから、城の人間よね――それから、セシリーか」
口の中で 転がすように、は只今の状況を復唱した。