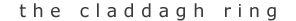「な、なんだ…?」
名もなきアクマが喚き声をあげた。気づけば、自分たちはアクマに取り囲 まれている。一体何体いるのか、数える気分にもならなかった。セシリーが、あの幽霊のようなおぞましくグロテスクな姿で立ち尽くし、こちら をボサッと見つめている。
「意味がわからないわ――あんた、死んでたんじゃなかったの?」
ひっくり返った素っ頓狂な声を聞 いて、は鼻先で笑い飛ばした。
「死んだ覚えなんかないわよ。少なくとも……わたしのイノセンスはね!わたしは死なないわ、 恍輝が壊れるまでは!」
自分で言っている意味がわかんない。頭、いかれちゃったのかも……?は自分の言動に僅かに首をか しげながら、恍輝を持ち直して構えた。そして強く地面を蹴り、神田とラビの前に立ちはだかる。
―――まずすべきことは。
はそっと背後を振り返り、地面に横たわるラビをそっと見据えた。だいぶ肌がどす黒くなっている――死んでしまう。はそっと彼の額に手を当てると、全神経を集中させた。
―――アクマの毒なら、イノセンスの力で相殺できるはず。
「 ク レ テ ィ オ 、 癒 せ 」
金色の光がの体から溢れ出し、触れている手からラビへと伝って彼を包み込んだ。まばゆい、目が眩むほどの光がラビの肌のどす黒さを吸い取って いく。
しばらくして、光が消えた。同時に、ラビの顔から苦痛が消えた。
はホッと安堵の息をついてから立ち上がると、恍輝を握り締め、ザッと敵陣に体を向けた。改めて見回すと、やっぱり数が多い。一体何匹 いるんだろう?……いや、知りたくもない。
「さーあ、いらっしゃいよ!どっからでも、誰からでもいいのよ!みんないっぺんだって構いや しないんですからね」
余裕の表情を取り繕って、フフンと笑う――もちろん、頭の中はいつも通り恐怖だらけ。けど、アクマはそれには 気づかず、怒りをあらわにして牙をむいた。殺気があふれ出してきて、ビリビリと恍輝の刃を震わせた。
背後から、アクマが飛び出 してきた。
恍輝をサッと上げて、アクマの攻撃を受け止める。そして振り向きざま奴さんの腹に蹴りを入れ、少し後ろへよろめいた 所に恍輝の刃先をつきたてた。そしてアクマが一匹、音を立てて爆発した。
何をするべきかはわかっていた。すべて、恍輝が脳に直接指 令してくれる。闘い方も、タイミングもすべて自分で見極めればいいと。わたしには六年間、元帥のところで磨いてもらった経験があるんだから!
ブーツが片方脱げてしまったのも気にせず、次々とアクマの攻撃をかわし、刃を振るった。体を地面に平行になるようにして跳び上がり、 飛んできた弾を腹スレスレできれいに避ける。そして恍輝から『三日月飛来刃』を飛ばして、遠くのアクマをいっぺんに五匹やっつけた。
アクマの数がどんどんゼロに近くなっていき、はついにセシリーの護衛を吹っ飛ばすことに成功した。これでセシリーとの一騎打ち、そ れに勝てばこの任務はお終いだ。あと少しだ、ガンバレ――心の中で、自分で自分に声援を送った。
セシリーはと向き合ったか と思えば、突然口をあけて、ドロッとしたものを吐き出した――異臭が鼻を突き、はハッとして口を覆った。
「毒……!!神田くん、ラビを連れて城を出て!!」
は背後に向かって金切り声を上げた。神田が起き上がり、妙にバタバタしながら遠ざかって 行く――逃げたに違いない。そしてチラッと背後を見やると、案の定、神田はラビを連れて逃げ出していた。
「に、逃がすものか!!」
セシリーが声を張り上げたが、は彼女の油断した隙をついて、恍輝で右腕を切り飛ばした。バシュッと血が飛び、セシリーの顔 に苦痛の表情が浮かび上がる。
「貴様……」
「逃がすものか、ってのよ!」
セシリーの言葉をそっくりそのままつき返すと、 今度は怒りの表情が飛んできた。セシリーが残っている方の手を振り上げる――肘の骨が逆に曲がり、小指の骨が変な方向から突き出していた。
はサッと横っ飛びに逃げて、ヤツの攻撃から逃れた。着地と同時に地面を蹴り、飛ぶようにセシリーへ向かっていく。セシリー がまた左腕を突き出してきたので、はその腐った手の平に刃の先をつきたてた。
ズブリと音を立て、恍輝がセシリーの手を貫通 する。そしてなお動きを止めない刃は、セシリーの顔まで届いて、頬をかすめた。僅かに血が飛び散り、はすぐさま恍輝を引き抜く。そ れと同時にその場で小さくジャンプし、右足をまっすぐ上方に突き出して顔にキックを入れると、着地するやいなや容赦なく恍輝を振るい、セシ リーの肩を切りつけた。
「ギャアアアア!!」
鋭い悲鳴を上げるセシリー。はさらに彼女の腹を蹴りつけてふっ飛ばし、セシリーを行き止まりの壁まで追いやった。そして恍輝をヒュッと振りまわし、彼女の首元 に切っ先を突き立てる。
「お休みの時間よ」
が言った。しかし、その切っ先がセシリーの首を切り落とすことはなかった。
の喉元に、ひんやりした鋭い感触が突きつけられたからだった。
―――これは、ナイフだ。
「セシリーさまからゆっくりと離れていただきましょう」
クリーグルだった。
虐殺パーティー
は喉元に突きつけられたまま、顎を少し上に上げながら、目玉だけを動かして背後を見た。クリーグルが口から一筋の血を流しながら、 の喉にナイフを突きつけている。
「聞こえなかったのですか?セシリーさまから離れなさいといっているのです」
ひんやりと冷たい切っ先が、の首の柔らかい皮膚を切り裂こうとしている。しかし、は何も言葉を返さなかった。心臓がまた騒ぎ始めている。
「もう一度言わせますか?セシリーさまから離れなさい」
「――ゴメン」
は悪びれた口調ではない言い方で謝ると、ゆっくりとセシリーから離れた。セシ リーが勝ち誇ったようにほくそ笑んでいる。
は一旦小さく息をつくと、クリーグルのナイフがゆっくり退けられたのを待ってから、腕を大振りに振り、セシリーの首を恍輝 で切り飛ばした――。
もの凄い爆発音、恍輝にこびり付いたどす黒い血――セシリーが、壊れた。
「セ……セシリー ?」
床に散らばった機械の残骸を見下ろし、クリーグルがポツリと零した。は息を切らしながら、ずっと彼を見下ろしてい た。クリーグルは地面に手をつき、残骸に向かって吠えていた。
「さぁ、今度はあなたの番よ、ブローカー。これからどうなるか分かって るでしょうね?」
淡々と言い放ちながら、恍輝の切っ先をクリーグルの頬に押し当てる。クリーグルはブローカー。ブローカーは犯罪者だ、 じっくりじっくり、自分の犯した罪の数々を反省しなければならない……。
しかし、今の彼にとってそんなことどうでもよかったのだろう。 怒りと憎しみで、脳が正常に作動していなかったのかもしれない。クリーグルは泣くのをやめて、恍輝の先をギロリと睨みつけた。
「お前が……壊した……!俺の、セシリーを……!!」
バーン!
そんな音がして、は背 中に激痛を感じた――いったい何が起こったのか、よく分からなかった。ただ、気づいたときには、自分が床に押し付けられていて、その上から、 クリーグルが、首を絞めていた。
「殺してやる!よく苦しむがいい!!」
クリーグルの手が首を締め付ける――。
――苦 しい……!!このまんまじゃ、死んじゃう……!!
酸素をなんとしてでも取り込もうと、は口を大きくパクパクさせたが、何の 足しにもならなかった。痛いのと苦しいのとがいっぺんに押し寄せてきて、また泣きたくなってきた。
わたしが早く行かないと、ラビが 死んじゃうかもしれないのに……。
でも、どうすればこいつから逃れられる?気絶でもさせるか?いや、この状態で気絶させるなんて無理だ、頭がぼやけて、手加減できな い…!
視界が狭くなっていくのを感じた。もがくことも出来なくなってきた。
―――死んじゃダメ、ダメなんだってば…!
自分自身に強くそう言い聞かせたとき、の 片手に握られていた恍輝が、ドクンと脈打った。
――殺シテシマエ――
そんな声が、 の脳の片隅で聞こえたような気がした。それに「え?」と聞き返す間もなく、は、自分の神経が全部、ダメになっていることに 気づいた。
手が、独りでに動く。
恍輝を握った、手が。
は恐怖に目を見開きたかったが、それす らもままならない状態だった。顔の筋肉が勝手に動いて、かつて一度も浮かべたことがないような、氷のように冷たい表情が独りでに浮かぶ……。
「あんた、終わりだよ」
の中から出てきた誰かが、そう言った。
そして、の視界いっぱいに、真 っ赤な鮮血が、飛び散った。
しばらく、は天井を見つめたまま動くことができなかった。次第に体中の痛みと背中に感じる 大理石の感触が戻ってきて、そして、は急いで恍輝を手放した。
ゆっくりと体を起こすと、自分の脇に、血まみれのクリーグル が目を見開いたまま死んでいた。心臓を、恍輝で一突きされている。噴き出した血は哀しいほど赤い色をして床をぬらしている。
―――わたし、殺した?
だんだん、恐怖が胸の中から沸き起こってくるのを感じた。何が起きたのかも、次第に理解できてきた。け れど、その事実が恐ろしかった。自分の体が独りでに動くのを信じられない思いで見つめていた、あの時ほど恐ろしかった。
―――わ たしが、人間を殺した……?