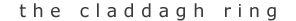「ねえ、ちょっと―――人居なさすぎじゃない?もしかして噂が本当で逃げ出したかな?」
「どこか適当に家を訪ねてみましょうか?」
がボソリと口を開くと、ゴズが神田に向かって聞いてきた。
ちょうどその時、神田の耳にかたり、という小さな音が聞こえてきた。神田は、パッと音源の方に目を向けた――それは、かろうじて 『雑貨店』と読める、ボロボロの看板をつけた二階建ての家で、年季の入った木造の家屋だった。
「どうかしたんですか?」
どうやら、ゴズとにはこのかすかな音が聞き取れなかったらしい。 神田は二人に目も向けず、無言でそこへ近づいた。古びた木のドアノブに手をかけ、ゆっくりと捻る。 ギギ、と木の軋む音が僅かに立った。
「すいませーん。誰かいますか?」
ゴズが、恐る恐る店内に声を響かせる。
本当に狭い店内だった。『雑貨店』の名の通り、色んなものがゴタゴタ並べられている。 古びた缶詰、釣竿、錆びた斧まで置かれていた。店の奥に弦の錆びたギターが置かれていて、が惹きつけられるかのように 近寄っていった。
店の奥のカウンターから、白髪頭の小柄な老人が現れた。 神田たちの姿に相当驚いたようで、ぽかんと口を開けたままこちらを見つめている。 その目は怯えと好奇心がごちゃごちゃに入り混じったような色をしていた。
「ここの店主か?」
「は、はい。そうです」
「黒の教団の者だ」
神田は自分の左胸のローズクロスをグッと指差した。 団員はヴァチカンの名において、あらゆる所への入場が許可されている。 こんな辺鄙な山奥の村に、そんな知識があるかはわからないが、身分を明らかにしておけば協力が得られるかもしれない。
「え、えーと、お偉い方のようで。ここへはどうして・・・・・・?」
「ここのところ、この村へ来た人間が戻ってこないという噂を聞いて調査に来たの。『帰らずの森』なんて呼ばれてるらしいわね」
「えっ、そうなんですか?」
がギターから目を離して答えると、店主はいささか驚いたようだった。 三人はチラッと顔を見合わせた。
「最近、村人以外の人間がここに来たりとかはしないの?」
「いいえ。私の知る限りではありません。尤もこんな何もない不便な村、時折村人の身内や友人が訪ねてくるだけで、来客自体少ない んですが」
「そう・・・。じゃあ、何か最近、村で――えーと、森でもいいけど――変わった事とかは?」
「いいえ。私はあまり外に出ていないので・・・」
店主は答えながら、ゆっくりとカウンターから出てきた。 杖をついており、どうやら足が悪いようでとても歩きづらそうだ。神田たちの視線に気がついて、老人は苦笑いをした。
「足を悪くしてしまってね。それで店の買い出しも他の村人に頼む始末ですよ」
どうやら、これ以上この老人から情報は得られないようだ。神田はじっと考えこんだ。 森で出くわしたアクマたちは、間違いなく村へ向かう人間を殺そうとしていた。しかし、何故だ?この村に何があると言うのだろう。 奴らの目的は一体何なんだ?
「一体どういうことなんでしょう・・・・・・?」
店主は深い溜め息を吐きながら言った。そんなの、こっちが聞きたいくらいだ。
「ところで、この村って他にも人がいますよね?」
「え、ええ。もちろんです」
「よかったー。村に入っても誰もいないし、人の気配もないから心配しちゃいましたよ」
ゴズの問いに、戸惑いながら店主が答える。ゴズはその答えに心からホッとしたようだった。 とりあえず、人はいるらしい。家の中に閉じこもっているのだろうか。
「ゴズ、。行くぞ。他の家も回ってみる」
神田がドアノブを捻ってドアを開けた途端、大粒の雨がバケツをひっくり返したように降ってきた。 いつの間にか、土砂降りになっていたらしい。雨のせいで、すぐそこの景色さえも見渡せないくらいだ。 さすがに躊躇して足を止めると、店主がおずおずと話しかけてきた。
「お客さん、もう夜だし、この雨だ。 明日にしたらどうです?お連れさんの顔色もよくないし―――」
店主の目が、チラリとゴズの方を見た。 神田もその視線を追い、ゴズの顔を覗き込んでみる。確かに、顔は痩せこけているし、隈までできている。 おそらく、襲われてから何も食べていないのだろう。
「お客さん方、今日はどちらかへお泊まりですか?」
「いいえ、まだ何も決めてないわ」
「この村、宿屋もないんですよ。もしよければウチの二階に泊まりませんか? 一部屋空いてますので」
「えーと・・・・・」
が、答えを伺うように神田を見た。 神田が少し考えてから小さく頷いて見せると、は愛想笑いを浮かべて言った。
「それじゃあ、お世話になるわ」
土砂降りの中
案内された部屋は、とても狭苦しい所だった。ベッドと小さなテーブルだけが置かれ、カーテンやシーツは淡い色の花柄だ。 おそらく、女性の部屋だったのだろう。
ドアがノックされて、こんもりした毛布を抱えたゴズが入ってきた。
「店主さんから毛布をもらってきましたー。神田さん、ベッドをどうぞ。どうせ俺、そのベッドに入らないんで」
神田はシングルベッドを見やった。自分でも窮屈そうなくらいの大きさだ。
「、お前ベッドで寝ろ」
「どうして?花柄シーツが気に食わないの?かわいいじゃない」
「バカかお前。俺でも窮屈なんだよ」
に茶化されて、神田は舌打ちしながら睨みつけた。しかし、はすでに窓際の床に、毛布を敷いて陣取っていた。
「あまり女の子っぽい柄だと、なんだか気分悪くなっちゃうの。神田くんベッドどうぞ。わたしはここで大丈夫。床も快適よ」
神田はまた舌打ちして、ドサリとベッドに腰を落とした。ゴズは椅子に腰掛けたが、かなり窮屈そうだ。 は、床に敷いた毛布の上に座り込んでいる。神田が鞘を外して壁に立てかけると、も真似して鞘を立てかけた。
一息つくと、ゴズが口を切って話し始める。
「とりあえず、人がいてよかったですね」
「まあな」
「本当に誰もいないのかと思っちゃいましたよ。 ずいぶん静かに暮らしているんですね、この村の人たちは」
「そうだな・・・アクマが入ってきた様子もない。 村に入らず、まだ森にいるのかもしれないな」
神田が静かに言うと、ゴズが深い溜め息をついた。
「でも、がっかりですね。命がけで調査に来たって言うのに、イノセンスはなさそうだ」
「『帰らずの森』の奇怪現象って、結局はイノセンスのせいじゃなくて、アクマが村へ向かう人を襲ったからよね?」
「おそらくな・・・アクマも村には入ってきていないようだし、イノセンス絡みではなさそうだが」
「魔女はどうなんでしょう?」
神田との表情が、同時に歪んだ。まだ魔女がどうとか言っているのか、こいつは。 睨みつければ、ゴズは肩をすくめる。
「どうします?イノセンスもないようですけど・・・・・・」
「そうねぇ。今回の任務は『失踪したファインダーたちを捜すこと』だけだったし、―――――――帰るの?」
「いや、アクマは複数いた。覚えてるだろ?まだ村やこの付近に潜んでいる可能性がある。全員倒してから帰還する」
例えイノセンスがないとしても、アクマを見過ごすことはできない。
「オッケー。じゃあ任務はイノセンスの調査から、アクマ退治に変更ね」
「あっ、それと、役に立たないかもしれませんが、 俺も一緒にいていいですか?」
の言葉に敏感に反応して、ゴズは言った。 その澄んだ青い瞳は、まっすぐに神田を見つめている。真剣な目つきだった。
――そうか、こいつにとっては弔い合戦になるのか。
仲間を目前で殺されたのだ、相当悔しいに違いない。 どっちにしろ、ゴズを一人で帰すわけにも行かないし、森にはまだアクマが潜んでいるかもしれない。
「かまわんが、足手まといにならないようにしろよ」
「わあ!ありがとうございます!」
ゴズは目をキラキラ輝かせて、まるで子供のように無邪気な声を上げた。イノセンスを扱えないゴズには、戦いには向いていないが、 聞き込み調査くらいはスムーズに行くだろう。
「じゃあ、明日は他の村人にも話を聞いて調査しましょう!」
「わかったから、もうちょっと声を小さくしろ!」
ゴズの喜びからくる大声に、神田は顔をしかめた。 誰がどこで聞いているか分からないのだ。屋内でも慎重に行動しなくては。
その時、一階から店主の声が聞こえてきた。
「夕食ができましたので、どうぞ」
「ありがとうございます!」
ゴズの顔が、また一段と輝いた。余程腹が減っていたのだろう。ゴズはドタドタと、物凄い音を立てて階段を駆け下りていく。 その様子は、まるで巨大な丸太が階段を転がり落ちていくようなものだった。
神田は溜め息をつき、ふと窓際のに視線をやった。まるで、ほほえましい光景を見るかのように、クスクス笑っている。
「ゴズさん、よっぽどお腹がすいてたのね。何だか子供みたいだわ」
「あんなデカい子供がいてたまるか」
神田は、事の成り行きにイマイチ付いてこれていない二人に、盛大な溜め息をついた。
「どうも、こんばんは」
神田とが階段を下りると、台所から女の子がひょっこりと顔を覗かせてきた。 自分より若干年下で、よりは上だろう。十六、七歳といったところか。金色に輝く髪を巻き毛にし、水色の綺麗な瞳をしている。 まるで西洋人形のような少女だ。
思わぬ美女の登場に、ゴズは固まったまま動かなくなってしまった。 こっちだって腹が減っているのに、でかい図体が邪魔で台所に入れない。神田が思い切り足を蹴ってやると、 ゴズは一体何を勘違いしたのだろう。少女におずおずと話しかけた。
「は、初めまして!いや、お美しいですね!お嬢さんですか?」
声は上ずっているし、表情はだらしない。見ている方が恥ずかしくなってきた。
「そうなんですよ。ソフィアといいます」
まるで警戒心のない笑顔だった。店主といい少女といい、 この村は暗い雰囲気に反して、人懐っこい人間が多いのかもしれない。
「お疲れでしょう。あまり大したものはないんですが、夕食を召し上がってください」
「はい!」
ゴズは嬉しそうに返事をして、台所に入っていった。神田も後を追う。こぢんまりとした部屋の中に、長テーブルがぽつりと置かれていた。 椅子はちょうど五つあって、ゴズは遠慮せずに素早く腰掛けた。
ふと、がいないことに気がついて、神田は後ろを振り返った。すると、はまだ階段の手すりに手を置いたままで、 目を見開いて突っ立っている。
「おい、どうした?」
神田が不審に思って声をかけると、はハッと我に帰って 神田の顔を見つめ返した。
「いいえ、なんでもないわ」
はにこりと微笑んで答えたが、 まるで説得力がなかった。神田は、自分を追い越して慌てて台所へ駆け込んでいくを、怪訝そうに見つめていた。