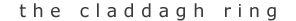「ええ」
「ソーセージもおいひいでふよ。むぐ。あっ、パンもおいひい!」
「食うか喋るかどっちかにしろ!」
口から盛大にパンくずが飛び散る。神田はたまりかねてゴズを叱りつけ、スープをすすった。少々薄味だが、確かにうまいな。
「あら、さんは召し上がらないの?―――もしかして気に入らなかった?」
ソフィアが、水色の瞳をに向けた。まだ、スープも一口くらいしか飲んでいない。 ただ、澄んだ緑色の瞳が憂鬱そうに曇り、ゴズとソフィアの間の空間をさまよっていた。
「いっ、いいえぇ!このスープなんか最高においしそうだわ!ただ、その・・・あまりにもおいしそうに食べるから、何ていうか――」
「あっ、ごめんなさい・・・下品でしたよね、食べながら喋るなんて!」
「ち、ちがうの!そうじゃないの! とにかく、わたしのことは全然気にしなくていいから!」
はそう言うと、慌ててパンを口に突っ込んだ。 あまり上品ではない食べ方が、アメリカ人を思わせる。そういえば、こいつ、性格の割には格好が派手だな。 神田はの耳に視線を滑らせた。隣に座っているため、左耳しか見えなかったのだが、それでも五箇所に派手な金銀のピアスが 付けてある。
一番大きなのは15センチくらいの長さの細い棒状のピアスで、少し身動きをとるたびに軽く揺れる。 銀色にキラキラと光り、そのシンプルなデザインがをさらに飾って見せていた。
「ソフィアさんはお店を手伝っているんですか?」
をじろじろと観察していた神田の耳に、 興味津々といったようなゴズの声が聞こえてきた。
「いいえ。私はミッテルバルトの町で針子の仕事をしているんです。 最近、ちょっとまとまったお休みをいただけたので、久しぶりに村に帰ってきたんです」
「町から・・・村へ来たですって?」
がボソリと呟いた。ソフィアの言葉を聞いた時、ギクリと肩が揺れたのを、神田は見逃していなかった。
―――妙だな。森を通ってきたのなら、アクマに襲われてしまうはずだが・・・。神田は意味深に、ゴズに目配せをした。 聞き込みはこいつに任せた方がいい。に任せれば、必要以上に怯えて、いつボロを出すか分からない。
「町から村へ来たんですか?それはいつ頃ですか?」
「えーと、十日前くらいかしら」
「その時は森の一本道を通って帰ってきたんですか?」
「ええ。それしかこの村に帰る道はありませんから」
「それで無事に来られたんですか?道中何事もなく?」
「ええ。・・・・・・・・・どうかしたんですか?」
ソフィアの表情が曇った。くいくい、と、右から袖を軽く引っ張られたので、神田はの方を向いた。
「何だ?」
「ねえ、それって・・・十日前まではアクマがいなかったって事よね?」
――まあ、そういう事になるだろう。 頷いてみせると、の表情が一段と暗くなった。
「ていうことは、その後に―――」
は何か言おうとして、突然口をつぐんだ。ソフィアの目が、チラリとこちらを向いたような気がした。
「村に帰ってきてどうですか?何か変わったことはありませんでしたか?」
「そうですね・・・・うーん。 特に変わったことはないですよ。ね、お父さん?」
突如、話が店主に振られる。 店主は瞬時ためらった様子を見せたが、おどおどと頷いて見せた。何だか、ソフィアが現れてから店主の様子が一変したような気がする。 そう思ったのは、神田だけではなかったようだ。
「そうですかー。まあ、平和そうな村ですもんね。 実は『魔女の村』って噂を聞いてたもんで、ちょっとビクビクしていたんですよ〜」
ガシャンという音を立てて、花柄のカップが床に叩きつけられた。中身の液体がそこら中に散らばり、破片があちこちに飛んでいる。 一方、カップを取り落とした張本人の店主の顔は真っ青になり、唇がガタガタと震えていた。
「どうしたの?お父さん」
ソフィアが心配そうに声をかけると、店主は慌てて目をそらして立ち上がった。ガタンと木製の椅子が後ろへ下がった。
「すまない。ちょっと足が痛んでね。―――先に休ませてもらうよ」
店主は、足をズルズル引きずりながら 台所を出て行った。ソフィアはそれを心配げに見送った後、疲れたように溜め息を吐いた。
「魔女ですか・・・・・・。 そんな大昔の伝説をまだもっともらしく話す老人とか多いんですよね。以前、偏屈なおばあさんが村はずれの小屋に住んでいましたが、 普通の人でしたよ」
言った直後、ソフィアが盛大にむせ込んだ。一体何事かと思えば、彼女の視線の先で、 ゴズが一心にスープ皿を舐めている。
――一体何を考えているんだこいつは。教団の権威を地に落とすつもりか。
神田が、氷よりも冷たい視線を向けていると、がおどおどしながら手を伸ばして、ゴズの太い腕を突っついた。 ゴズは、ピタリと動きを止めて、ゆっくりと顔を上げる。
「あっ・・・・・・すいません、スープがおいしすぎて思わず――」
「いいんですよ、お気になさらないで下さいな。量が少なすぎましたよね、ごめんなさい」
思わぬところで褒め言葉が飛び出してきたからか、はたまた心が本当に広いのか、ソフィアはにっこり笑いながら首を振った。
「い、いえ!そんなことありません!大丈夫です・・・」
そう言いながら、ゴズの言葉に一片も真実がないのは、 誰の目にも明らかだった。呆れと恥ずかしさが入り混じったような、重い感情が頭の中で渦をまき、 神田は体にドッと疲れが押し寄せてくるのを感じた。
「ちょっと待っててくださいね」
ソフィアが立ち上がり、台所を駆け出していった。 ガサガサと何かをあさる音がし、しばらくして戻ってきた彼女の手には、白い袋。
「ゼリービーンズです。大人の男性に差し上げるようなものじゃないんですけど」
「大丈夫だ。図体はでかいが、 こいつ精神年齢は低―――――――」
ガッという凄まじい音がして、の長い足が横から神田の向こう脛を打った。 涙が出るくらいの痛みが襲い掛かり、神田の言葉は途中で遮られた。顔に似合わず、どうやら凄く腹黒いようだ。
「ありがとうございます!お菓子、大好きなんですよ〜」
「もっとお出しできたらいいんですけど、食糧にも限りがあって―――貧乏な村なので」
と神田の、テーブル下での出来事には何も気付かなかったらしく、ソフィアが穏やかに言った。
「いえ、そんな!突然訪ねた上に、泊めてもらって食事までいただいて。じゃあ俺たちは二階で休ませてもらいますね。 あ、もしかしてあの部屋はソフィアさんの部屋ですか?なんなら俺たちは廊下でも構わないので」
「え?いえ違います。私の部屋は向かいなので、お気になさらないで」
――それでは、あの部屋は店主の妻のものだろうか。そういえば、この家、二人以外に家族はいないのだろうか?
「あの、失礼ですがお母様は?」
ゴズがおずおずと尋ねた。ソフィアは目を伏せ、その目に悲痛の色を浮かべた。 表情を見れば、聞かなくても分かる――おそらく、既に死んでいるのだろう。
「・・・・・・母は亡くなりました」
「そうですか。失礼しました」
ゴズは慌てて頭を下げた。
「いえ、もう三年も前のことなので」
「ほんとにすいません・・・じゃ、俺たちは二階で休ませてもらいます」
ゴズはもう一度頭を下げて、神田に目配せをした。神田はまだパンを口に突っ込んでいるを突き、椅子から立ち上がった。
ディナー
カタン、と音がして、は目を開けた。視界がしばらくぼやけてよく見えなかったが、次第にはっきりしてくる。 体を起こしてみると、床に寝ていたはずのゴズの姿が見当たらなかった。
団服をたたんで枕にしていたのだが、その近くに添えておいた金色の懐中時計が月の光を受けて光っている。 それを手にとって時刻を確認する。まだ夜中だった。開け放たれたドアから、冷たい風が吹き込んでくる。
「神田くん!!」
声がまだ寝ぼけていた。自分に背を向け、ベッドで寝息を立てている神田に声をかけてみるものの、 反応はない。はかけていた毛布をはいで団服を引っつかみ、立ち上がった。 ノースリーブのシャツを二枚重ね着し、下はスカートのままだ。相当寒い。
「神田くんってば」
もう一度声をかけながら、今度はベッドに駆け寄ってみた。穏やかな、端正な寝顔が間近にあって、ドキドキしてしまう。 なんだか、起こすのが勿体無いような気がして、はそっと自分のかけていた毛布を神田にかぶせてやった。 神田は少しもぞもぞと動いたが、やはり起きなかった。
「行くわよ、ティナシャロン」
団服をバサッと大きく振りながら羽織ると、どこからか飛び出した純白のゴーレムが、の肩に止まった。
***
なるべく床を軋ませないようにしながら、はなんとか、誰も起こさず家の外へ出ることに成功した。 パタパタと羽音を静かに立てながら、ティナシャロンが高く舞い上がる。
「あら・・・・・・?」
ふと、厚底のブーツに何かが触れた。かがんでそれを拾い上げ、月の光にかざしてみる。鮮やかな黄緑色をした、独特の形。
「これって、ゼリービーンズ?」
確か、これは先程ゴズがソフィアからもらったものだ。 ひょっとしたら、後から追ってこれるようにゴズがまいて行ったのかもしれない。だとすれば、これをたどった先に・・・・。
は、ゼリービーンズを追って駆け出した。しばらく走った後、村はずれに小さな明かりのついた小屋が見えてきた。 近づくにつれ、鼻を突くような臭いが広がってくる。何の臭いだろう・・・?以前、嗅いだことのあるような臭いだ。それも、何度も。
「まさか、これって・・・・・・・・・・・・・・・」
何の臭いだか思い出した。そして、気味が悪くなった。 もしこの考えがあっているとすれば・・・わたしたちは、とんでもない村へ足を踏み入れてしまったことになる。 しかし、これは間違いない。立場上、何度もであった場面に充満した、あの―――。
「死体の、腐敗した臭い・・・?それも・・・大量の―――」
バサッと、ティナシャロンが大きく羽ばたいた。 まるで、何かを知らせようとしたかのように。直後、鈍い音が鳴り、後頭部に激痛が走った。 そこで、の意識は途切れた。