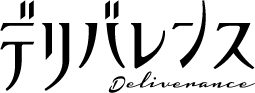
空座町の幽霊屋敷といえば、町の誰もがよく知る心霊スポットだった。住宅地の外れにある、とびきり古い木造の日本家屋だ。庭は荒れ放題、外壁は絡まった蔦にほとんど覆い隠され、ろくな手入れもなく長い間雨ざらしになっていた屋根は、ひどく傷んで崩れかかっている。汚れた窓ガラスは昼も夜も真っ黒で、中の様子なんてちっとも見えやしない。
しかし、全く人の気配がないというわけではなかった。夜になると、近所の若者が仲間を連れ立って肝試しにやってくることがある。亡霊や怪奇現象との遭遇に胸を躍らせ、懐中電灯片手に侵入を試みるのである。そして、風に舞うビニール袋や、人の形をした幻覚に尾ひれがついて、面白おかしく吹聴される。空飛ぶ生首、彷徨う女性、青い鬼火に、鳴り止まないうめき声……。噂は人を呼び、人は更なる都市伝説を作り上げる。そうして、いつしか家は『空座町の幽霊屋敷』と呼ばれるようになっていた。
ところが、ある日を境に、若者たちは肝試しを断念せざるをえなくなった。屋敷に、ある家族が引っ越してきたのだ。
伸びきった草木は整えられ、壁の蔦は焼き払われ、窓ガラスも全て取り替えられた。門には真新しい表札が貼られ、夜になると窓に明かりが点るようになった。傷んだ箇所をつくろっても、屋敷は相変わらず汚らしかったが、もう誰も「幽霊が出る」とは言わなくなった。
近所の人々は、『幽霊屋敷』の変化を大いに喜んだ。住宅地に空き家が放置されているのは防犯上好ましくないし、薄気味悪い窓の向こうの暗闇や、悪臭を放つ庭、何より、夜な夜な若者たちが騒ぎ立て、ごみを散らかしていくことにうんざりしていたからだ。
「これでようやく夜ものんびり寝れるようになるわね…」
次々と家具が運び込まれていくのを、人垣はホッとした様子で眺めていた。
宝生玲乃は、しかし、この展開がいたく気に食わなかった。
せっかく東京に引っ越してきたというのに、こんな汚らしいボロ屋敷に住まうはめになるなんて、どうあっても許しがたかった。廊下は歩くたびにギシギシ軋むし、天井はあちこちに雨漏りの痕が染みついている。窓を開けても電気をつけても薄暗くて、おしゃれなインテリアは似合いそうにない。
(どうせなら、新築の家に引っ越したかった…)
玲乃は自分の部屋に段ボールを運びながら、人知れず溜め息をついた。
「玲乃ちゃ〜ん」
着替えを箪笥に移し替えていると、階下からのんびりと自分を呼ぶ声がした。
「なに〜?」
「ご近所さんに挨拶回りしにいくんだけど、一緒に行きましょうよ」
「別にいい」
玲乃は即座に断った。休憩する口実があるのは有り難かったが、「近所に挨拶」というのがあまり気乗りしなかった。
「そんなこと言わないの!これからしばらくお世話になるんだから」
「だって、めんどくさい……」
「めんどくさいじゃありません!」
母親がドカンと火を噴き、どすんどすんと荒い足取りで部屋に上がってきた。その形相は鬼のようで、今にも角が生えてきそうだと玲乃は思った。「さぁ来るのよ!」と腕を引っ張る母親がうざったくて、あれやこれやと言い訳をつけて断ろうとしたが、結局は強制的に連れ出されてしまった。
挨拶回りは予想していた以上にしんどかった。単に菓子折りを配って会釈するだけかと思ったら、母親はご丁寧にも15分以上も立ち話して回った。女同士の話は気が遠くなるほど長い。年齢を重ねればさらに長くなる。その間、玲乃は白い外壁を羨んだり、前髪の枝毛を裂いたり、時々話題にされたら照れ笑いしてみせたり、それくらいしかすることがなかった。
「あらあら、日が暮れてきたわね」
時計の短針が下を向く時間帯になっていた。空は赤く色づき、町の向こうから夜が僅かに滲み始めている。
「あそこのお店にちょっと顔出したら、そろそろおうちに帰りましょうね」
まだあるのか、と玲乃は呆れて空を目で仰いだ。
母親が最後に訪ねたのは、民家に挟まれて建つ小さな駄菓子屋だった。『浦原商店』とロゴの入った頭でっかちな看板を掲げている。ひょいと中を覗いてみると、店内には誰もいなかった。その代わり、狭苦しい空間は見たこともないお菓子で溢れ返っていた。あんずあめ、酢昆布、ラムネ、チョコバット、それに、どうやって食べるのかも分からない、変わった形のお菓子……玲乃は『宇宙玉』と書かれたパッケージに手を伸ばしかけたが、触れた途端に何かよからぬことが起きそうな予感がして、思わず手を引っ込めた。
「すみませーん、どなたかいらっしゃいませんか?」
玲乃がしげしげと商品棚を眺め回していると、後ろで母親が店員を呼んだ。
「はいはーい。ただいま」
店の奥から、間の抜けた声が帰ってきた。
ほどなくして、ひょろりとした長身の男が姿を現した。深緑色の甚平の上に羽織を着て、カランカランと下駄を鳴らしている。緑と白のストライプが入った帽子を目深にかぶっているので、顔はあまりよく分からない。つばの下から、好き勝手に跳ねる明るい色の髪の毛が飛び出している。
「いらっしゃいませー」
男の口元がへらりと笑った。なんだかうさんくさそうな男だ。玲乃は一歩下がった。
「何かお買い上げで?」
「あ、いえ、今日はご挨拶にと思いまして……これ、つまらないものですが良かったらどうぞ」
母親が鞄から菓子折りを取り出すと、男は扇子を広げて「挨拶?」と聞き返した。
「今度裏の家に引っ越してきた宝生と申します。こっちは私の娘です」
男はちらりと玲乃に顔を向け、「あ、どうも」と頭を下げた。玲乃は僅かに顔を動かしてそれに応じた。
「アタシはこの店で店長やってる浦原喜助といいます。あ、裏の…ってことは、例の『幽霊屋敷』に越してきた方っスか?イヤー、あそこに住もうだなんてどんな方かと思ったら、こんなキレイな奥さんだったとは!それに、かわいらしい娘さんっスねぇ!お名前なんていうんスか?」
「れ、玲乃です…」
玲乃は慌ててお辞儀した。喉の奥が引きつって上手く声が出せなかった。浦原が「アハハ!照れ屋サンなんスね」と声を上げて笑ったので、玲乃はますます恥ずかしくなって縮こまった。
「あっ、そうだ。ウチばっかりいただくのもなんなので、よかったらお礼にコレでも持って帰ってくださいな!」
浦原はカランカランと下駄を引きずるようにして棚に向かい、そこから適当にお菓子の袋を一つ取り上げて、「ハイ」と玲乃に手渡した。玲乃は礼を言おうと口を開いたが、袋の中身を見たとたん、頭の中が空っぽになってしまった。それは、色とりどりのゼリービーンズの詰め合わせだった。
「おや?お嫌いでした?」
浦原は口元を扇子で隠して不安そうに聞いた。玲乃は急いで首を振った。
「いえ…!あの……ちょっと懐かしくって…」
「あー…最近の子はこういうもの食べないっスからねぇ〜」
お陰で売上げもイマイチで…とぼやく浦原に適当な相槌を返し、玲乃と母親はこっそり目を見交わした。玲乃の言わんとしていることは、母親にははっきりと伝わっていた。
「じゃあそろそろ失礼しますね」
母親は玲乃の頭にポンと手を置いて、浦原に頭を下げた。浦原は扇子をヒラヒラさせながら挨拶を返し、玲乃に向かって「いつでも遊びに来てくださいね」と笑いかけた。
宝生親子が帰った後、下駄を脱いで奥へ引っ込んだ浦原の前に、がたいのいい大男がぬっと姿を現した。四角いメガネと太い眉、豊かな口髭が気難しそうな印象を醸し出しているが、てっぺんの禿げ上がった頭から垂れる細かな三つ編みがそれを愉快にぶち壊している。
「店長、お客さんで?」
「ん?いや、ちょっとね」
浦原は肩に叩きつけるようにして扇子を閉じ、男——握菱テッサイの隣を通り過ぎた。
「あの『幽霊屋敷』に新しく越してきた親子が挨拶に来てね……」
「幽霊屋敷に…?まさか——」
テッサイは顔をこわばらせたが、浦原は緩やかに首を振った。
「ところが、それが驚くほど普通の親子なんスよ。とんだ“物好き”がいたもんだ…」
普通の親子。
誰もが宝生親子に対して似たような感想を抱いたはずだ。幸せに包まれた、ごく普通の家庭の母と娘。
宝生玲乃 / 15歳
「——けど、まあ…しばらくしたら泣きながら出てくことになるでしょうねぇ……あの親子も」
髪の色 / 飴色
瞳の色 / ブラウン
職業 / 高校生
幽霊屋敷に着くと、親子は玄関で靴を脱ぎ、それぞれ別々の方向に歩き出した。母親は調理場に、玲乃は荷物整理の続きをするため、二階の子供部屋に。
特技 /
玲乃は、段ボールだらけの混沌とした部屋を前に立ち尽くした。箪笥の引き出しからたたみかけの衣類が中途半端にはみ出していて、その側にまだ開けてすらいない箱が山積みになっている。まともに片付けていたら気が遠くなる。きっと夜が明けてしまうだろう。
玲乃は袖から紫檀の杖を取り出し、段ボールの山に向かって一振りした。
次の瞬間、箱の中身が一斉に空中へ躍り出た。雑貨は勉強机の引き出しの中へ、本は本棚へ飛んでいき、衣類はひとりでに畳まれて箪笥の中に収まった。玲乃がもう一度杖を振ると、今度は空になった段ボールがパタパタと順序よく解体され、部屋の隅に積み上げられた。
特技 / 魔法が使える
宝生親子は、皆の知らないところで、確かに“異質”だった。
気づかない浦原さんもいいかな〜と。
真実が発覚した時にびっくりすればいい。