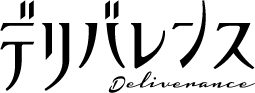
4月——。
玲乃は「空座第一高校」に入学する。
空座一高は市内の公立高校で、玲乃が唯一入学試験を合格できたところだった。玲乃も母親も隣町の私立「鳴木女学院」に入学することを望んでいたが、鳴女の入学試験は問題用紙を裏返した瞬間目玉が飛び出すほど難しく、あっさりすぎるほどすとんと落っこちた。
「落ちたものは仕方ないわよ。それに、空座一高の方が近くて通いやすいじゃない」
母親はそう言って慰めてくれたが、玲乃のショックは拭いきれなかった。偏差値が高いとは聞いていたが、他の学校の試験とあそこまで差があるとは思っていなかった。
唯一慰めになったことといえば、空座一高の制服がかわいかったことだ。グレーを基調としたブレザーで、胸元の大きなリボンと、ポケットに引かれたラインの鮮やかな赤がアクセントになっている。
「あら、似合うじゃない」
入学式当日、さっそく制服に袖を通した娘を見て、母親が褒めた。
「鳴女の制服よりもいいんじゃないの?」
「強いて言うなら、黒の方がよかった」
鳴女の品がある黒いジャケットを思い出しながら、玲乃は悲しみに満ちた声で言った。
「過ぎたことグチグチ言わないの。ほら、朝ご飯できてるわよ」
母親に言われてテーブルにつくと、調理場からパンケーキの載った皿と、ナイフ、フォーク、そしてバターケースとはちみつ壷が飛んできて、玲乃の前に整列した。玲乃はバターを切り分けてホカホカのパンケーキに塗り、その上からはちみつを好きなだけ垂らした。
「はちみつかけすぎちゃダメよ——今、何時?」
母親が慌ただしく調理場から飛び出してきた。玲乃はパンケーキを口に運びながら壁掛け時計に目を走らせた。
「……ママ、ダイニングの時計、またイカれてる」
玲乃はうんざりして言った。一分に一目盛りしか進まないはずの長針が、ぐるぐると暴走している。
「あら、また?」母親が廊下から忙しそうに顔を出した。「帰ったら直すわ。それより、パフスケインとフィージーに餌をあげておいてちょうだい。お母さん、そこまでやってる時間ないの」
「えーっ」玲乃が呻いた。
「『えー』じゃないでしょう。あんたがちゃんと自分で世話するっていうから飼ってもいいって言ったのよ」
「私だって時間ないのに……」
玲乃の口答えをかき消すように、二階からつんざくような悲鳴が聞こえた。
「もう!こんな時に……」
玲乃の席から、母親が杖を抜いて二階へすっ飛んでいくのが見えた。
「『屋根裏お化け』だわ——ああ、嫌だ!こいつ、本棚をめちゃくちゃにしてる!あぁーっ……」
バサバサッと本の山が崩れ落ちたような音の後、母親が『屋根裏お化け』に向かって口汚く罵る声が聞こえた。バーン!バーン!と呪いが炸裂して、家が激しく揺さぶられた。しばらくすると、『屋根裏お化け』のけたたましい悲鳴が壁の裏を通ってどこかへ姿をくらました。ようやく静かになったと一息つくも、玲乃がはちみつをおかわりしようとした途端、ダイニングの床下に強い衝撃が走り、玲乃の椅子がぽんと飛び上がった。
「ママ!床下!」
「知らない!自分でどうにかしてちょうだい!」
玲乃は袖から杖を引っぱり出し、激しく突き上げる床に向けて叫んだ。
「 ステューピファイ! 」
赤い閃光が床を貫通して消え、一秒後、「うっ」という呻き声を最後に床下が静かになった。
「やったの?」
髪の乱れた母親が、信じられないという顔でダイニングに飛び込んできた。玲乃は袖の中に杖をしまい込みながら、得意げに笑った。
「餌やりはママがやってね」
こんなことで驚いていられないくらい、「幽霊屋敷」にはいろんなものが棲み着いていた。荒廃するまで空き家状態が続いたのも、『若者が選ぶ心霊スポット100選』に載ったからという理由だけではないだろう。『屋根裏お化け』は真夜中でも水道管を叩いたり悲鳴を上げたりするし、箪笥に棲み着いている『まね妖怪』は隙あらば血みどろのバンシーに変身して金切り声を上げた。家全体に「防音呪文」がかけられているため、これらの騒音が外に漏れることはなかっただろうけど、これではどうにも買い手がつかないはずだ。
「きっと、前の家主は魔法族だったのね」
髪型を整えながら、母親が溜め息をついた。
「マグルだったら堪えられないわ、こんなお化け屋敷」
それから30分もしないうちに、玲乃は家を出なければならない時間になった。母親は「急ぐ」と言っていた割に、まだ服が決まらず、姿見の前に張りついていた。
「玲乃ちゃん、こっちとこっち、どっちがマグルっぽく見えると思う?」
母親は紫と緑色のストライプ柄のスーツと、金色のワンピースを手に持っていた。
「どっちも」
玲乃はありえないと首を振った。
「やっぱり真っ黒のスーツがいいのかしら?でもあれは地味で好きになれないのよね——あ・玲乃ちゃん、杖は持っていきなさいよ。何があっても肌身離さず持っていること!だけどマグルの前で呪文を使っちゃダメですからね……」
「分かってるったら」
返事もおざなりに、玲乃は玄関の扉を押し開けて外へ出た。
「いってきまーす」
新生活を始めるにふさわしい、とても清々しい天気だった。眩い朝の光がチカッと目を突く。玲乃は突き抜けるような青空を見上げて、ぐっと伸びをした。
空座一高に着いた玲乃は、そびえ立つコンクリートの校舎を見上げて、気合いを込めて頷いた。今から玲乃はこの学校の生徒だ。ちょっと妙ちきりんな木の枝を隠し持ってはいるが、ただのマグルの女子高生に過ぎない。玲乃は一度自分の姿を見下ろして、何もおかしなところはないか最終確認した。大丈夫。靴下は地味な黒を選んで履いてきたし、紫と緑のストライプも、きんきらきんもない。オーケー、いける。
「入学おめでとう!」
校門の前には簡易テントが設置されていて、生徒会の上級生が待機していた。新入生はそこでプリントと手帳をもらい、最初にクラス分けを見に行くよう案内された。
校庭に出ると、大きな掲示板が何枚か立てられていた。向かって左から3番目の掲示板——1年3組の女子の中に、「宝生玲乃」の名前があった。担任は越智美諭、女の先生のようだ。玲乃は鞄の中から手帳を引っぱり出すと、クラスと出席番号を書き留め、さっそく教室に向かった。
(3組…3組……あった!)
1年3組の教室に着くと、クラスの子たちがガヤガヤと楽しそうに盛り上がっていた。今日からこの人たちがクラスメイトになるのか——玲乃はどぎまぎしながら教室を見渡した。みんな玲乃と同じ年齢のはずなのに、一つか二つくらい大人びて見えた。明るい髪色と派手な髪型、短いスカート、香水の匂い。教室の真ん中ではスタイルのいい女の子達がキャーキャー騒いでいて、男の子達が気を引きたそうにチラチラ窺っている。
「おい、通してくんねーか」
耳元で急に低い声がして、玲乃は飛び上がった。教室の入口に突っ立ってぼんやりしていたせいで、通行の邪魔になっていたらしい。謝ろうと急いで振り返ったが、背後に立っていた男の子を見て玲乃は泣き出したくなった。鮮やかなオレンジ色の髪、さっそく着崩された制服。玲乃より20センチ以上高いところから睨んでくる、不機嫌そうな目つき。その上あちこち擦り傷だらけで、全身が「さっきまでケンカしてました」と正直に語っていた。
——ヤンキーさんだ!
「?どうしたんだよ」
顔を見上げたっきりパッタリ動かなくなってしまった玲乃に、『ヤンキーさん』は眉間の皺を深めてみせた。
——ひい!ヤンキーさんは私がどかないのでお怒りである!!
「あ、ごごご…ごめんなさい…!」
咄嗟に謝罪したはいいが、涙声になってしまった。
「すすすすぐどきます!ごめんなさい!」
「いや、別にいーけどよ…」
面食らったような『ヤンキーさん』を置いて、玲乃は教室の中へ駆け込んだ。
今日が初めての登校日だというのに、新入生の間では既に仲良しグループができ上がっていて、玲乃だけがひとりぼっちだった。みんないつの間に仲良くなるんだろう。玲乃は不思議でたまらなかった。そして、心の中に焦りが芽生えた。このままでは、ずーっとひとりぼっちの寂しい奴になってしまう。そんなみじめな思いをするのは絶対嫌だ。前の学校にいたときは、どうやって友達を作ったんだったか。
(どーしよう……居場所がない…)
手持ち無沙汰でロッカーの前をうろうろしていると、目の前をボーイッシュな女の子が颯爽と通り過ぎた。
「織姫ー、あんた席どのへんだった?」
その一言で思いつく。
(あっ、席!)
時間的にはまだちょっと早いが、もう座席についてしまおう。そして、隣の席の子に話しかけてみたらいいんだ。
座席表は黒板の真ん中に張り出されていた。玲乃の席は教室の真ん中あたりだった。隣は「石田雨竜」——男の子の名前だ。玲乃は一瞬ひやりとしたが、実際の席についてみてホッとした。石田はさっきの『ヤンキーさん』とは正反対の男の子だった。まじめそうな顔にメガネをかけて、つんと正面を向いて座っている。
——優等生さんだ。
男の子だけど、この人となら、仲良くなれるかもしれない。
「あ、あの……」
恐る恐る声をかけてみたが、無視された。
「あの!」
気づいていないのだと思い、もう一度、今度は少し声を振り絞って呼びかける。
「……なんだい」
返された言葉はとても冷たかった。
「あ、いや……その…」
人選ミスだ。
四角いメガネの奥に光った細い目を見て、玲乃は即座に理解した。だが、このまま「なんでもない」と打ち切ってしまうのも気が引けて、俯きながらも苦し紛れに言葉を繋げた。
「私、宝生玲乃…です。隣、よろしくね…」
「………」
おや、返事がない。顔ごと持ち上げるほど勇気が出ず、恐る恐る上目遣いに顔色を窺った。石田は何の表情もなかった。
「………」
それどころか、視線に突き刺すような鋭さを孕んでいる。今の短い文章のいったいどこに、彼をそんなに不機嫌にさせる単語が含まれていたんだろうかと、玲乃は不安になって口を覆った。ひょっとして声をかけたこと自体がまずかったのだろうか。大事な考え事をしていたのかもしれない……。
「あ・いや——」
石田がふいに声を上げた。
「——ごめん。声、かけられるなんて思ってなかったから」そう言ってから、ほとんど聞き取れないくらい小さな声で、「よろしく」と続けた。
「う、うん!よろしく…!」
言葉を返しながら、玲乃は心臓がドキドキ動き出すのを感じていた。
(よかった……できた、友達…!)
いきなり“一護と友達☆”はハードル高すぎた。
黒崎さんも石田さんも単に目つきが悪いだけです。