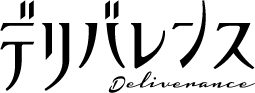
高校生活の幕開けから何週間か過ぎたある日のこと、玲乃は『いつも』の通学路に『いつも』じゃないものを見つけて立ち止まった。
『松田屋』——箒磨きセット値下げ中——
「箒……」
ちらりと周囲に目を配る。時計屋と眼鏡屋に挟まれて窮屈そうに佇むその店は、昨日までずっと古びたシャッターを下ろしていたように記憶している。人々は誰も興味を引かれないのか、おかしな宣伝文句には目もくれずに通り過ぎていく。
「……磨き…」
わざわざ箒なんかを磨く人種を、玲乃は一つしか知らない。玲乃はもう一度あたりを見回し、誰の目もこちらに向いていないことを確かめると、思い切って暖簾をくぐった。
「お邪魔しまーす」
首を下げて声をかけてみる。返答はない。というか、人の気配もなかった。店内は外から見たよりもやや広く、なんだかきついスパイスみたいなにおいがした。ぎっしり並んだ商品棚にはごちゃっとものが並び、ところどころで光ったり跳ねたり奇声を上げたりしていた。
『悪戯用品——イギリス直輸入、店内で試さないこと——』
一番奥の商品棚で何かが激しい爆音を上げながら刺激臭のする煙を噴き出している。玲乃はその棚には近づかないようにしながら、じっくりと色んな売り物を眺めた。羽根ペン用のインクが切れないインク壷、スペロテープに、こすると消えている文字を出現させる『現れゴム』——馴染み深い品もあれば、初めて見るおかしなものもある。しかし、玲乃にはその全部が懐かしくてたまらなかった。
文房具の棚をじっくり歩いて見ていると、不意に低い唸り声が急速に近づいてくるのが聞こえた。慌ててしゃがみ込むと、玲乃の頭のてっぺんスレスレのところを、『噛みつきフリスビー』が歯を剥き出しながら通り過ぎていった。
「びっくりした……」
そろそろと立ち上がりながら、『フリスビー』が店内を旋回して他の商品を破壊しているのを見ていると、ぽんと肩に手が乗った。「わっ」——飛び上がって振り返ると、ラヴェンダー色の三角帽子をかぶった老人が、淀んだ目で玲乃の顔を覗き込んでいた。
「いらっしゃいませ」
「……びっくりした…」
玲乃は胸を撫で下ろした。老人は早くもたった一人の来客に興味を失い、棚の陳列を数ミリ単位で整え始めた。
「あの——」
帽子と同じ色をしたローブの背中に向かって声をかけたが、返事はない。
「………」
玲乃は改めてグルッと店内を見回した。ここには大体なんでもあるようだ。文房具や悪戯グッズの他にも、日用品やペット用品、護身用グッズも揃っている。きっとこの付近に住んでいる魔法使いや魔女たちは、この店で日頃の買い物を済ませているに違いない。
そうだ。パフスケインの餌と、フィージーにやるふくろうフーズを買っていこう。お金はあるかな?——玲乃は通学鞄から財布を取り出した。玲乃がイギリスの魔法学校に入学した時、両親にお祝いに買ってもらったドラゴン革の財布で、金の留め具がつまみになっている。玲乃がつまみを時計回りに二つ回すと、蓋に貼りつけられた金のプレートに刻印された文字が『日本円』から『ユーロ』を経由し、『ガリオン』に切り替わった。
「すいません、これください」
レジに買い物を置いて老人を呼ぶと、老人は入り口付近の商品棚の向こうからちらりとこちらを一瞥し、その場で杖を一振りした。おんぼろのレジがチンと鳴り、ひとりでに代金を計算した。玲乃は財布からガリオン金貨とシックル銀貨を取り出す。革製のトレーがふわふわ宙に浮き上がり、催促するように玲乃の手元を飛び回っている。
「マホウトコロかね」
レジがつり銭を弾き出し、宙を舞うクヌート銅貨を革製のトレーが左右に揺れながらキャッチしているのを見ていた玲乃は、思いがけない質問に「えっ?」と変な声を上げてしまった。
「マホウトコロの生徒かね?——わしの思い出が正しけりゃ、今は学期中だったと思うが」
「あー——」
ちょっと遅れて、ようやく学校を尋ねられているのだと気付いた。
「ホグワーツです」と、玲乃は答えた。「今は行けてないですけど……」
「ホグワーツ?」
老人の目に突然生気が宿った。
「ダンブルドア先生のところかい」
「はい。でも今は、マグルの高校に行っています」
「……フーム」
老人は顎をさすりながら、再び陳列棚の整頓作業に戻った。
「うちは代々マホウトコロじゃ。わしも息子もそこを出とる」
「そうなんですね」
「孫はホグワーツじゃ。あんたと同じ——結局おられんようになって、空座一高の制服を着ちょる。それもあんたと同じじゃな」
玲乃は唇をきゅっと引き結んだ。
「外国なんぞに出て行くもんじゃないわい。まったく、物騒な時代になったもんじゃ……」
老人は不機嫌そうにぶつくさ言って、店の奥へ消えてしまった。
「おやァ?今お帰りっスかァ?」
『浦原商店』の前を通りかかった玲乃を、間延びした声が呼び止めた。
「えーと……」
初めて会った時と全く同じ格好の店長が、玲乃に向かって手を振っていた。店の奥の畳に腰掛け、片足を膝に乗せてくつろいでいる。
「浦原っスよん♪玲乃チャン」
「……う、浦原、さん。こんにちは…」
「はい!こんにちは」
よくできましたと言うような口ぶりにちょっぴり恥ずかしくなる。玲乃は曖昧に笑った。
「今日、学校だったんスね」
「あ・はい」
「その制服は空座一高っスね!いや〜よくお似合いですよん。カワイイカワイイ」
「……あ…りがとうございます…」
なんと反応したらいいのか分からなくて、玲乃はうつむいた。大人の男の人から「かわいい」だなんて初めて言われてしまった。熱っぽくなったほっぺを隠すように押さえる。どうか気づかれていませんように——そんな玲乃の胸の内など露知らず、浦原は暢気に「やっぱり女子高生はいいっスね〜!肌のハリが眩しくてたまりません」などとギリギリなことを口走っていた。
小学生のはしゃぐ声が、春の陽気な風に乗ってどこからかやってくる。平和で穏やかな、心地よい時間帯だ。
「どうです?お友達はできましたか?」
浦原が立ち上がり、扇子を揺らしながら玲乃の傍へと寄ってくる。微かな風を浴びて、明るい色をした髪の毛がふわふわ揺れた。
「あの……えーっと、はい」
「そースか!それはよかった」
浦原の手がそっと玲乃の背中に当てがわれた。「えっ?」と顔を見上げる玲乃を、浦原は意外にも紳士的な所作で店の中へと誘い込む。
「どうぞ。立ち話も何なんで」
促されるままに畳に上がり、座布団に座ると、卓袱台の上に二人分のお茶が湯気を上げてお出迎えをしていた。まるで、玲乃がやって来るのを予知して待ち構えていたかのように。
「粗茶スけど」
「……あ、ありがとうございます…」
へらり。うさんくさい笑みをたたえた口元を見ながら、玲乃はほんの少しだけ背筋が寒くなった。お茶まで用意して、一体何の用だろう——。
「麗しのお母サマもお元気で?」
身構えた玲乃に肩すかしを食らわせる質問が飛んできた。
「いやァ、最近お母サマお見かけしないもんですから」
「あ、えっと、母は、平日は仕事で出てて……」
「あー、お仕事されてるんスねェ。それじゃお忙しいワケだ」
浦原は湯気の立つ湯飲みに口をつけ、こくりと喉を動かした。それを見て、玲乃もお茶を少しだけ啜る。苦味の強い味だった。
「しっかし、綺麗なお人っスよね。初めてお会いした時、心臓が止まるかと思いましたよ」
「はあ……」
この人、もしかしてママを狙ってるんだろうか——玲乃の緊張が別の色に変わろうとしていた。
「う・うちのマ——お母さん、イギリスとのクォーターなんです」
「へー!」
浦原はなぞなぞが解けた時のような明るい声を上げた。
「道理でお綺麗なわけだ!いやァ〜いいなァ、あんな美人なお母サマ」
「……うち、お父さん、いますよ」
「ハイ?」
「あ、いえ…」
玲乃はごまかすようにもう一口お茶を飲んだ。
ぽんぽんと続いていた会話が途切れ、変な沈黙が下りた。居心地が悪くなって、玲乃は座布団の上でお尻をもぞもぞ動かしたけれど、浦原は何とも感じていないみたいだった。玲乃とは作りの違う、ごつごつして頑丈そうな指が、備前焼の湯呑みをくすぐるように撫でている。その手つきを見ていると、なんだか胸の奥がむずがゆくなってきて、玲乃はパッと目を逸らした。
「そういえば、」
体ごと横を向いていた浦原が、卓袱台に片腕を乗せて玲乃の方を向いた。距離が詰まって、思わず逃げるように姿勢を正してしまう。
「——新しいお家には慣れました?」
玲乃はすぐには答えられず、「えーと」と口ごもった。
「だ・だいぶ……」
「随分年季の入ったお家らしいスけど、困ったこととかありませんか?」
「うーん、特には……」
玲乃は曖昧に笑った。最近は芝生を踏み荒らす庭小人に悩まされているところだが、それを浦原に言うわけにはいかなかった。
「……ちょっと埃っぽいけど、お部屋がたくさんあっていいです」
「はァ〜そうなんスか。まあ、広さはありそうですもんね〜あのお屋敷」
「は・はい。三階から綺麗な夕陽も見えますし…」
「…………」
浦原は何を思ったか少しだけ押し黙って、それから「なるほど」と相槌を打った。
「何かお困りでしたら気兼ねなく言ってくださいね。すぐに飛んでいきますよ!——近所のよしみですから」
「ありがとう…、ございます…」
それが親切なのか、下心なのか、はたまた別の含みがあるのか、玲乃には判別がつかなかった。
「三階……ねェ…」
パチンと閉じた扇子で、首の付け根を叩く。短いスカートをひらひらさせて帰っていく少女の後ろ姿が、オレンジ色に染まった『幽霊屋敷』の中に消えていくのを見届ける。
「アタシには二階建てに見えますけどね……」
検知不可能拡大呪文