
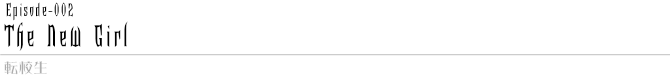
その日の昼休みのうちに、恐怖はホグワーツ中を駆け巡った。「女子更衣室から死体がでた」——まさかこんな恐ろしいことがホグワーツで起きようとは夢にも思っていなかった。それも、新学期が始まってたった一ヶ月で。今日の飛行訓練は中止になったが、誰も文句を言わなかった。グリフィンドールとスリザリンの一年生は、突然ぽっかり空いてしまった一時間をそれぞれのやり方で過ごすことにした。
「僕が思うに、こういうことには慣れておいたほうがいい」
レノーラが談話室のひじ掛け椅子に座って暖炉を眺めていると、どこからともなく双子がやって来て慰めた。
「死体の身元がうちの生徒じゃなくってよかったじゃないか」
「きっと学校内で殺人があったわけじゃない。誰かが夜のうちにコッソリ忍び込んで、死体を捨てたんだ」
「ええ、ありがとう。これでホッとしたわ」
双子のたちが悪いのは、皮肉や嫌味が通用しないところだろう。得意顔で「まあね」と肩をすくめられた時は、頭突きをかましてやりたい衝動に駆られた。
「……あなたたち、こんなところにいていいの?」
休講になったのは一年生だけだと知っていたレノーラは、無意味だと分かっていながら敢えて指摘した。
「スネイプの鼻を縮めるんじゃなかったの?」
「いいか?僕たちにはまだ猶予がある。今日さぼっても、あと四回はセーフだ」
「前期はな」
レノーラは呆れてものを言うどころではなくなった。
肖像画の穴から入ってきたネビル・ロングボトムが、レノーラと双子の奇妙な組み合わせを物珍しそうに見ながら通り過ぎていった。それはそうだろう、双子がレノーラのことを好いていないのは明白な事実だ。それでもなお執拗に絡んでくるのは、くだらない下心があるからだとレノーラは知っていた。双子は先ほどからレノーラに話しかけながら、談話室の中をじっと探るように見回していた。
「飛行訓練は中止になったんじゃなかったか?もう戻ってきてもいい頃だぞ」
「なんでいないんだ?」
二人ともはっきりとは言わなかったが、レノーラには誰のことかがすぐに分かった。
「転入初日だもの。学校見学でもしてるんじゃなくて?中庭とか、大広間とか、図書館とか——」
「図書館!」双子が大袈裟に叫んだ。「バカ言うな。あそこにゃ本しかないんだぜ。あんなところ、試験の前日かレポート提出日の朝でもなきゃ行かないだろう」
レノーラは今度こそ何も言い返す気がしなくなり、大袈裟に首を振って二人に背を向けた。
「よっ。ダコタ」
いきなり真後ろから容赦なく頭をひっぱたかれ、レノーラは大きくつんのめった。振り向くと、細かい三つあみを縮らせた髪型の男の子が、ニヤニヤと双子そっくりの笑みを浮かべてレノーラを見下ろしていた。
「ダコタですって?誰?」
「あれっ?」男の子が不思議そうに眉を寄せた。「おかしいな。君、ダコタじゃないな……金髪だし、フレッドとジョージに絡まれてるからそうかと思ったんだけど…よく見たら両目がちゃんとおんなじ場所についている」
「それから、鼻の頭にどでかいほくろがないぜ」
「それに石頭。純血主義だ」
「そうなの?」男の子が目を丸くした。
「いったいそれのどこが悪いのよ!いい加減ほっといてちょうだいよ」
レノーラはカリカリしながらそのへんにあった本を適当に引っつかみ、読みふけるふりをした。それでもなお、双子のわざとらしい芝居がかった声がしつこくまとわりついてくる。
「リー、こちらは我らの希望の星レノーラ嬢、そう、かの有名なハーグリーヴス家のご令嬢だ。非常に聡明な女性であり、なんと本を逆さまにして読むことができる」
双子の言葉に、レノーラは慌てて本の向きを正した。
「ハーグリーヴスか。あんまりいい噂聞かないけど——僕はリー。よろしく」
レノーラはリーの差し出した右手を冷ややかな目つきで一瞥した。
「あなたってとっても礼儀正しい人なのね。うっとりしちゃうわ」
しかし、リーはちっとも聞いていなかった。
「おい、フレッドだかジョージだか。例の転入生見れたか?」
「全然。飛行訓練の時、こいつをけしかけようと企んでたけど、更衣室から死体がでたせいで計画中止になった」
右側にいた双子が、レノーラの頭を小突きながら言った。レノーラは思わず舌打ちした。
「無駄なことかもしれない提案なんだけど、新入生を『こいつ』呼ばわりするのやめて、あと、少しは被害者のことを悼んでやったらどう?」
双子とリーは一瞬きょとんと目をしばたいたが、三秒ほどしてから、ようやく訳ありげに「あー」と唸った。
「さっきも言ったけど」と双子が切り出した。「こういうこと、慣れておいた方がいいよ」
「慣れるって……ロッカーから死体?」
「死体とまでは言わないけど、ホグワーツには気味の悪いものがそろっているから」
リーはあまりこの手の話題をするのに気が乗らない様子だった。
「だって、ホグワーツは安全な場所なんでしょう?」
レノーラは本を閉じて膝に乗せ、双子とリーに向き合った。
「そりゃあ、まあ安全だろうよ。ダンブルドアがいるかぎりは。けど、サニーデール——ホグワーツ城のある町のことだけど——この町じたいは前から妙な噂が多いんだ。だからダンブルドアはあの暗い『森』に入るなと言ってる。ホグワーツの魔力のせいで、奇妙な魔法生物が集まってきてるのかもしれない…」
レノーラはしばらく沈黙のまま身構え、双子が「なーんちゃって!」とおちゃらけるのを待っていた。ところが、どちらも何も言わない。恐る恐るリーの顔色を窺ってみると、暗い面持ちで小さくうなずきかけてきた。
「ほ、ほんとの話なの…?」
「ああ。大マジさ。途中でふざけようと思ってたけど忘れた」
双子のどちらかがヒョイと肩をすくめた。
レノーラは愕然とした。なんだかとんでもない詐欺にあわされた気分だった。いくらあのダンブルドアがいるとはいえ、そんな危険が潜んでいる学校だったなんて。「前から」って、どれくらい前からだろう?ひょっとして、ホグワーツ出身の両親はこのことを知っていたのだろうか?
「気をつけたまえよ、ハーグリーヴス嬢」
完全に怖じ気づいたレノーラに向かって、双子が追い討ちをかけた。からかわれていると分かっていても、いつもみたいに無視したり反抗したりできるほどの余裕はなかった。
「迂闊に『森』へ近づくと食われるぞ」
「吸血鬼」
「ゾンビ」
「悪霊」
「狼人間」
「何でも出るぜ。なーんでも。舌なめずりしながら、若い生き血を啜る機会を窺ってるんだ」
双子のウィーズリーが余計に煽るものだから、すっかり妙な警戒心が芽生えてしまった。これまではスリザリンとマグル生まれに関わらないように意識しているだけでよかったのに、今は人気のない廊下を歩くのが怖い。見方が変わると、ホグワーツ城はとても不気味なところに思えた。冷たく湿った石の廊下、遠くに見え隠れする銀色のゴースト、ヒューヒューと吹き込むすきま風、頼りなく揺れる松明……。日が傾きだして、窓から差し込む光が弱々しくなってくると、さらに雰囲気が増す。
夕食を取りに大広間に向かったところまではよかった。だが、ひとりぼっちで友達と談笑することもないレノーラは、誰よりも早く食事を終え、賑わしい大広間の中で手持ち無沙汰になってしまった。仕方なく一足先に寮へ引き返そうと席を立ち上がったのだが、すぐに大広間を抜け出したことを後悔し始めた。
「寮ってこんなに遠かったっけ?」
レノーラは、光を失いどっぷりと闇に浸かった窓の外を見て足を速めた。どこかから誰かに見られているような気がする。その奇妙な感覚は寮を出てひとりきりになった時からずっとつきまとっていた。早く人通りのある場所に出たかったが、『太った婦人』までの道のりは気が遠くなるほど複雑で長い。フィルチや双子が駆使している秘密の通路を、使えたらいいのに——。レノーラは階段を一段飛ばしで駆け下り、次の曲がり角に駆け込んだ。
「アイタッ」
角を曲がった拍子に、巨大な壁のようなものに衝突してしまった。レノーラは強い力ではね飛ばされて、無様に尻餅をついた。
「ちょっと。どこ見て歩いてるのよ」
「ご、ごめん……」
相手はオドオドしながら謝った。そのゴリラみたいな野太い声には聞き覚えがあった。見上げた先には、ビンセント・クラッブが両腕いっぱいのお菓子の山を抱えて佇んでいた。
「あら。あなただったの」
レノーラが眉をつり上げると、クラッブはまた「ごめん」と謝った。いつの間にかあの気味の悪い感覚はきれいさっぱり消し飛んでいた。その代わり、気まずさにソワソワする羽目になった。お互い、何を話したらいいのか分からなかったのだ。マルフォイ一味とこうして顔を合わせるのは、入学式の日以来のことだった。
「おい、クラッブ。そこで何やってるんだ。忘れ物を取りに行くんじゃなかったのか」
気取った声がして、クラッブの巨体の後ろから、ゴイルを引きつれたドラコ・マルフォイが現れた。マルフォイはレノーラの顔を見ると、あからさまに嫌そうな顔をした。レノーラは思わず身をすくめた。
「なんだ。何ごとかと思えば、ハーグリーヴスじゃないか」
マルフォイが冷ややかに言った。ダイアゴン横丁や列車の中で会ったときとはまるで違う態度だ。改めてきつい目を向けられると、胃袋をぎゅっと掴まれたような感覚がする。
「久しぶりだな。グリフィンドールではうまくやっているかい?傷モノのポッターや貧乏のウィーズリーなんかと一緒に暮らせるだなんて、さぞかし楽しい毎日なんだろうねぇ。君が羨ましいよ」
レノーラがうまく言い返せないでいると、廊下は不自然なほどシーンとした。マルフォイが肘でクラッブの土手っ腹をつつくと、クラッブとゴイルは慌ててフガフガ笑い出した。レノーラはきっと二人が「手の平を返す」という行為を知らなかったに違いないと思った。
「そういえば、クレイオスおじさまから僕のところへ手紙が届いたよ」
レノーラの眉がピクリと動いた。マルフォイは気にせず続けた。
「君の返信が遅いから、おじさまはとても心配してるようだよ」
返事の催促にマルフォイをよこすなんて、一体どういう神経をしてるんだろう。アステリアが知ったら白目をむいて倒れるだろうとレノーラは思った。
「僕は君のお父上にとても信頼されているんだ。だから君の様子を聞くよう頼まれた」
マルフォイがぐっと顔を近づけてきた。意地悪く細められたアイスブルーの瞳がレノーラをまっすぐと射すくめた。居心地は悪いが、ここで目を逸らしたら負けてしまうような気がして、レノーラは辛抱強く見つめ返した。
「おじさまはいつまで待っても返信がこないわけを知りたがってらっしゃる。いったいどうしたっていうんだい?ご両親の手紙を無視するなんてひどいんじゃないか?羽根ペンを握れないわけでもあるのかい?それとも何か後ろめたいことがあるとか?」
答えなんて分かりきっているのに、マルフォイはレノーラの口から直接聞きたがった。レノーラは口を真一文字に結んだまま、何も言わなかった。
「あぁ、そうだ」
マルフォイはレノーラの頑な表情を見てほくそ笑んだ。
「僕がかわりに返事を書いてあげようか?」
レノーラは目を見開いた。マルフォイはますます楽しそうにニヤニヤした。
「『親愛なるクレイオスおじさま、お嬢さんはスリザリンに入ることすらできず、授業ではへまばかりで、お二人の顔に泥を塗っています』って。何だよ、またお得意の無視かい?」
遊ばれているんだ——レノーラは悔しくて、奥歯をギリッと噛みしめた。マルフォイはレノーラの反応を見て、楽しんでいる。ここで「やめて」と泣き叫んだら、マルフォイの思うつぼだ。だからといって目の前のしたり顔を歪められるようなうまい皮肉も思いつかず、レノーラは沈黙を貫き通すしかなかった。
五分、十分、いやもっと長く感じた——とにかく長い時間二人は言葉もなく睨み合っていたが、やがて、大広間から溢れ出してきた喧騒が終わりを告げた。食事を終えたばかりで上機嫌な生徒たちの流れに呑み込まれて、マルフォイの姿はあっという間に見えなくなった。レノーラは涙が出そうになった目元を乱暴に袖で拭い、鼻をすすってグリフィンドール塔へ走り出した。
レノーラは誰よりも早く玄関ホールを抜け、誰よりも早く外へ飛び出し、一目散に塔へ駆け戻った。途中、転校生に声をかけられた気がしたが、「知らない」と突っぱねて走った。相当ひどい顔をしていたらしく、『太った婦人』はレノーラを見るなり「まあ、一体どうしたの?」と心配したが、事情を説明して慰めてもらう気にはならなかった。どうせ何も知らないんだから、下手に同情なんてしてくれなくていいのに……。
「ようスリザリンもどき!」
談話室に飛び込むなり、何も知らない双子が陽気に話しかけてきた。
「トフィーに好きなタイプ聞いてきてくれたかい?」
「顔よく見て!少しは——同情——しなさいよ!」
理不尽に怒鳴りつけられ、困ったように両手を広げている双子を置き去りにして、レノーラは寝室に駆け込んだ。服を脱ぎ捨て、パジャマに袖を通し、ベッドに飛び乗った。まだ宿題に手をつけてないことに気づいたが、どうでもよかった。とにかく早く眠ってしまいたかった。ところが、頭の中の興奮がなかなか収まりきらないせいで、ちっとも眠気がやってこない。
レノーラは、やけに進みの遅い秒針を睨みつけながら、頬を涙が伝うのを感じていた。枕に冷たい染みがじんわりと広がっていく。堪えなきゃ。堪えるのよ、レノーラ——崩壊してしまいそうな脳みそに向かって、レノーラは必死に言い聞かせた。黙って堪えていれば、きっと時間が解決してくれるわ……。
その日、真夜中になるまでウィローが帰って来なかった。
「僕が思うに、こういうことには慣れておいたほうがいい」
レノーラが談話室のひじ掛け椅子に座って暖炉を眺めていると、どこからともなく双子がやって来て慰めた。
「死体の身元がうちの生徒じゃなくってよかったじゃないか」
「きっと学校内で殺人があったわけじゃない。誰かが夜のうちにコッソリ忍び込んで、死体を捨てたんだ」
「ええ、ありがとう。これでホッとしたわ」
双子のたちが悪いのは、皮肉や嫌味が通用しないところだろう。得意顔で「まあね」と肩をすくめられた時は、頭突きをかましてやりたい衝動に駆られた。
「……あなたたち、こんなところにいていいの?」
休講になったのは一年生だけだと知っていたレノーラは、無意味だと分かっていながら敢えて指摘した。
「スネイプの鼻を縮めるんじゃなかったの?」
「いいか?僕たちにはまだ猶予がある。今日さぼっても、あと四回はセーフだ」
「前期はな」
レノーラは呆れてものを言うどころではなくなった。
肖像画の穴から入ってきたネビル・ロングボトムが、レノーラと双子の奇妙な組み合わせを物珍しそうに見ながら通り過ぎていった。それはそうだろう、双子がレノーラのことを好いていないのは明白な事実だ。それでもなお執拗に絡んでくるのは、くだらない下心があるからだとレノーラは知っていた。双子は先ほどからレノーラに話しかけながら、談話室の中をじっと探るように見回していた。
「飛行訓練は中止になったんじゃなかったか?もう戻ってきてもいい頃だぞ」
「なんでいないんだ?」
二人ともはっきりとは言わなかったが、レノーラには誰のことかがすぐに分かった。
「転入初日だもの。学校見学でもしてるんじゃなくて?中庭とか、大広間とか、図書館とか——」
「図書館!」双子が大袈裟に叫んだ。「バカ言うな。あそこにゃ本しかないんだぜ。あんなところ、試験の前日かレポート提出日の朝でもなきゃ行かないだろう」
レノーラは今度こそ何も言い返す気がしなくなり、大袈裟に首を振って二人に背を向けた。
「よっ。ダコタ」
いきなり真後ろから容赦なく頭をひっぱたかれ、レノーラは大きくつんのめった。振り向くと、細かい三つあみを縮らせた髪型の男の子が、ニヤニヤと双子そっくりの笑みを浮かべてレノーラを見下ろしていた。
「ダコタですって?誰?」
「あれっ?」男の子が不思議そうに眉を寄せた。「おかしいな。君、ダコタじゃないな……金髪だし、フレッドとジョージに絡まれてるからそうかと思ったんだけど…よく見たら両目がちゃんとおんなじ場所についている」
「それから、鼻の頭にどでかいほくろがないぜ」
「それに石頭。純血主義だ」
「そうなの?」男の子が目を丸くした。
「いったいそれのどこが悪いのよ!いい加減ほっといてちょうだいよ」
レノーラはカリカリしながらそのへんにあった本を適当に引っつかみ、読みふけるふりをした。それでもなお、双子のわざとらしい芝居がかった声がしつこくまとわりついてくる。
「リー、こちらは我らの希望の星レノーラ嬢、そう、かの有名なハーグリーヴス家のご令嬢だ。非常に聡明な女性であり、なんと本を逆さまにして読むことができる」
双子の言葉に、レノーラは慌てて本の向きを正した。
「ハーグリーヴスか。あんまりいい噂聞かないけど——僕はリー。よろしく」
レノーラはリーの差し出した右手を冷ややかな目つきで一瞥した。
「あなたってとっても礼儀正しい人なのね。うっとりしちゃうわ」
しかし、リーはちっとも聞いていなかった。
「おい、フレッドだかジョージだか。例の転入生見れたか?」
「全然。飛行訓練の時、こいつをけしかけようと企んでたけど、更衣室から死体がでたせいで計画中止になった」
右側にいた双子が、レノーラの頭を小突きながら言った。レノーラは思わず舌打ちした。
「無駄なことかもしれない提案なんだけど、新入生を『こいつ』呼ばわりするのやめて、あと、少しは被害者のことを悼んでやったらどう?」
双子とリーは一瞬きょとんと目をしばたいたが、三秒ほどしてから、ようやく訳ありげに「あー」と唸った。
「さっきも言ったけど」と双子が切り出した。「こういうこと、慣れておいた方がいいよ」
「慣れるって……ロッカーから死体?」
「死体とまでは言わないけど、ホグワーツには気味の悪いものがそろっているから」
リーはあまりこの手の話題をするのに気が乗らない様子だった。
「だって、ホグワーツは安全な場所なんでしょう?」
レノーラは本を閉じて膝に乗せ、双子とリーに向き合った。
「そりゃあ、まあ安全だろうよ。ダンブルドアがいるかぎりは。けど、サニーデール——ホグワーツ城のある町のことだけど——この町じたいは前から妙な噂が多いんだ。だからダンブルドアはあの暗い『森』に入るなと言ってる。ホグワーツの魔力のせいで、奇妙な魔法生物が集まってきてるのかもしれない…」
レノーラはしばらく沈黙のまま身構え、双子が「なーんちゃって!」とおちゃらけるのを待っていた。ところが、どちらも何も言わない。恐る恐るリーの顔色を窺ってみると、暗い面持ちで小さくうなずきかけてきた。
「ほ、ほんとの話なの…?」
「ああ。大マジさ。途中でふざけようと思ってたけど忘れた」
双子のどちらかがヒョイと肩をすくめた。
レノーラは愕然とした。なんだかとんでもない詐欺にあわされた気分だった。いくらあのダンブルドアがいるとはいえ、そんな危険が潜んでいる学校だったなんて。「前から」って、どれくらい前からだろう?ひょっとして、ホグワーツ出身の両親はこのことを知っていたのだろうか?
「気をつけたまえよ、ハーグリーヴス嬢」
完全に怖じ気づいたレノーラに向かって、双子が追い討ちをかけた。からかわれていると分かっていても、いつもみたいに無視したり反抗したりできるほどの余裕はなかった。
「迂闊に『森』へ近づくと食われるぞ」
「吸血鬼」
「ゾンビ」
「悪霊」
「狼人間」
「何でも出るぜ。なーんでも。舌なめずりしながら、若い生き血を啜る機会を窺ってるんだ」
†††
双子のウィーズリーが余計に煽るものだから、すっかり妙な警戒心が芽生えてしまった。これまではスリザリンとマグル生まれに関わらないように意識しているだけでよかったのに、今は人気のない廊下を歩くのが怖い。見方が変わると、ホグワーツ城はとても不気味なところに思えた。冷たく湿った石の廊下、遠くに見え隠れする銀色のゴースト、ヒューヒューと吹き込むすきま風、頼りなく揺れる松明……。日が傾きだして、窓から差し込む光が弱々しくなってくると、さらに雰囲気が増す。
夕食を取りに大広間に向かったところまではよかった。だが、ひとりぼっちで友達と談笑することもないレノーラは、誰よりも早く食事を終え、賑わしい大広間の中で手持ち無沙汰になってしまった。仕方なく一足先に寮へ引き返そうと席を立ち上がったのだが、すぐに大広間を抜け出したことを後悔し始めた。
「寮ってこんなに遠かったっけ?」
レノーラは、光を失いどっぷりと闇に浸かった窓の外を見て足を速めた。どこかから誰かに見られているような気がする。その奇妙な感覚は寮を出てひとりきりになった時からずっとつきまとっていた。早く人通りのある場所に出たかったが、『太った婦人』までの道のりは気が遠くなるほど複雑で長い。フィルチや双子が駆使している秘密の通路を、使えたらいいのに——。レノーラは階段を一段飛ばしで駆け下り、次の曲がり角に駆け込んだ。
「アイタッ」
角を曲がった拍子に、巨大な壁のようなものに衝突してしまった。レノーラは強い力ではね飛ばされて、無様に尻餅をついた。
「ちょっと。どこ見て歩いてるのよ」
「ご、ごめん……」
相手はオドオドしながら謝った。そのゴリラみたいな野太い声には聞き覚えがあった。見上げた先には、ビンセント・クラッブが両腕いっぱいのお菓子の山を抱えて佇んでいた。
「あら。あなただったの」
レノーラが眉をつり上げると、クラッブはまた「ごめん」と謝った。いつの間にかあの気味の悪い感覚はきれいさっぱり消し飛んでいた。その代わり、気まずさにソワソワする羽目になった。お互い、何を話したらいいのか分からなかったのだ。マルフォイ一味とこうして顔を合わせるのは、入学式の日以来のことだった。
「おい、クラッブ。そこで何やってるんだ。忘れ物を取りに行くんじゃなかったのか」
気取った声がして、クラッブの巨体の後ろから、ゴイルを引きつれたドラコ・マルフォイが現れた。マルフォイはレノーラの顔を見ると、あからさまに嫌そうな顔をした。レノーラは思わず身をすくめた。
「なんだ。何ごとかと思えば、ハーグリーヴスじゃないか」
マルフォイが冷ややかに言った。ダイアゴン横丁や列車の中で会ったときとはまるで違う態度だ。改めてきつい目を向けられると、胃袋をぎゅっと掴まれたような感覚がする。
「久しぶりだな。グリフィンドールではうまくやっているかい?傷モノのポッターや貧乏のウィーズリーなんかと一緒に暮らせるだなんて、さぞかし楽しい毎日なんだろうねぇ。君が羨ましいよ」
レノーラがうまく言い返せないでいると、廊下は不自然なほどシーンとした。マルフォイが肘でクラッブの土手っ腹をつつくと、クラッブとゴイルは慌ててフガフガ笑い出した。レノーラはきっと二人が「手の平を返す」という行為を知らなかったに違いないと思った。
「そういえば、クレイオスおじさまから僕のところへ手紙が届いたよ」
レノーラの眉がピクリと動いた。マルフォイは気にせず続けた。
「君の返信が遅いから、おじさまはとても心配してるようだよ」
返事の催促にマルフォイをよこすなんて、一体どういう神経をしてるんだろう。アステリアが知ったら白目をむいて倒れるだろうとレノーラは思った。
「僕は君のお父上にとても信頼されているんだ。だから君の様子を聞くよう頼まれた」
マルフォイがぐっと顔を近づけてきた。意地悪く細められたアイスブルーの瞳がレノーラをまっすぐと射すくめた。居心地は悪いが、ここで目を逸らしたら負けてしまうような気がして、レノーラは辛抱強く見つめ返した。
「おじさまはいつまで待っても返信がこないわけを知りたがってらっしゃる。いったいどうしたっていうんだい?ご両親の手紙を無視するなんてひどいんじゃないか?羽根ペンを握れないわけでもあるのかい?それとも何か後ろめたいことがあるとか?」
答えなんて分かりきっているのに、マルフォイはレノーラの口から直接聞きたがった。レノーラは口を真一文字に結んだまま、何も言わなかった。
「あぁ、そうだ」
マルフォイはレノーラの頑な表情を見てほくそ笑んだ。
「僕がかわりに返事を書いてあげようか?」
レノーラは目を見開いた。マルフォイはますます楽しそうにニヤニヤした。
「『親愛なるクレイオスおじさま、お嬢さんはスリザリンに入ることすらできず、授業ではへまばかりで、お二人の顔に泥を塗っています』って。何だよ、またお得意の無視かい?」
遊ばれているんだ——レノーラは悔しくて、奥歯をギリッと噛みしめた。マルフォイはレノーラの反応を見て、楽しんでいる。ここで「やめて」と泣き叫んだら、マルフォイの思うつぼだ。だからといって目の前のしたり顔を歪められるようなうまい皮肉も思いつかず、レノーラは沈黙を貫き通すしかなかった。
五分、十分、いやもっと長く感じた——とにかく長い時間二人は言葉もなく睨み合っていたが、やがて、大広間から溢れ出してきた喧騒が終わりを告げた。食事を終えたばかりで上機嫌な生徒たちの流れに呑み込まれて、マルフォイの姿はあっという間に見えなくなった。レノーラは涙が出そうになった目元を乱暴に袖で拭い、鼻をすすってグリフィンドール塔へ走り出した。
レノーラは誰よりも早く玄関ホールを抜け、誰よりも早く外へ飛び出し、一目散に塔へ駆け戻った。途中、転校生に声をかけられた気がしたが、「知らない」と突っぱねて走った。相当ひどい顔をしていたらしく、『太った婦人』はレノーラを見るなり「まあ、一体どうしたの?」と心配したが、事情を説明して慰めてもらう気にはならなかった。どうせ何も知らないんだから、下手に同情なんてしてくれなくていいのに……。
「ようスリザリンもどき!」
談話室に飛び込むなり、何も知らない双子が陽気に話しかけてきた。
「トフィーに好きなタイプ聞いてきてくれたかい?」
「顔よく見て!少しは——同情——しなさいよ!」
理不尽に怒鳴りつけられ、困ったように両手を広げている双子を置き去りにして、レノーラは寝室に駆け込んだ。服を脱ぎ捨て、パジャマに袖を通し、ベッドに飛び乗った。まだ宿題に手をつけてないことに気づいたが、どうでもよかった。とにかく早く眠ってしまいたかった。ところが、頭の中の興奮がなかなか収まりきらないせいで、ちっとも眠気がやってこない。
レノーラは、やけに進みの遅い秒針を睨みつけながら、頬を涙が伝うのを感じていた。枕に冷たい染みがじんわりと広がっていく。堪えなきゃ。堪えるのよ、レノーラ——崩壊してしまいそうな脳みそに向かって、レノーラは必死に言い聞かせた。黙って堪えていれば、きっと時間が解決してくれるわ……。
その日、真夜中になるまでウィローが帰って来なかった。