
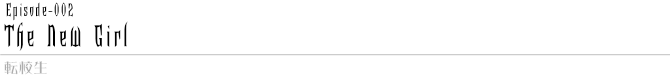
レノーラへ
ホグワーツでの学校生活が始まって、もう三週間が経ちますね。調子はどうですか。お友達はできましたか。お勉強ははかどっているでしょうか。
あなたからの連絡がないので、パパもママも寂しいです。
追伸 手紙に返信用の羊皮紙を持たせました。どの寮の所属になったか教えてくださいね。アステリア・ハーグリーヴス
どうしてこんな余計な手紙を寄越すのだろう。レノーラはかたいパンを飲み込みながら頭を抱えた。
ホグワーツでは、朝食の間に郵便配達の時間がやってくる。何百羽というふくろうが窓からなだれ込み、天井の真下を旋回しながら、手紙や小包を飼い主の膝に落としていくので、いつもそこで食事は中断された。ハーグリーヴス家のふくろう——名前は忘れた——は、これまでに何度かお菓子や洋服の包みを運んできたことはあったが、手紙を運んできたのは今日が初めてだった。
——『追伸』?バカバカしい。そんなこと言って、一番言いたいことは、これなんでしょう。
いつかは組分けの報告を催促する手紙がくると分かっていたので、この場合どう対処するか、実は前もって答えを決めていた。レノーラはふくろうの足に返信の手紙はつけず、手ぶらのまま飛び立たせた。娘が手紙を無視していると分かれば、何かよからぬことが起きたのだと悟ってくれるだろう。高窓をくぐり抜けて青空に溶けだしたふくろうを見送り、重たい溜め息を口にした。
あえて母親の手紙に答えを返すとするならば、調子は「あんまり」だった。何せ、スリザリン生の陰険さはひどすぎる。コーディリアは相変わらず顔を突き合わせるたびに髪型に文句をつけてきたし、マルフォイは隙あらば『くらげ足の呪い』を試そうとし、スネイプはレノーラが何かへまをするたびに両親と比べて嫌味を言った。スリザリン生たちの猛攻に比べたら、ウィーズリーの双子が「スリザリンもどき」と呼んでからかうことなど、ヒヨコのフン程度に思えた——もっとも、夕食のキドニーパイをこっそり『ゴキブリゴソゴソ豆板』にすり替えられたときは、さすがに『くらげ足の呪い』を試してみようかと思ったが。
とはいえ、一年生ではグリフィンドールとスリザリンが一緒になるクラスは『魔法薬学』だけだったので、週に一度スネイプとまとめてやってくる災難を耐え忍べば、あとは「まあまし」な学校生活と言えた。授業だって悪い面ばかりではない。マクゴナガル先生の授業は毎回難しいことばかりだったが、セドリックが言ったとおり、やりがいはある。カレンダー先生と星を眺めるのも、スプラウト先生と泥まみれになって薬草やきのこを育てるのも、存外におもしろかった。
交友関係についても、当初心配していたほど問題にはならなかった。結局、グリフィンドールで友達に最適な子を見つけるのは不可能だったが、ひとりきりでも特に差し支えはなかった。休み時間は教室移動でほとんど潰すことができたし、昼休みは図書館で本を漁り、夕食後から就寝時間までは、毎日山のように課される宿題をこなしていれば、難なく暇をごまかすことができた。
しかし、十月に入って最初の朝、グリフィンドールの談話室に掲示された新しい「お知らせ」を読んで、レノーラはどん底に突き落とされた。
飛行訓練は今週の木曜日に始まります。グリフィンドールとスリザリンの合同授業です。
「そらきた。何でもお望みどおりだ」
レノーラのそばで、ハリーが失望した声で呟いた。
「マルフォイの目の前で箒に乗って、物笑いの種になるのさ」
飛行訓練の日が近づくにつれて、確かにマルフォイの飛行自慢をよく聞くようになった。その話は飽きるほど長ったらしかったが、なぜかいつも、マグルの乗ったヘリコプターを紙一重でかわすところで終わった。飛行術の自慢話をするのは、何もマルフォイだけではなかった。特に純血の魔法族の子たちは、そろってクィディッチの話をしたがった。テイラーは、子どもの頃、いつもサニーデール町の上空を飛び回っていたことを自慢していたし、ロンでさえ、ハリーのいないところでは、兄のお古の箒でハンググライダーにぶつかりそうになった時の話をしていた。結局のところ、みんな『マグル生まれ』と同じスタートラインに立っていると思われたくないのだ。「人間みんな平等」などと唱えているのは、嫌われないための建前にすぎないのだろう。そう思ったレノーラは、純血の子たちの『正しい変化』に大いに満足した。
ところが、木曜日当日になると、飛行訓練の話題はいっさい耳にしなくなった。そればかりか、奇妙なことが起こった。朝、レノーラが朝食をとりに大広間へ下りると、どういうわけか双子のウィーズリーに機嫌取りをされた。トーストとはちみつ壷を手渡され、ヨーグルトをよそわれ、いったい何を企んでいるのと問いつめようとしたところ、深々と礼をしてずらかってしまった。レノーラはトーストのにおいを嗅ぎ、はちみつ壷を覗き込んだが、ゴキブリはどこにも潜んでいなかった。
「変なウィーズリー」
そういえば、様子が変なのは双子だけではない。今日は初めての飛行訓練の日だというのに、一年生は何か別のことでソワソワしているように見える。
「ねえ、あの子じゃない?」
突然、話したこともないハッフルパフの女子生徒に指をさされ、レノーラは驚いた。
「違うったら。あの子ならずっといたわ」
「嘘。いなかったわ。初めてよ」
「他にそれらしい子いないわよ…」
失礼ね!レノーラはわけも分からずぷりぷりした。どういうつもりなのかしら。まるで、私を影が薄いみたいに扱うなんて——「どういうつもりか」は、テイラーによってもたらされた噂話で明らかになった。
「今日、転校生が来るってよ」
レノーラがトーストにはちみつを塗っていると、テイラーが興奮気味に急き込んできた。いつもなら無視して食事を続けるところだったが、話題が話題なだけに、レノーラはつい食いついてしまった。
「転校生?新学期始まったばかりなのに?」
「女の子だって!私たちと同い年。ザンダーが城門前で見たって言ってたわ」
レノーラはもう一度「新学期始まったばかりよ」とつっこんだが、テイラーは聞く耳持たずだ。レノーラの背後に向かって「ハリー!」と叫び、さっさと行ってしまった。どうやら、視界に入った知り合いを片っ端からつかまえて、自分が手に入れた珍しいニュースを吹聴して回っていたようだ。
「呆れた」
子どもみたいにはしゃぐテイラーたちを見て、レノーラはやれやれと首を振った。
「私たちと同い年って……私たち新入生よ!今の時期に転校生なんて来るわけないじゃない」
レノーラの考えは、朝一番の『魔法史』のクラスでものの見事に打ち砕かれた。ハーマイオニーの隣に見たことのないブロンドの女の子が座っていて、一緒に授業を受けていたのだ。
「——この四年間に、およそ二五〇〇万人のマグルが亡くなったと見積もられています…でも面白いのは、『黒死病』がなぜヨーロッパで発生したかということであり…原因は、初期の最近戦争とも言われております…」
ビンズ先生の講義は今日も手強く、生徒たちを次々に夢の世界へ陥れていたが、レノーラは驚くあまり、眠気が吹き飛んでしまった。まさかテイラーの言っていたことが本当だったなんて!
レノーラは筆記用具をしまい込んだままノートもとろうとせず、じっと転校生を観察していた。女の子は人形みたいに可愛らしかった。真っ白い肌、大きなアーモンド型の目、完璧な角度の睫毛。それにくわえて、とってもおしゃれだ。髪型はバッチリ決まっているし、爪も綺麗な色に塗られている。転校生が目の覚めるような美少女だなんて、陳腐な小説の中だけだと思っていた。
「……六十三ページの地図を見れば、この伝染病がどういう経路でローマ、更にはその北に広がったかが分かるでしょう…」
女の子がパッと顔を上げ、不安そうにキョロキョロし始めた。レノーラはずっと見つめていたことに気づかれないよう慌てて顔を伏せ、六十三ページを探すのに手間取るふりを決め込んだ。
それからまた二言三言進んだところで、終業を告げるチャイムが目覚ましのように鳴り響いた。生徒たちは魔法が解けたように目覚め、手早く荷物をしまって一斉に席を立ち上がった。
「ハーイ。ハーマイオニーよ」
さっそくハーマイオニーが転校生と握手をかわしていた。
「あたしバフィー」と、転校生が名乗った。
「ハーイ。もし教科書がないなら、図書室に行けば多分貸し出してくれるわ」
「本当?よかった!図書室ってどこ?」
バフィーが気軽に訪ねたところで、ハーマイオニーは突然押し黙った。バフィーの背後にコーディリアが立っていたからだ。転校生の噂を知っていたのは、グリフィンドール生だけではなかった。
「あたしが、連れてってあげる」
「コ、コーディリア…ハーイ」
ハーマイオニーの顔は引きつっていた。バフィーは不思議そうに首を傾げていたが、レノーラにはその理由が痛いほどよく分かった。コーディリアがハーマイオニーのボサボサ頭に関して、何も言わなかったはずがない。彼女にいびられたことのある人は、みんな今のハーマイオニーとまったく同じ表情をするのだ。
「あら、ハーミー。今日も素敵ね」
深読みしなくても皮肉だと分かった。コーディリアはさっさと背を向け、バフィーに先立ち教室を出て行った。バフィーはハーマイオニーに笑顔を残し、急いでコーディリアの後を追いかけていった。
「あんた、ロサンゼルスのヘムリーから来たんでしょう?」
「ええ」バフィーが短く答えた。
「L.Aなんて憧れちゃう!だって靴屋がいっぱいあるんだもん」
さっきまではとっても魅力的な女の子に見えたのに——レノーラはがっかりした。家族の姓を確認して、もしよかったら友達になってもらうつもりだったが、二人で仲睦まじく笑い合っている姿を見たら、そんな気はすっかり失せてしまった。どんなに見た目がかわいかろうが、コーディリアのブロンド版ではこっちから願い下げだ。小股でよちよちと遠ざかっていく女の子たちを見送って、レノーラは静かに立ち上がった。授業中には珍しくも確かにあった気持ちの高まりは、嘘のようにしぼんでいた。
†††
昼休みになって食事をとりに向かうと、大広間は転校生の話でもちきりだった。レノーラはすでに興味を失っていたので、聞き耳を立てることすらしなかった。みんなの騒ぎようときたら、ほとほと呆れてしまう。ハリーについてあれこれ言っていたときと全くおんなじじゃない。レノーラがテーブルの奥からサンドイッチの皿を引き寄せると、その荒々しさに怯えて、正面にいたネビルが席を替えた。
「やぁ、レノーラ」
「調子はどうだい?」
ドスンドスンと背中を殴られ、レノーラは危うくサンドイッチの山に顔を突っ込むところだった。
「レノーラ!お前、同じ学年だろう。噂の美少女転校生、どうだった?」
せっかくひとりでゆっくり食べようと思ったのに、あっという間に両隣の席がふさがってしまった。レノーラはげんなりして双子を睨みつけた。
「あなたたち、よく友達面して話しかけられるわね」
「そう言うなよ。俺たち、親しみを込めて呼んでるんだぜ——『スリザリンもどき』って」
レノーラはぎらりと右側を睨みつけた。双子は肩をすくめた。
「金髪で、背はこんくらい(レノーラは自分の鼻の辺りに手をかざした)、名前はバフィー、LA出身、頭悪そうでコーディリアと仲が良い!これでいい?満足したらさっさとあっち行ってよ」
「オエー、マジかよ。コーディリア!」
双子の右側が悔しげに膝を叩いた。
「あのマルフォイにインクをぶっかけて女にしたみたいなやつか」
「レノーラにインクぶっかけて美人にしたみたいともいうな」
「俺は気にしないぜ。『かわいい』は正義だ」
レノーラは呆れて目玉でぐりぐりと天を仰いだ。まったく!男の子ときたら!
「次、一年生は飛行訓練だろう?」
今度は双子の左側が先にしゃべり出した。レノーラは相づちを打つのも面倒臭く、黙ってサンドイッチにかじりついた。大嫌いなラム肉だった。
「ぜひとも清楚可憐な転校生を拝みにいきたいところなんだが、まことに残念ながら、俺たちはスネイプと『萎び無花果』の皮をむかなきゃならない。どうしても外せない用事でね——奴のでかっ鼻にうっかり『縮み薬』をぶっかけちまう予定なんだ」
あまりにも真面目くさって言うので、レノーラは必死でふき出したいのを堪えた。
「そこでだ。君が、その『バフィー』って子に、それとなく好みのタイプとか聞いてきてくれないかな」
「そういうのは、自分で聞くか友達に頼むかしてくれないかしら」
レノーラはサンドイッチを皿に放り投げた。
「何言ってるんだ。俺たちとレノーラの仲だろう?」
双子の左側が、レノーラの顎を指先でするりとなで上げた。レノーラはゾッとして身を引いた。その隙に、双子の右側が横からひょいと手を伸ばし、かじりかけのサンドイッチをつかんで口の中に放り込んだ。レノーラは唖然としたが、双子は何とでもないというようにおどけて見せた。
「ほらね」
「無理だわ。他人の食べかけを平気で頬張れる人なんかと、『俺たちの仲』なんて言われたくない!」
「俺、君のこと妹みたいに思ってるよ」右側が口の中をラム肉でいっぱいにして言った。「だから、ほら、聞いてきてくれよ。俺たちは学年が違うから、その『ダフィー』って子と顔を合わせる機会がないんだ。でも君はおんなじ学年だし、同性どうしで話もしやすい。まさに適任だと思うんだ」
ついにレノーラは爆発した。
「嫌だと言ったら嫌なのよ!相手の名前を覚えてから出直してきなさい!!」
†††
昼休みも終わる頃、スリザリン寮の女子生徒たちはクィディッチ競技場の更衣室で服を着替えていた。更衣室の中はすでにスリザリン生でいっぱいだ。アフロディシア・キングズベリーは友達のオーラと空きのロッカーを探しながら、新しく来た生徒についてうわさ話を広げていた。
「今度来た子、なんか変なのよねぇ。『バフィー』なんて妙な名前!」
「アフロディシア」
着替えを終えたパンジー・パーキンソンが、通りすがりに声をかける。アフロディシアは一瞬だけ彼女を振り向いたが、それどころではないとばかりに申し訳程度の挨拶を返した。「あぁ、ハーイ」
「なんでも噂じゃ、彼女退学になったんだって!」
アフロディシアが椅子に腰を下ろすと、オーラが物知り顔で情報を提供した。
「それで母親も転職したって」
「ウソー!」アフロディシアはまさかという口ぶりだ。
「ホントよ。大ゲンカしたって!」
「マジで?」
「とにかくブルーから聞いた話じゃ——」
椅子に荷物を下ろしてロッカーを開いた時、オーラの噂話はつんざくような絶叫に変わった。開けたロッカーから、紫色に青ざめた変死体が彼女に倒れかかってきたのだ!
「ぎゃあああぁぁああああああああぁぁぁああぁぁぁぁああぁ!」
ロッカールームは一瞬にして女生徒たちの悲鳴に包まれた。オーラはクィディッチ選手も目を見張るような素早い動きで死体から飛び退き、頭を抱え、声の枯れるまで叫び続けた。